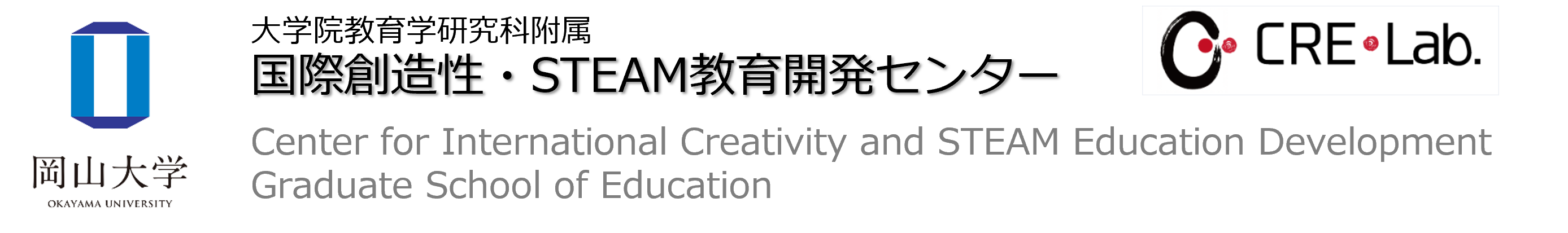インタビュー 創造性教育と社会
知りたいと思うことからはじまる
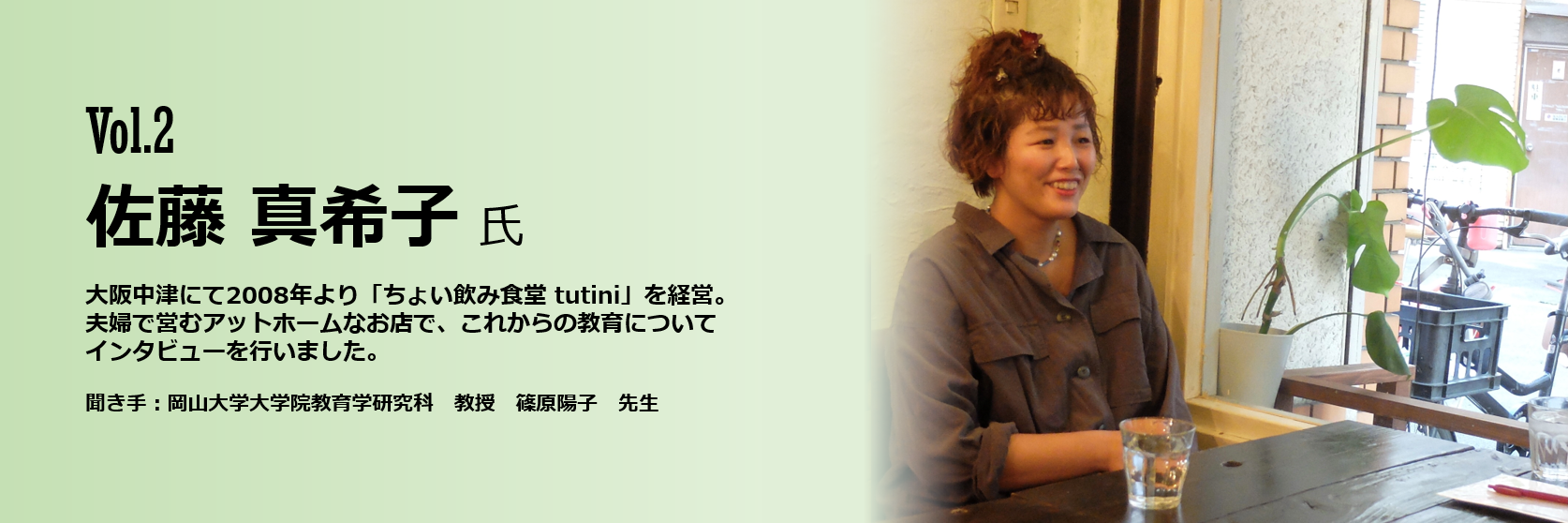
学校生活が楽しかった
篠原(以降篠):(2022年当時)これから小学校に入学するお子さんがいらっしゃいますが,教育の世界もだんだん変わってきていて,我々のころは「お勉強,お勉強」ってすごく言われてきましたが,最近はそうでもないです。そこで,いま気になっているトピックがあればお話しできればと思っています。
佐藤さん(以降佐):先生らがしんどいのではないのかなと。保育園でもそうなのですが,そもそも人数が足りていないとか。自分の時は,先生と生徒の距離が近いというか。やんちゃな子がいても担任の先生がいい意味で介入してくれて自分は学生生活が楽しかったけど,今はそういう意味での良さがなくなっているのかも。
篠:なるほど。
佐:今の子たちにも楽しいって思ってほしいし,そういう意味で育てていくにあたって,どうやって他人に優しくするとか,面白いことができるセンス,人間力のようなものは気になります。
配慮によって快適だけれど,考えなくてもよくなっている
佐:私は好き嫌いがあって給食が全然食べられなくて,コッペパンひとつ食べるのにも時間がかかって。でも,絶対残してはいけないという時代でした。意地になってきて,コッペパンを机の引き出しやカバンに隠してカビはやしては,「うわ,あいつパン入ったままやぞ」と言われる子でした。
篠:私は牛乳でした。牛乳が飲めなくて家に帰れませんでした。
佐:今はどうなっているのか分かりませんが,私の時は絶対残してはダメで,こっちも意地になっていました。
篠:今はアレルギーで体調を壊す子もいるので,それに応じて食べたらいいよって。セレクト給食ってご存知ですか?
佐:知らないです。
篠:クリスマスの頃になったら給食でケーキとかが出るんです。小麦アレルギーの子とかいるじゃないですか。だからアレルギーに合わせて3種類くらい提示して,その中から選べるよとか。
佐:そうなんですか。
篠:そんな時代なんです。
佐:そう考えたら,昔ってアレルギーがある子っていましたよね。(今の子たちは)繊細になりつつあるのかな。
篠:繊細になりつつ,今はそういうところに配慮が届くようになっていますね。先程のパンを隠すお話で,絶対残しちゃダメの頃ってどうやってそれをクリアしようかと考えておられましたよね。今の子どもたちは,考えなくても快適に過ごせるようになっていますよね。それが本当にいいことなのだろうか。昔,厳しい状態の時の方が知恵を張り巡らせようとしているのでは。子どもに配慮がされていてすごく快適でそれはいいのだけれど,全部用意されているから全然考えなくてもよくなってしまう。大人になって何もない状況でどうしようもなくなる。スマホがないとどうしようもなくなる。
佐:何かがあったときに,自分で考えるということが弱くなっているように思います。
違いを知るということ
佐:あとは発達障がいについての理解も,自分の時とは違うのかなと。
篠:保育園も幼稚園も小学校も,変わってきています。地域や家庭の人を学校が間に入って,積極的にみんなを繋ごうという流れになってきて,学校に閉じこもることなく,子どもたちもいろいろな大人を知っていく流れになっていると思います。インクルーシブと言って,今までは健常児でクラスを構成していたところに,支援が必要な子どもたち,発達障がいがある子たちも,みんなでクラスを形成して,できることを協力してやろうという動き。世界的にもそうなのですが,日本でもそういう動きになってきています。そうすると,いままで別々で育ってきた子どもたちが,そういうお友だちのことも知りながら育っていけます。
佐:そうですよね,知らないということが一番怖いから。そういう色々な子がいるから,みんなで協力しあってほしいと思います。みんな一緒なわけじゃないってことは知ってほしいし,感じてほしい。子どもと一緒にテレビを観ていても,話し合ったりもします。例えば,耳がきこえない子と遊んでいる時にトラブルになった場面を取り上げ,あなたならどうすると問いかけてくる番組があって。そういう番組などでは,自分の子どもにも聞くようにしています。
篠:大人って教えた方が早いと判断してしまいますよね。大学生に対してもそうですが,こちらが教えた方が早いというように。例えば,実験でも理解させようと思ったら,ものすごく時間がかかります。こちらがやった方が早いこともあります。それでも待ちます,学生が自分一人でできるように。こちらはもう忍耐です。
佐:そうか,なるほど。先回りするのはいけないのだろうなと思って,朝の支度でも,待たなきゃ行けないと思っているのに,ついついこちらがやってしまったりして。
篠:私の友だちの外国の方の子育てをみていると,日本人と違います。日本人だと,親がいろいろやってあげますよね。だけどそこは子ども自身に何でもやらせています。そして,叱るときには,なぜそれがダメなのか全部説明をしています。それは,ものすごく時間がかかります。
佐:なるほど,理由をちゃんと説明するって大事だと思います。
篠:そうですよね。理由がわかったら,次は対応できますよね。ゴミの分別でも,なぜ分別するのか意味がわかったら,次からずっと分別ができる。
佐:ちょっとしたことなのでしょうけれど。あと,色々な人に出会うこと。ここは飲食店なので,勝手に子どもにとってそうなっています。色々な人を見て,この人なら話を聞いてくれるって分かっているから,人を選んで話に行っている。お客さんの中でも,うちの子を一個人として接してくれる人や,一緒にお菓子買いに行ってくれる人がいたりして,いろいろな人と出会える。子どもなりに感覚で感じ取っていて,おもちゃ持ってそういう人のところにスッと行って遊んだりとかします。
篠:それでいうと先程おっしゃっていた人間力になるのかな。今されているように,色々な大人に会って,さらにそこでこの大人とこの大人の関係性とか,ネットワークが子どもなりにわかるのかもしれませんね。
佐:子どもの方が純粋にその大人のことが好きかどうかを判断する。子どもは嘘をつかないですものね。
生活と結びつけるということ
篠:お子さんは保育園で今日あったことをママに話したりしますか?
佐:そうですね。最近は会話も普通にできるようになったので,自分から言ってくれたりします。
篠:保育園に行ったらお子さんは何をしているんですか?
佐:大体,園庭で遊んでいたり。あとは,お部屋の中で三角形のブロックみたいなもので遊んでいます。はめるときに,カチって音がして快感というか。いろいろな色もあって,見本通りに作ってもいいし,自分独自でつくってもいいし。お迎え行ったらだいたいそれで作ったものを見せてくれます。あと,保育園の中でお野菜とか果物を育てているので,季節の果物なども覚えていて。秋なら柿が採れるから,ひと家庭に1つもらったりすると,今なら秋だよとか話したりします。それを保育園も考えているのかなと思ったりします。
篠:今の小学校でも,給食は季節のもの,果物を出していたりしますね。岡山だと,夏にピオーネがでたり,9月ならお月見だから月見団子がでたり。家ではなかなか口にしなかったり,行事ごとができなかったりしますが,学校では給食からそういうことを教えたりします。
佐:秋にあった月食なども,保育園で先生が子どもらに伝えてくださって,それを子どもから聞いてお父さんお母さんで一緒に見ました。そこから発展して,なんで冬は暗くなるのは早いの,なんで月はなくなるときがあるの,自転車に乗っていて月が追っかけてくるのは何でとか。親として,なかなかそういうことに答えられなくて。だから一緒に勉強しようかなと思ったりします。理科や歴史なども今なら生活に結びつけて楽しいのに,学生の頃は勉強を授業として捉えていたから興味が持てなくて。だから子どもには生活と結びつけたいな,身近なことと一緒に考えたいと思います。
篠:昔はテストで点を取るための,覚えるための勉強も多かったでしょうけど。まだ学校に上がっていないお子さんが,なんでなんでと自分から言うのは興味深いですよね。
佐:そうなんです,それにハッとさせられます。それをどうやって答えようか,今になって勉強し直すことがありますし,子どもが小学校に入ったら一緒に勉強しようと思います。
篠:お子さんのその自由で素直な発想がいいですよね。
佐:生活の中でいろいろなことを教えたいです,純粋すぎてなんでも聞いてくれるので。
篠:他に親子の繋がりを感じるときはありますか?
佐:普段,仕事をしているときは子どもと距離がありますが,寝るときに耳を触ってきたりして,そんなときにより強く存在を感じます。自分が親にしてもらったことを子どもにもしたいなと心がけていています。特に表現することは大事にしていて,「大好き」,「ありがとう」と言葉にして伝えたりします。そうすると,ニコって笑って嬉しそうにするんです。やっぱり,そういうことって大事だと思います。
篠:れって,お子さんも安心しますよね。
佐:色々な子育ての本を読むと大体,自己肯定感って言葉が出てきますが,それって愛されているっていうことなのかなと思います。だったら,愛していることを言う,伝えることが大事なのかなと思っています。
篠:配慮によって,快適だけど自分で考えなくてもよくなっていること。自分との違いを知り,協力していくこと。そして,生活体験の中から感じ取ったことだからこそ,知ろうとする。その探究する姿勢がまさに創造的なのだと思います。本日はありがとうございました。