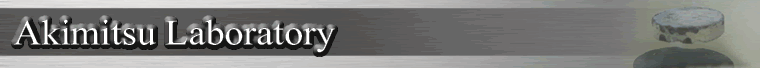 |
||||||||||
���_�������`����
�@ 1986�N��J. Bednorz��K. Müller�ɂ��wPossible High Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System�x�̕�(Fig.1)����n�܂������_�������`���̂́A���݂����������݂̂Ȃ炸�����̌����O���[�v�ɂ���Č�������Â��Ă��܂��B���݂ł�100 K���̒��`���̂���������������Ă��܂��B
�@�w���_�����x�Ƃ������O�̗R���ł����A����͂��̌n�������\�����ɕK�����Ǝ_�f����Ȃ�CuO2�ʂ������Ă��邱�Ƃ��炫�Ă��܂��BFig.2�ɍŏ��̓��_�������`����La2-xBaxCuO4�̌����\���������Ă���܂��B���̌����\����K2NiF4�^�ƌĂ����̂ŁA Ba1-xKxBiO3�Ɠ����y���u�X�J�C�g�^�\���Ɗ≖�^�\�������݂ɐςݏd�Ȃ����\�������Ă��܂��B�}���Ŗ��Ŏ������Ƃ��낪CuO2�ʂł��B���_�������`���̂ł́A����CuO2�ʂ����`���̕���ƂȂ�d�v�Ȗ�ڂ�S���Ă��܂��B
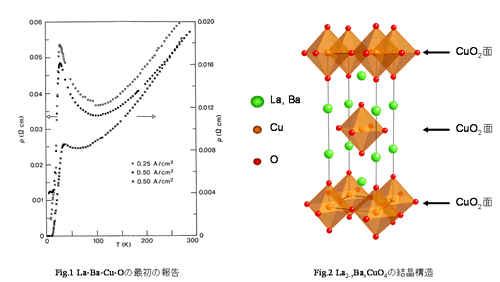
�E���`�������̃L�[�t�@�N�^�[ CuO2�ʂ̓d�q��ԂƃL�����A�h�[�v!!
�@����Tc�������_�������`���̂ł����A���̔����@�\�Ȃǂ͔�������20�N�߂����������݂ł��͂�����ƕ����Ă��܂���B���ʓ_�͂���������A�K���ꕨ��CuO2�ʂ������������≏�̂ł���A�L�����A�h�[�v�ɂ�蒴�`�������Ɏ���Ȃǂł��B�����ł́A���_�����ɂ�����ŏ��̒��`����La2-xSrxCuO4�̕ꕨ��La2CuO4���ɂƂ��āA���ݍł��L�͂Ȃ��̂��Љ�܂��B
CuO2�ʂ̓d�q��ԇ@�@�`Mott insulator�Ɣ��������������ց`
�@���_�������`���̂́A�����\�����ɕK�����Ǝ_�f����Ȃ�2��������: CuO2��(CuO2 plane)�������Ă��邱�Ƃ���A����CuO2�ʂ����`�������ɑ傫���֗^���Ă���ƍl�����Ă��܂����B�ꕨ���̑g�����݂Ă݂�ƁA(La3+)2(Cu2+)(O2-)4�Ɗe�C�I�����Ƃɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B�����\���S�̂��݂�ƁACuO2�ʂ�La3+��O2-����Ȃ�(LaO)2�w�����݂ɐϑw�����\�����Ƃ��Ă��܂��BCuO2�ʂ͑S�̂�-2���A(LaO)2�w�͑S�̂�+2���ŃC�I���I�ƂȂ�A�n�S�̂𒆐��ɕۂ��Ă��܂��B
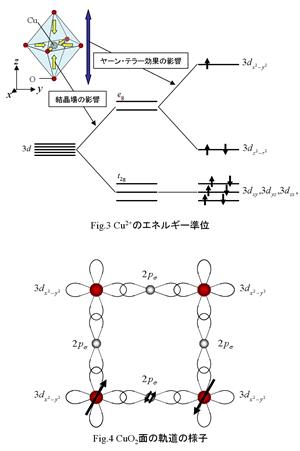
�@CuO2�ʂ��݂Ă݂�ƁACu2+��(3d)9�AO2-��(2p)6�̓d�q��Ԃ��Ƃ��Ă��邽�߁ACu��3dx2-y2�̋O���͓d�q��1����Ȃ���ԂƂȂ��Ă��܂��B�����Łw3dx2-y2�̋O���͓d�q�x�Ə����܂������A�����La2CuO4�ɂ�����Cu2+�̃G�l���M�[���ʂ��݂Ă݂��Fig.3�̂悤�ɂȂ��Ă��邽�߂ł��BCu2+��3d�O����5�d�ɏk�ނ�����ԂŁA5�̋O���͂��ꂼ��O��������3dxy(x-y����), 3dyz(y-z����), 3dzx(z-x����), 3dx2-y2(x����y������), 3dz2-r2(z������)�ƌĂ�Ă��܂��B���i�Ȃ瓯���G�l���M�[���ʂɂ���͂���5�̋O���Ȃ̂ł����A�܂��ACu���͂��8�ʑ̔z�ʂ��Ă���_�f�̉e�����A�_�f�����̋O��������3dx2-y2, 3dz2-r2���G�l���M�[�I�ɍ����Ȃ�܂��B���̂��߁A5�d�ɏk�ނ��Ă���3d�O����t2g(3dx2-y2, 3dz2-r2)��eg(3dxy, 3dyz, 3dzx)��2�̏��ʂɕ��܂��B���̂悤�Ȍ����\�����̌��q�z�ʂɂ��e�����A������Ƃ��܂��B����ɁALa2CuO4�̏ꍇ�ACuO6���ʑ̂�z�������ɐL�тĂ��邽��(�G�l���M�[�I�ɂ��̂悤�ȍ\���ɂȂ����ق�������Ȃ���)�A 3dx2-y2�̕���3dz2-r2�����傫�ȉe�����܂��B���̂��߁A 3dx2-y2�̃G�l���M�[���ʂ��ł������Ȃ�܂�(���̂悤�ȃG�l���M�[���ʂ���e�������[���E�e���[���ʂƌĂт܂�)�B���̌��ʁA Cu2+�̏ꍇ3dx2-y2�O���ɓd�q��1������������ԂƂȂ�܂��BCuO2�ʂ̋O���̗l�q��`���Ă݂�ƁAFig.4�̂悤�ɁACu��3dx2-y2�O����O��2p�O������Ȃ鍬���O�����`�����Ă��܂��B
�@
CuO2�ʂ̓d�q��Ԃ́A Cu2+��(3d)9��3dx2-y2�̃o���h�������������܂������(Fig.5(a))�ł�����A�����I�Ȑ�����������͂��ł��A���ۂɂ͓`�������Ȃ��A�ꕨ���͐≏�̂Ƃ��ĐU�����܂��B����́A�d�q�Ԃɋ������ւ������Ă��邽�߂ł�(���̂悤�Ȍn�̂��Ƃ������֓d�q�n�ƌĂт܂�)�B
�@�`�����N���邽�߂ɂ́A 3dx2-y2�̓d�q��Cu�T�C�g�Ԃ��шڂ�Ȃ�������܂���B�������A 3d�O����L���铺�_�����̂悤�Ȍn�ł́A2�d�q������T�C�g�ɂ���Ɠd�q�Ԃɋ����N�[�������ݍ�p: U�������܂��B�܂�A1��Cu�T�C�g��2�d�q����L����ƃG�l���M�[U�̕������]�v�ɃG�l���M�[���K�v�ƂȂ�܂��B���̂��߁A�`�����N���邽�߂̓d�q�̔�шڂ�͗}������A�d�q�͊eCu�T�C�g�ɋǍ݂����ԂƂȂ�܂��B���̂Ƃ���CuO2�ʂ̃o���h�̗l�q��Fig.5(b)�̂悤�ɂȂ�܂��B�傫�ȓd�q���ւ̌��ʂɂ����Cu��3d�o���h���d�q�Ŗ������ꂽ�����n�o�[�h�o���h�Ƌ�̏㕔�n�o�[�h�o���h��2�ɕ��A���̊ԂɃM���b�v(Mott-Hubbard gap)���`������Ă��܂��̂ł��B����āA�{���d�C�`��������͂��̓��_�������`���̂̕ꕨ���͐≏�̂̏�ԂɂȂ��Ă���ƍl�����Ă��܂�(�����d�q���ւɂ���ċO�����������ʐ≏�̂ƂȂ������̂����b�g�≏��(Mott insulator)�ƌĂ�ł��܂�)�B���̌��ʁACu�T�C�g�ɂ�1�̐��E(Hole)�ƃX�s��1/2���������Ǎݓd�q�����݂��ACu�C�I���������C�I���ɂ��Ă��܂��B�ꕨ���Ŕ��������̒�����������̂����̂��߂ł��B
�@�ꕨ���ł́ACu�T�C�g���s=1/2�̃X�s�������������I�ɐ��Č����܂����A����́ACu�T�C�g�ɃX�s�������邱�Ƃ��������Ȃ̂ł����AO�T�C�g��2�̓d�q�̉e����������ċN���Ă��邱�Ƃł��BFig.4��Cu��O��̖��́A���ꂼ��̃T�C�g�̓d�q�ɂ��X�s����\���Ă��܂��BO�T�C�g�́A�S�ēd�q���l�܂��Ă���̂Ō�������2�̃X�s�������܂��B���_�����ɂ����锽�����������̑��ւ́A�ד��m��Cu�T�C�g�̃X�s��������O�T�C�g�̃X�s������đ��ݍ�p���������Ă��܂��B���̂悤�ȑ��ݍ�p�������ݍ�p�Ƃ����܂��B
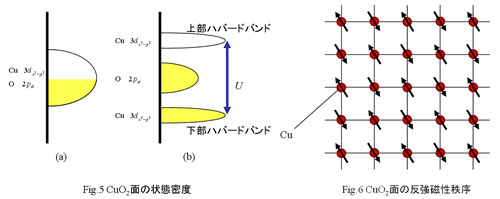
CuO2�ʂ̓d�q��ԇA�@�`�L�����A�h�[�v�ƒ��`���̔����`
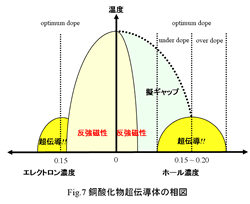
�@���_�������`���̂̑傫�ȓ������A�L�����A�Z�x�Ɉˑ����Čn�̐������������������`���������ƕω����邱�Ƃł��B�����ŁA�L�����A��CuO2�ʓ��ɓ��������z�[����G���N�g�����̂��Ƃ������܂�(Ln-214�n�̂�����u����: x�̂��Ƃł�)�BFig.7�͓��_�������`���̂̃L�����A�Z�x�ɑ��鑊�}�ł��B�����̉E�̕������L�����A���z�[��(La2-xSrxCuO4, YBa2Cu3O6+��, Bi2Sr2CaCu2O8+�� etc�c)�̂Ƃ��A���̕������G���N�g����(Nd2-xCexCuO4 etc�c)�̂Ƃ��ł��B�z�[���Z�x���������̈�ł́A�ꕨ���̐������������������������≏�̂ł����A�z�[���Z�x����������ɂ��������Ē��`�����������܂��B���`�����́A�͂��߃L�����A�h�[�v�������ɂ���������Tc����������̈�(underdoping region)������A����h�[�v�ʂōō�Tc����������(optimal dope) �ƁA���x�͋t��Tc����������̈�(overdoping region)�ɂȂ�܂��B�œK�h�[�v�ʂ�0.15�`0.20���x�ł��B�h�[�v�ʂ�����ɑ�������ƁA���x�͒��`���͎����Ȃ��Ȃ�A�����I�Ȑ����������̈�ƂȂ�܂�(�G���N���g���h�[�v�̏ꍇ�́A�z�[���h�[�v�̏ꍇ�����ɂ₩�ɔ����������������A�����������Ȃ��Ȃ�Ɠ����ɒ��`����������܂�)�B�܂��A���_�������`���̂ł́A���`����Ԃł͂Ȃ��̈�ŋ[�M���b�v�Ƃ��钴�`���M���b�v�\���̂悤�Ȃ��̂�Tc�ȏ�ł�������̈悪����܂��B
�@���ɁA���`������������ۂ̃o���h��Ԃ����Ă݂܂��B�����Ŏg�����f���́A���_�����̓d�q��Ԃ�\������Ƃ��ɂ悭�x������Ă��郂�f���ł�(���̂Ƃ���L�͂Ƃ��������ŁA���_�������`���̂ɂ����Č���I�Ȃ��̂͒���Ă��܂���)�B
�@���`�����o������Ƃ������Ƃ́A�{�����b�g�≏�̂ł���ꕨ���̃o���h��Ԃ������I�ȃo���h��Ԃɕω������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��ɏq�ׂ��悤�ɁA�ꕨ���ɂ�����CuO2�ʂɃo���h��Fig.8(a)�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�܂��A�z�[���h�[�v�ɂ�钴�`����La2-xBaxCuO4���l���Ă݂܂��B La2-xBaxCuO4 �ł́ALa3+��Ba2+�Œu�����邱�Ƃɂ��(LaO)2�w�̓d�ׂ�+2�����猸���Ă��܂��܂��̂ŁA�n�S�̂̓d�ׂ𒆐��ɕۂׂɂ́A-2���ɕۂ��Ă���CuO2�ʂ̓d�ׂ�-2����-1���̕����ɕω����Ȃ���Ȃ�܂���B�܂�ACuO2�ʓ�����d�q����苎��(CuO2�ʓ��Ƀz�[��������)�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̌��ʁA�{���≏�̓I�o���h���(Fig.8(a))�ł�����CuO2�ʂ̃o���h�\�����A�d�q��������(�z�[�������������)���Ƃ�Fig.8(b)�̂悤�ȋ����I�ȃo���h��Ԃɕω�����ƍl�����Ă��܂��B
�@����A�G���N�g�����h�[�v�ɂ�钴�`����Nd2-xCexCuO4�ł́ANd3+��Ce4+�ɒu������邱�Ƃɂ��(NdO)2�w�̓d�ׂ�+2�����瑝�����܂��B���̂��߁ACuO2�ʂ̓d�ׂ�-2������-3���̕����ɕω��A�܂�CuO2�ʓ��ɂ���ɓd�q�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̌��ʁA�o���h�\����Cu3d�̏㕔�n�o�[�h�o���h�ɓd�q��������Fig.8(c)�̂悤�ɂȂ�ƍl�����Ă��܂��B
�@���_�������`���̂ōl�����Ă��邱�̂悤�ȃo���h���f���́A�����̂̐����ɂ悭�����邱�Ƃ���A�����̂ɖ͂��ăz�[���h�[�v�ɂ�钴�`���̂�p�^���`���́A�G���N�g�����h�[�v�ɂ�钴�`���̂�n�^���`���̂ƌĂт܂��B
�@���̂悤�ɁAp�^n�^�̗����`���̂Ƃ������ł��邱�Ƃ���A���̃��f�����L�͂ł���ƍl�����܂����A�G���N�g�����h�[�v�ɔ�ׂĒP�������e�Ղɓ�����z�[���h�[�v�^�ł́AFig.8(b)�Ƃ͏����قȂ�Fig.8(d)���L�͂ł���Ƃ������Ă��܂��B���̃��f���́A�z�[���h�[�v��O2p�o���h�̏�����ɐV�������(�����̂ł����Ƃ���̕s��������)���`������A����ɂ������������Ƃ������̂ł��B���̂ق��ɂ��An�^��p�^���{����(Tc�ɍ�������̂�)�������f���Ő����ł��邩�Ȃǂ��낢��c�_�̗]�n���c����Ă���̂�����ł��B���̋@�\�𖾂̂��߂ɂ��A������V�����������ʂ�V�����̔��������҂���Ă��܂��B
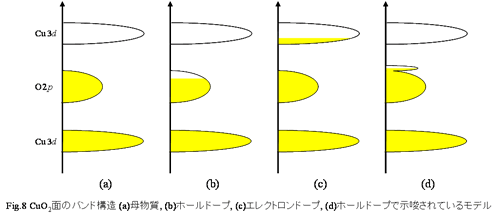
�E���`���T���̎w�j!? - ���_�������`���̂̓��� -
�@���X�̓��_�������`���̂��������ꂽ���݂ł́A���`���@�\�̉𖾂ɂ������������Ă��܂������A���̈���ŐV�������`���T���̎w�j�ƂȂ�ׂ��������킩���Ă��܂����B
�@���̈��Fig.9�Ŏ������w�v���b�N�w�̊T�O�x�ł��B���_�������`���̂̌����\����Fig.9�Ɏ������悤�ɁACuO2�ʂ𑼂̌��q�w�����ݍ���CuO2�ʂ��Ǘ�������Ԃɂ���܂��BFig.10��La2-xSrxCuO4�ł́A[(La,Sr)2O2]�w��CuO2�ʂ��Ǘ��������ڂ��ʂ����Ă��܂��B���̂悤�Ȍ��q�w�̂��Ƃ��w�u���b�N�w�x�ƌĂ�ł��܂��B���Ȃ킿�A���_������CuO2�ʂƃu���b�N�w�����݂ɐςݏd�Ȃ����\��������Ă���̂ł��B
�@
��ɏq�ׂ��悤�ɁACuO2�ʂ����`����S���Ă���̂ɑ��A�u���b�N�w�͒��`�������̌��ƂȂ�L�����A�����������ڂ��ʂ����Ă��܂��B���_������1�̓����Ƃ��ẮACuO2�ʂ̒���(�o���h�\�� etc)�𗐂����ƂȂ��A�u���b�N�w�̓d�׃o�����X�̒����ɂ���Ē��`�����������邽�߂̃L�����A�𒍓��ł��邱�Ƃł��B���̂Ƃ��ALa2-xSrxCuO4�ɂ�����CuO2�ʂ� [CuO2]-2�A�u���b�N�w��[(LaO)2]+2�ƕ\���ƁASr���h�[�v���邱�Ƃɂ��u���b�N�w��[(La,Sr)2O2]+2-p�ACuO2�ʂ�[CuO2]-2+p�ƕ\�����Ƃ��ł��܂��B����p���L�����A�Z�x�ƂȂ�܂�(p > 0�Ńz�[���h�[�v, p < 0�ŃG���N�g�����h�[�v�ɑΉ����܂�)�B�܂��A�u���b�N�w�͒P�ʊi�q�ōl�����Ƃ��A�ꕨ���ɂ����ău���b�N�w�̓d�ׂ͕K������+2���ɂȂ��Ă��܂�(Y-123�ł�Y3+, [CuO chain]1+�ł����P�ʊi�q�S�̂ōl�����Ƃ��A�u���b�N�w�͕���+2�ƂȂ�܂�)�B
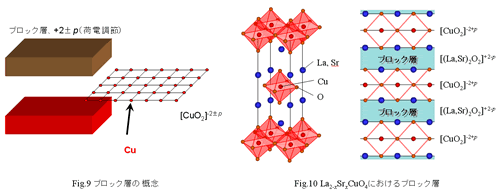
�@���̂悤�ɍl����ƁA���_�������`���̂�CuO2�ʂƃu���b�N�w���p�Y���̂悤�ɑg�݊����邱�ƂőS�ĕ\�����邱�Ƃ��ł��܂��B���������āA�V�������_�������`���̂��J������Ƃ��́A��Ƀu���b�N�w�̑g�����H�v���邱�Ƃōs�����Ƃ��ł���̂ł��B
�@�������������ꂽ���_�������`���̂���A�������̂������낢�o����������Ă��܂��B��́ACuO2�ʂ̖�����Tc�̊W�ł��B�P�ʊi�q����1����CuO2�ʂ�����La2-xSrxCuO4�ł�Tc = 40 K�A2������YBa2Cu3O6+d�ł�Tc = 90 K�A3������HgBa2Ca2Cu3O8+���ł�Tc = 134 K�ƁA�m����CuO2�ʂ̖����������ق���Tc�������Ȃ�X��������܂��B�ł́A������CuO2�ʂ��ςݏd�Ȃ��Ă��镨���ł͂ǂ����Ƃ����ƁA���`�����玦���܂���B��͂�A�u���b�N�w�ȂǂŊu�Ă�ꂽ�Ǘ�����CuO2�ʂ��K�v�ł��邱�Ƃ����������ł��BFig.11�͒P�ʊi�q����CuO2�ʂ̖����ɑ���Tc�̒l���\�I�Ȋe�������ƂɎ����Ă��܂��B���������ƁACuO2�ʂ̖�����3���̂Ƃ��ɍł�Tc�������Ȃ�X��������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B�Ǘ�����CuO2�ʂ����肷���Ă͋t�ɍ���Tc��������̂ɂ͕s���̂悤�ł��B�܂��ACuO2�ʂ̌`��Tc�ɊW���Ă���Ƃ������Ă��܂��BFig.12�́A�e�퓺�_�������`���̂�CuO2�ʂ̌`���\���Ă��܂��B���_�������`���̂̒��ł�����Tc������Hg,�@Tl�n��CuO2�ʂ�����Ȃ̂ɔ�ׁALa-214��CuO2�ʂ͓ʉ����Ă��܂��B������݂�ƁACuO2�ʂ�����ɋ߂��ق�������Tc�����҂ł���X��������悤�ł��B
�@���_�������`���̂́ALa2-xBaxCuO4�̔����ȍ~��200��߂�����Ă��܂��B�������A���̑��ɂ����낢��Ȍo���������݂��Ă��錻�݂ł́A�����ŏЉ�����̂��l�����邱�Ƃł܂��܂�����Tc�����V���`���̂������邩������܂���B
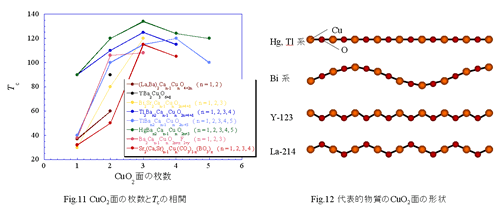
�E ���_�������`���̂̃��j�[�N�Ȍ����\��!!
�@���_�������`���̂́A���`���������ǂ̑g����CuO2�ʂ������Ă���Ƃ������ʓ_������܂����A�P�ʊi�q(unit cell)�Ɋ܂܂��CuO2�ʂ̖����ɂ���ă��j�[�N�ȍ\�������܂��B�����ł́A���\�킠�錋���\���̎�Ȃ��̂��Љ�܂��B
Ln-214(CuO21���w��L����)�n
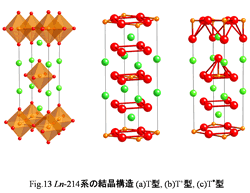
�@ Fig.13��3��ނ̓��_�����̌����\���������Ă���܂��B�����̕����̓����́A�P�ʊi�q����1����CuO2�ʂ������Ă���Ƃ������Ƃł��B�ʗႱ���́A(a)T, (b)T�f, (c)T*�^�\���ƌĂ�Ă��܂��B�܂��A(a)��T�^�ł����A�ŏ��̓��_�������`����La2-xBaxCuO4�Ȃǂ�����ɑ������܂��BT�^�ł�Cu�Ǝ���̎_�f��8�ʑ�(CuO6 8�ʑ�)�����ACuO2�ʂ͂���8�ʑ̂����ɘA�Ȃ����`�����Ă��܂��B���ɁA(b)��T�f�^�ł����A�G���N�g�����h�[�v�ɂ�蒴�`��������Nd2-xCexCuO4�����̍\�����Ƃ�܂��BT�^�Ƃ̈Ⴂ�́AT�^�ł�8�ʑ̂�����CuO6�̒��_�����̎_�f(���_�_�f)���Ȃ����Ƃł��B���̂���T�f��CuO2�ʂ́A�����`�ɂȂ��Ă��܂��B�Ō��(c)��T*�^�ł����A�����T�^��T�f�^�����킹���悤�ȍ\��������Ă��܂��B���̂��߁ACuO2�ʂ̕Б��ɂ������_�_�f���z�ʂ��A�s���~�b�h�^��CuO2�ʂ��`�����Ă��܂��B(Nd,Ce)2-xSrxCuO4�����̍\���Œ��`���������܂��B
�@ ���̌n�̒��`���̂ɂ�����傫�ȓ����́A�L�����A�R���g���[�������f���ꕔ�u�����邱�Ƃōs���Ă���Ƃ����_�ł��B�����ŏЉ�������ł́ALn3+��Ba2+��������Ce3+�Ȃǂňꕔ�u�����邱�ƂŒ��`�������܂��B
Y-Ba-Cu-O�n
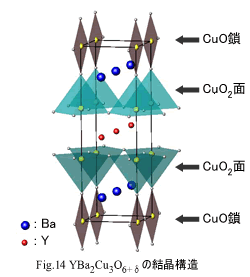
�@ ���߂ĉt�̒��f���x���z����90 K����Tc���L�^�����̂�Fig.14�Ɏ�����YBa2Cu3O6+��(Y-123)�ł��BY-123�̔����́ALa2-xBaxCuO4�ɂ�����Ba�ł͂Ȃ�Sr�ɂ��L�����A�h�[�v���s������������Tc���o���������Ƃ�A���͂���������Ƃ���Tc���㏸�������Ƃ����[�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�C�I�����a���������ق�������Tc��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������z�ł��B���̌��ʁALa2-xSrxCuO4��2�{�ȏ��Tc����������Ɏ���܂����B
���̌n�ł͒P�ʊi�q����2����CuO2�ʂ������Ă��܂��B La2-xBaxCuO4��8�ʑ̌^��CuO2�ʂ������Ă����̂ɑ��AY-Ba-Cu-O�n�ł�8�ʑ̂��㉺�ɕʂ�A���̊Ԃ�Y�����邱�Ƃɂ���ď㉺��CuO2�ʂ����_�_�f����Ē��ڂɘA������̂�h���ł��܂��B���̂���2����CuO2�ʂ̓s���~�b�h�^������Ă��܂��B�܂��A���̌n�̌����\���ɂ�����傫�ȓ������s���~�b�h�̒��_���Ȃ��ł���CuO��(�`�F�[��)�̑��݂ł��B���̃`�F�[���T�C�g�͂��傤��CuO2�ʂ̖ʕ����̎_�f���������邱�ƂŌ`�����ꂽ�`�����Ă��܂�(���̕�����CuO2�ʂ��ƁA3�̃y���u�X�J�C�g�����_�_�f����ĘA�����Ă��܂�)�B���̓_�ŁAY-Ba-Cu-O�n�́A���_�����̒��ōł����j�[�N�Ȍ����\���Ƃ����܂��B
�@CuO�`�F�[���́AY-Ba-Cu-O�n�̒��`�������ɂ��傫�ȉe����^���Ă��܂��BLn-214�n��Ln�T�C�g�𑼌��f�u�����邱�ƂŒ��`�������������̂ɑ��A���̌n�ł́A�`�F�[���T�C�g�Ɏ_�f�C�I�������邱�ƂŒ��`�����������܂�(Y-123�n�̕ꕨ���́A�`�F�[���T�C�g�̎_�f���S����������Ԃ�YBa2Cu3O6�ƂȂ�܂�)�BY-Ba-Cu-O�n�̒��`���Ƃ��ẮAY-123�̂ق��Ƀ`�F�[���T�C�g��2�d�ɂȂ��Ă���YBa2Cu4O8(Y-124)��AY-123��Y-124�\����1�������ƂɌJ��Ԃ���Y2Ba4Cu7O14(Y-247)�Ȃǂ�����܂��B�܂��A������Y�T�C�g��Ln�Œu���������n�ł����l�ɒ��`�����m�F����Ă�����̂����݂��܂��B
Bi, Tl, Pb, Hg�n

�@�����̌n�ł�Tc = 100 K���̒��`���̂��������݂��Ă��܂��B�傫�ȓ����́ACuO2�ʊԂ�Ca�C�I�������邱�Ƃɂ���ĒP�ʊi�q����CuO2�ʂ̐��������āA����ƂƂ���Tc�������Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B�܂����̌n�ł��A�_�f�����`�������ɕK�v�ȃL�����A���������Ă��܂��B
�@Fig.15��Bi�n���`���̂̈��������Ă��܂��B���Ԃ�(a)Bi2Sr2CuO6(Bi-2201), (b)Bi2Sr2CaCu2O8(Bi-2212), (c)Bi2Sr2Ca2Cu3O10(Bi-2223)�ƂȂ��Ă��܂��BFig.15���݂�ƁACa��1������ƁACuO2�ʂ̖�����1�����Ă���̂��킩��܂��B
�@�����Ɏ�����Bi�n���`���̂̍ŏ��́̕ABi-2201�ł����B���30 K���̒��`���̂ł��邱�Ƃ�����܂������A����������Tc��10 K���x�ł��������߁A���܂蒍�ڂ���Ȃ��܂܂ł����B������Bi-2201�̔������琔������A�����Ca��������Bi2Sr2CaCu2O8(Bi-2212)��Bi2Sr2Ca2Cu3O10(Bi-2223)�����ꂼ��A95 K, 110 K�̒��`���̂ł��邱�Ƃ���������܂���(Bi-2201�������������ł́A��R����Ȃǂ�Bi-2212��Bi-2223�̒����������Ă��������ɑ�ό�����܂����Ƃ�����b������܂�)�BBi-2223�͓��_�������`���̂ɂ����āA�͂��߂�100K����Tc���L�^�������`���̂ł��B
�@�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́ACa��Sr�������\�����ɕʁX�̃T�C�g�������Ă���Ƃ������Ƃł��B�����A�V���`���̂̒T�����s���Ƃ��A���w�I�Ȑ��������Ă��錳�f��u�����Ă��傫�ȕω��͂Ȃ����낤�Ƃ����̂����ʂ̍l�����ł����BSr��Ca�͋��ɃA���J���y�ދ����ɑ����Ă��錳�f�ł��B�������A�C�I�����a��Ca��1.02Å, Sr��1.18Å�ƈႢ������܂��B���̈Ⴂ���������w�I�����������Ă���ɂ�������炸�A�����Ɍ����\�����ɑ��݂ł��錋�ʂƂȂ����̂ł��B����Bi�n�̔����ȍ~�A���l�Ȋϓ_����̒T���ɂ��ATl�n�Ȃǂł�����Tc��L���钴�`���̂���������܂����B
�@���݁A�ō���Tc�̋L�^�������Ă���Hg�n���`���̂������\�������X�قȂ���̂́ACa�C�I�������邱�Ƃɂ��CuO2�ʂ���������Ƃ��������悤�ȓ����������Ă��܂��BFig.16�́AHg�n���`���̂̌����\���������Ă���A����(a)HgBa2CuO4+��(Hg-1201), (b)HgBa2CaCu2O6+��(Hg-1212), (c)HgBa2Ca2Cu3O8+��(Hg-1223)�ƂȂ��Ă��܂��BTc�͂��ꂼ��A90 K, 120 K, 134 K�ł��B����Hg�n�̒��ŁAHg-1223�̍������ɂ�����Tc = 164 K�����݂̍ō�Tc�ł��BBi�n�̂Ƃ��Ɠ��l�ɁAFig.16�Ŏ����������\������镨����Tl�n, Pb�n�ɂ����݂��A���ɍ���Tc���������`���̂Ƃ��ĕ���Ă��܂��B
[1] J. G. Bednorz and K. A. Müller, Z. Phys. B64 (1986) 189
[2] BKBO
[3] S. Uchida, H. Takagi K. Kitazawa and S. Tanaka, Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987) L1
[4] M. K. Wu, J. R. Ashburn, C. J. Thorng, P. H. Hor, R. L. Meng, L. Gao, Z. J. Huang, Y. Q. Wang and C. W. Chu, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 908
[5] H. Maeda, Y. Tanaka, M. Fukutomi and T. Asano, Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) L209
[6] Y. Tokura, H. Takagi and S. Uchida, Nature 337 (1989) 345
[7] �\�q�D�I, �p���e�B 5 (1990) 34
[8] A. Schilling, M. Cantoni, J. D. Guo and H. R. Ott, Nature 363 (1993) 56
[9] J. Akimitsu, S. Suzuki, M. Watanabe and H. Sawa, Jpn. J. Appl. Physics. 27 (1988) L185
[10] A. F. Marshall, R. W. Barton, K. Char, A. Kapitulnik, B. Oh, and R. H. Hammond, Phys. Rev. B 37 (1988) 9353
[11] D. B. Currie, M. T. Weller, P. C. Lanchester and R. Walia, Physica C 224 (1994) 43
[12] D. E. Morris, N. G. Asmar, J. Y. T. Wei, J. H. Nickel, R. L. Sid, J. S. Scott and J. E. Post, Phys. Rev. B 40 (1989) 11406
[13] J. Akimitsu, A, Yamazaki, H. Sawa and H. Fujiki, Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987) L890
[14] S. N. Putilin, E. V. Antipov, O. Chamaissem and M. Marezio, Nature. 362 (1993) 226