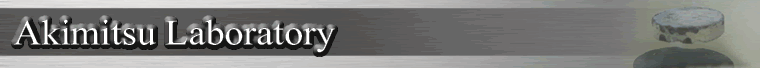 |
||||||||||
�����ԉ��������`����
�@�����ԉ������̒��`���́A�P�̌��f���`���̂ƂƂ��ɁA�Â����璍�ڂ���ĒT������Ă��������ł��B Fig.1�́A�����ԉ��������`���̂�Tc�̐��ڂ������Ă��܂��B�����ԉ��������`���̂́A���_�������`���̂قǍ���Tc�������̂͂܂���������Ă��܂��A���X�����ł��邾���ɉ��H���₷���Ƃ������_�������Ă���A�L�����p�Ɍ������������i��ł��܂�(���_�������`���̂͌��X�䒃�q�̂悤�ȃZ���~�b�N�X�̂��ߓW���E�����ɖR�����B���̂��߉��H����ϓ��)�B
�@���`���̗��_�ł���BCS���_���A�����ԉ��������`���̂̔������Ȃ���ΐi�܂Ȃ������ł��傤�B�܂��A�ߔN�A��r�I����Tc = 39 K�Œ��`������������MgB2���������ꂽ���Ƃ���A���܂ł�������ɐ��͓I�Ɍ������i�߂��Ă��܂��B
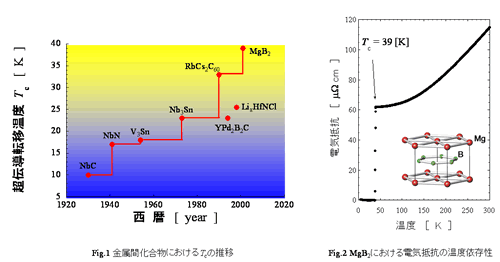
�EBCS���_�ƒT���̎w�j!?
BCS��Tc�����������McMillan������������Tc�������������!!

�@1957�N�ɔ��\���ꂽBSC���_�ɂ��A���`���̊�{�I�ȋ@�\���𖾂���A�ǂ̂悤�Ȋϓ_���璴�`���T�����s���������Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂����BBCS���_�ł͇@���̂悤��Tc�����������������Ă��܂��B���̎��ł́A�����̒��`���̂̑�����\�����邱�Ƃ��ł��܂����B�������AMatthias��ɂ�蔭�����ꂽA15�^���`���̂����̎��ŕ\�����邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B���̂����@���͓d�q�ԑ��ݍ�p:V ��V<<1�Ƌߎ����ē��o���ꂽ���̂ł��B���̂��߁A�����o���Ȃ����x��V���傫�������ł́A���܂��\���ł��Ȃ������̂ł��B�����œo�ꂵ���̂��B����McMillan�������ł��B���̎��́A�@���ɂ����閳���o���Ȃ�V��N(0)�̏������̒��Ɏ�荞��ŕ\�����Ă��܂��B����ɂ��A����ɍ���Tc�������̂܂ŕ\���ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@�@��, �B���Ƃ��ɁATc��������������Ƃ��āA�܂��i�q�U����(�f�o�C�U����): ��D��傫����������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B�܂��A�t�F���~�ʋߖT�̏�Ԗ��x: N(0)�A������V��傫����������Ƃ������Ƃ��킩��܂�(McMillan�������ł́A�ɂ̒��ɂ��̏�܂܂�Ă���)�BV�̒l�͎��ۂɑ��肷����@���Ȃ����߁A�L���Ȓ��`���T���̎w�j�Ƃ͂Ȃ�܂���B�܂��A����2�̃p�����[�^�����ۂɑ��肷��ƂȂ�Ɠ���ł��B�������A���݂܂Ŕ������ꂽ���`���̂̌X��������ƁA�m���Ƀf�o�C�U�������傫�����ʂ̌y�����f(�A�����)�ł�Tc�������AA15�^�̒��`���̂̒��ł��A�t�F���~�ʋߖT�̏�Ԗ��x���������f�̑g�ݍ��킹�̂ق���Tc�������Ȃ�܂��B�������A�����ŋ��������̂ł͂��܂����Ă͂܂��������ŁA���S�ɂ��ׂĂ̒��`���̂ɂ��Ă͂܂�킯�ł͂���܂���B�Ⴆ�A����Tc���ق��铺�_�������`���̂ɂ͂����ŋ��������̂��قƂ�NJY�����܂���B�������Ȃ���A�����ԉ������ɂ����Ă��ꂾ�����Ă͂܂邱�Ƃ��l����ƁA��T�ɕ��j�Ƃ��Ė��Ӗ��Ǝ̂ĂĂ��܂��̂͂��܂�ɂ��i���Z���X�Ƃ�����ł��傤�BBSC���_��蓱�����Tc�ɗL���ȏ������A���h�Ȓ��`���T���̎w�j�ɂȂ肦��̂ł��B
���ʂ̌y�����f( �y���f )��Tc�ɗL���ɓ���!?
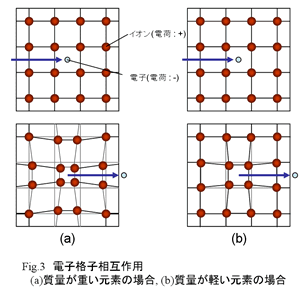
�@BCS���_�ɂ����āA�f�o�C�U�������傫�����ʂ̌y�����f��Tc�ɗL���ł���Ǝ�����܂����B���ʂ̌y�����f�͌y���f�ƌĂ�A���ɋK��͂���܂��A�����\��Ő��f(H)����J���V�E��(Ca)������ɑ�������Ƃ���Ă��܂��B
�@�i�q�U����S�����f�́A�������ŃC�I�������Ă��܂��B�N�[�p�[�y�A�̌`���������N�����d�q-�i�q���ݍ�p�́A���̊i�q���`�����Ă���C�I���Ɠ`���d�q�̑��ݍ�p�ł��B�C�I�����d�����f�̏ꍇ(Fig.3(a))�A�i�q���ɓ`���d�q������Ă���ƁA���������t�����܂��B�܂��A���ʂ��傫�����߁A���x�͊i�q�����Ƃ̌`�ɖ߂�̂ɂ����Ԃ�������܂��B�������A�C�I�����y�����f�̏ꍇ(Fig.3(b))�A�i�q���K�x�ɂЂ��݁A�܂����ʂ����������Ƃ���A�i�q�����Ƃ̌`�ɖ߂�̂ɂ���������Ԃ�������܂���B���̂��߁A�d�����f�̏ꍇ�����Z���Ԋu�ő����N�[�p�[�y�A���`�����邱�Ƃ��ł��܂��B�y���f���L���Ƃ����̂́A���̂悤�Ȃ��ƂɋN�����Ă��܂��B
�@���̂悤�ɒ��`���Ɉꌩ�L���Ɏv����y���f�ł����A�����̌n�Ō��Ă݂܂��ƁA�x�����E��(Be)�Ȃǂ̓f�o�C�U�������傫���ɂ�������炸�ATc = 0.03 K���x�ł��B�܂��A�f�o�C�U��������������(Pb)��Tc = 7.19 K�ƂȂ��Ă���A��T�ɗL���Ƃ͌�������������������܂��B�������Ȃ���A�����ԉ������ōō���Tc���ق���MgB2�́AB���f�ɋN�������傫���i�q�U�������`�������Ɛ[�����т��Ă��邱�Ƃ���������Ă��܂��B���̂��Ƃ���l���Ă���͂�A�y�����f���܂ޕ����ɂ́A�܂��܂�����Tc�������`���̂��c����Ă���\��������܂��B
�t�F���~�ʋߖT�̍�����Ԗ��x��Tc�ɗL��!?
�@�����̒��`���̂����邱�Ƃɐ��������}�`�A�X(B. T. Matthias)�́A�����ԉ������̕��ωדd����Tc�Ƃ̊Ԃɂ�Fig.4�̂悤�ȑ��ւ����邱�Ƃ���܂����B����́AMatthias�̉דd����(Matthias rule)�ƌĂ�Ă��܂��B��ɁA�����̑J�ڋ������`���̂ɂ悭���Ă͂܂�o�����ł��邱�Ƃ�������܂������A����́A��قǂ�BSC���_��Tc�ɗL���ɂȂ�Ǝ������ꂽ�A�t�F���~�ʋߖT�̏�Ԗ��x������������ʂ𗘗p�������̂ł��B
�@��`����Ԃł́AFig.5�̂悤�Ƀt�F���~�ʂ�艺�͓d�q�Ŗ�������Ă���A�������͓d�q�����Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��B���`����ԂɂȂ�ƁA�t�F���~���ʂ�艺�ɓd�q���{�[�Y�E�A�C���V���^�C���Ïk���܂��B�܂�A�N�[�p�[�y�A���`���ł���d�q�̓t�F���~�ʋߖT�ɂ���d�q�����Ƃ������Ƃł��BBCS���_�ł́AN(0)��傫�����邱�Ƃ�����Tc�����������邱�ƂɗL���ł���Ƃ���Ă��܂����A����͒��`���d�q�ɂȂ��d�q�̐��𑝂₵�A��葽���̓d�q�`�������ɊW�����邱�Ƃɑ������܂��B
�@���̂悤��N(0)�𑝂₷�Ƃ������@�́AMatthias�̂悤�ɒ��`���T���̒��ŗމ��̂�荂��Tc�������`���̂�T�����@�Ƃ��Ė𗧂��܂��BNaCl(B1)�^��A15�^�Ȃǂ��A���̍l�����ɂ���ėމ��ő����̒��`���̂���������܂����B��������l�ȕ��@�ŁA�������`���̗̂މ��ł�荂��Tc������������������邩������܂���B
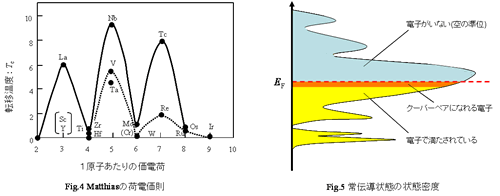
�E �����ԉ��������`���̂̌����\��
�@�����ԉ��������`���̂́A����1000��߂��̂��̂���������Ă��܂��B�܂��A���`���T���̗��j���������Ƃ���A���p�̖ʂł��g�p����Ă�����̂����݂��܂��B�����ł́A���̒���Tc���X�V���Ă����������𒆐S�ɁA���̌����\���̓����������Ă����܂��B
NaCl�^(B1 type)���`����
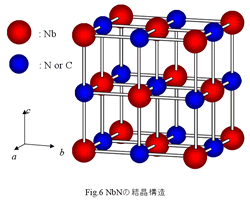
�@���`���̗��j�̒��ŁA�ŏ���10 K���z�����̂�����NaCl�^(B1 type)���`���̂ł��B��Ȃ��̂́A�J�ڋ���(Ti, Zr, Hf, V, Nb, Mo, W)�ƒY�f(C)���邢�͒��f(N)�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł��B���̌n�ōō���Tc�������`���̂́ANbN��17.7 K�ł��B
�@���̒��`���̂ł�TMC(TM: transition metal)�̒Y�����̂Ƃ�����TMN(TM: transition metal)�̒������Ƃ����ق����A�ǂ̑J�ڋ����̏ꍇ�ł�Tc�������Ȃ�܂����B����́A�\�����錳�f��C����N�ɕς�邱�Ƃɂ���āA�t�F���~�ʋߖT�̏�Ԗ��x���オ�������ʂɂ����̂Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł��܂��B���̒���Mo�ł́AMoC��Tc = 13 K�Ɠ����Ƃ��Ă͍���Tc�����������Ƃ���AMoN�̎������`�����o��̂ł�?�Ɨ\�z����܂����B�c�O�Ȃ���MoN�́A�P���ō������邱�Ƃ�����A���`�����m�F�����ƕ���Ă�����̂ł��ANbN�����Ⴍ�A���҂��ꂽ�قǂ̍������x�ł̒��`���͂̕Ȃ���Ă��܂���B�܂��A�g����NbN1-xCx�Ƃ����n�ł́ANbN��17.7 K���������钴�`������������Ă��܂��B
�@���̌n�̒��`���̂̔��������������ɁA�����ԉ������ł̒��`���T���������ɂȂ�܂����B
A15�^���`����
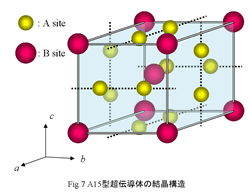
�@A15�^���`���̂́A���߂�20 K���z����Tc�������������Q�ł��B1954�N�ɍŏ���A15�^���`���̂��o�ꂷ��ƁAMatthias��̌����O���[�v�ɂ���Đ��͓I�Ɍ�������A�މ������ł��������̒��`���̂���������܂����B���̌n�ōō���Tc��L���钴�`���̂́ANb3Ge��23.5 K�ƂȂ��Ă��܂�(�A���A���������ł�)�B
�@A15�^���`���̂�A3B�̑g����������AFig.7�̂悤�Ȍ����\�����Ƃ��Ă��܂��B���A�T�C�g���J�ڋ�����B�T�C�g��Ge��Sn�ƂȂ��Ă��܂��B
�@A15�^���`���̂́A���̔�r�I����Tc�ƈ����₷�������̐��������āANb-Ti�����ȂǂƋ��ɉ��p�̖ʂł����͓I�Ɍ�������Ă��܂��BNb3Sn�Ȃǂ́A���`���d���̃R�C���Ƃ��Č�������Ă��܂����B�a�@�Ȃǂɂ���MRI(Magnetic Resonance Imaging)�Ȃǂł��AA15�^���`���R�C�����g�p����Ă�����̂�����܂��B���������ł��AMPMS�@(Magnetic property measurement system)��SQUID�f�q(Superconducting QUantum Interference Device)�Ƃ��āA�������������̕�������ɂ��̈З͂����Ă��܂��B
A3C60�@(A : alkali metal)���`����
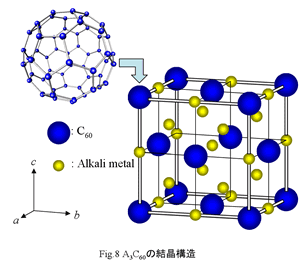
�@���_�������`���̂��r���𗁂юn�߂����ɔ������ꂽ�̂��AC60(�t���[���� : Fullerene)�̒��`���̂ł��B�t���[������C��60�W�܂��āA�T�b�J�[�{�[���^���Ƃ������̂ł��B�ȑO��肱�̍\�����ł��邱�Ƃ͗\�z����Ă��܂������A���ۂɔ��������ƁA���̍\���̖ʔ������瑽���̌������Ȃ���Ă��܂����B
�@�t���[��������Tc = 17 K�̔�r�ITc�̍������`���̂ł����A�P�̌��f�̒��ň�ԑ傫���C�I�����a�����A���J������(Alkali metal)�ƁAA3C60(A: alkali metal)�Ƃ����g����̉��������`�����܂��B�A���J�����������g�����`���������Ȃ��̂ɁA�C�I���Ƃ��ċ����C60�ƌ������`�����邱�ƂŒ��`���������_�������[���Ƃ���ł��B���̌n�ōō�Tc�������`���̂́ARbCs2C60��Tc = 33 K�ł�(�������ł́ACs3C60��Tc = 40 K�Œ��`���������܂�)�B
�@�Y�f����Ȃ镨���Ƃ��ẮA�t���[�����̂ق��ɃO���t�@�C�g�A�_�C�������h�A�J�[�{���i�m�`���[�u�Ȃǂ�����܂��B�ŋ߁A�z�[�����h�[�v�����_�C�������h�Œ��`������������ȂǁA�����ƒ��`�������̐��E����킹�Ă���n�ł��B������͒Y�f�������Ŏ������`������������邩������܂���B
��Y����YPd2B2C, YNi2B2C���`����
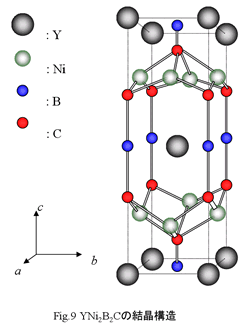
�@���_�������`���̃t�B�[�o�[�ɂ���ĉ����Ƃɂ��₩������1994�N�ɁACava�ƍ���ɂ���ĕ��ꂽ�̂��A������Y�������`����YPd2B2C(Tc = 23 K)��YNi2B2C(Tc = 15.6 K)�ł��B�����\����Fig.8�̂悤�ɂȂ��Ă���AYC�w��Ni2B2�w����Ȃ���̑w��\���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��܂�(�d�C�`����3�����I�ł�)�BTc�������̂�YPd2B2C�̕��Ȃ̂ł����A�P�������̍���������Ȃ��Ƃ�����A���݁A��Ɍ�������Ă���̂�YNi2B2C�̕��ł��B���̒��`���̂ł́A��Ԗ��x�̌v�Z�Ȃǂ���A�J�ڋ���: Ni��3d�d�q����r�I����Tc�ɋN�����Ă���ƍl�����Ă��܂��B�܂��A�g���l�������Ȃǂ̌��ʂ���A�]����BCS���`���ł��邱�Ƃ���������Ă��܂����B�������A�ŋ߂̔M�`���x�̎�������ABCS���`���Ƃ͈قȂ钴�`���M���b�v�̌`��Ă���A���ڂ���Ă��܂��B
�@YNi2B2C�̌n�ł́AY�T�C�g����y�ތ��f�Œu�������n�ł����`��������Ă��܂��BY�T�C�g����y�ތ��f�Œu���������ʁA�{�����`����Ԃ����������鎥���ƒ��`������������Ƃ��������[���n�ƂȂ�܂��B���̂���RENi2B2C(RE: Ho, Er, Tm)�n�ł̓��G���g�����g�^���`��(���`����Ԃ���x���Ăђ��`���ɖ߂�)�ƌĂ��ʔ������`���]�ڂ��ϑ�����Ă��܂��B
�w�������`����
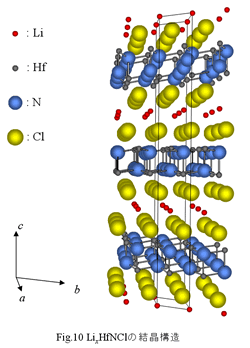
�@1998�N�ɕ��ꂽ�̂��A�w�����ƌĂ���A�̃n���Q���������̒��`���̂ł��B���̌n�ň�ԍ���Tc���������̂̈���AFig.10�Ɏ�����LixHfNCl��Tc = 25.5 K�̒��`���ł��B
�@���̕����̓����Ƃ��āACl-Cl�Ԃ�Li���C���^�[�J���[�g����邱�ƂŒ��`�������Ɏ���Ƃ������Ƃ��������܂��B�ꕨ��HfNCl��2�d�n�j�J��(�I�̑�)�\�����`������HfN�w��Cl�w����Ȃ�w��\�����`�����Ă��܂��B�܂��ACl-Cl�Ԃ������͂̎ア�t�@���E�f���E���[���X�����ō\������Ă���̂��傫�ȓ����ł��BGraphite(�O���t�@�C�g)�ȂǂŗL���ł����A���̂悤�ȑw�Ԃɂ͌����\����ۂ����܂ܑ����f��}�����邱�Ƃ��ł��A����ɕ����̕ω���^���邱�Ƃ��ł��܂��BLixHfNCl��Li�C���^�[�J���[�g�ɂ����HfN�w�ɃG���N�g�������h�[�v����A���`�������Ɏ������ƍl�����Ă��܂��B
�@���̌n�ł́A�މ������̒��`���̂������������Ă��܂��BHfNCl�Ɠ������ɔ������ꂽZrNCl�ł́A�C���^�[�J���[�g�ɂ��G���N�g�����h�[�v���`����Cl���f����ZrNCl1-x�̃z�[���h�[�v�ł����`�����m�F����Ă��܂��B�܂��ACl-Cl�w�ԂɗL�@�����C���^�[�J���[�g���������ł��A20 K���̒��`�����m�F����Ă��܂��B
�@�w�����n�͂܂��܂����W�r��i�K�ł���A��荂��Tc��L���镨���̔��������҂���Ă��܂��B
�퉻��MgB2�̒��`��
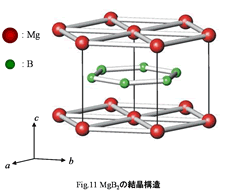
�@21���I�̖��J���Ƌ��ɕ��ꂽ�̂��A�퉻��MgB2�̒��`���ł��BTc = 39 K�Ƃ������_�������`���̂ɕC�G����Tc�����������Ƃ���A��ϒ��ڂ���܂����B�܂��A���̕����́A���_�������`���̂Ɣ�ׂ�ƁA�y�ʊ������R�X�g�������A���H�v���Z�X�ł̃R�X�g�_�E�����\�Ƃ��������b�g���������킹�Ă��邱�Ƃ���A���`�����ނƂ��Ẳ��p�I���ʂ�������ɊS���W�܂��Ă��܂��B���݁A~20K�ł�MRI�A�e��f�o�C�X��t�̃w���E����p���ł̏]���ޗ�(Nb-Ti, Nb3Sn)�̑�ւ��^�[�Q�b�g�Ƃ��āAMgB2���ނ̊J�������{�A�A�����J�A���[���b�p�ōs���Ă���A���ɊJ�������Ƃ������l���ł��B
�@MgB2�̌����\���́AFig.10�̂悤�ɎO�p�i�q����Ȃ�Mg�w�ƘZ������Ȃ�B�w��c�������Ɍ��݂ɐϑw����2�������̋����\���ƂȂ��Ă��܂��B���̂��߁AMgB2�̕����I�����ɂ����������������f�������ʂ��ϑ�����Ă��܂��B
�@���̒��`���̂̔����ȍ~�A�Ăы����ԉ��������r���𗁂сA�މ����퉻����Y�����̒��`���T��������ɂȂ��Ă��܂����B���̌��ʁA�l�X�Ȓ��`���̂���������܂������AMgB2��Tc���z����悤�Ȓ��`���̂͗މ������ł͔�������Ă��܂���B
[1] J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani and J. Akimitsu, Nature. 410 (2001) 63
[2] J. Bardeen, L. N. Cooper and J. R. Schrieffer, Phys. Rev. 108 (1957) 1175
[3] Matthias. Bernd T et al, Science 156 (1967) 645
[4] W. L. McMillan, Phys. Rev. 167 (1968) 331
[5] Aschermann, Friederich, Justi and Kramer, Z. Phys. 42 (1941) 349
[6] K. Tanigaki et al., Nature 352 (1991) 222
[7] R. J. Cava, H. Takagi, H. W. Zanbergen, J. J. Krajewski, W. F. Peck, T. Siegrist, B. Batlogg, R. B. van Dover, R. J. Felder, K. Mizuhashi, J. O. Lee, H. Eisaki and S. Uchida, Nature 367 (1994) 252
[8] S. Yamanaka et al., Nature 392 (1998) 580