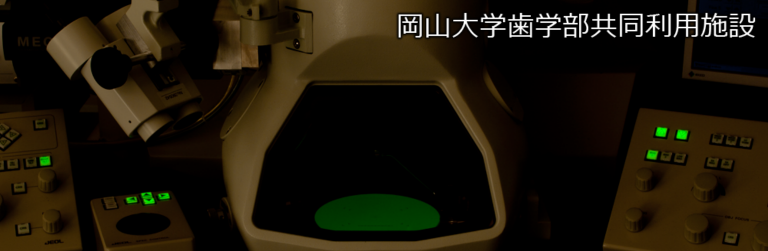組織学標本の作製
ここでは普遍性の高い試料作成法を紹介する。実験に多く用いられるラットの組織を対象とする。H-Eなどの一般染色だけでなく、免疫染色やin situ hybridizationなどにも利用できるが、染色の種類により、特殊な固定液や薄切法が指定される場合があるので、注意が必要である。I.プレパラート作成の手順 |
|---|
1)固定(動物の屠殺、潅流固定)からパラフィン包埋まで
2)薄切(ミクロトーム)
3)染色
II.固定(動物の屠殺、潅流固定)からパラフィン包埋まで |
|---|
〇年〇月〇日 |
|
固定からパラフィン包埋までは一連の作業として行うのがよい。固定には0.1Mリン酸緩衝4%ホルムアルデヒド固定液を用いる。これはH-E染色など、光顕の一般染色に広く利用される。古典的な10%ホルマリン固定液(ホルムアルデヒドの40%水溶液をホルマリンと呼ぶ)と同等とみなしてよいが、10%ホルマリンの場合の欠点であった蟻酸の生成やpHの不安定といった欠点が改善されている。免疫染色やin situ hybridizationなどにも利用される。古典的な10%ホルマリン固定液と同じ用途に使用できる。 潅流固定は血管中の血液を固定液で置換する方法で、固定液が急速に浸透する利点があるが、目的とする組織によっては生の試料をより高濃度の固定液に浸漬して固定(浸漬固定)する方が望ましい場合もある。また固定後、パラフィン包埋を行わず凍結切片を作成する方法もある。 A.準備する試薬とその調整1)リン酸緩衝生理食塩水(PBS)、1000 ml
蒸留水900 ml に完全に溶解した後、さらに蒸留水を加えて総量を1000 mlとする。 上記の処方でpHは7.3-7.4になり、特に調整の必要はない。室温で1ヶ月程度の保存なら変質しない。 2)リン酸緩衝生理食塩水(PBS)、1000 ml
室温で1ヶ月程度の保存なら変質しない。 3)0.1Mリン酸緩衝4%ホルムアルデヒド固定液、500 ml パラホルムアルデヒド20 gを乾燥した三角フラスコにとり、蒸留水200 mlを加え、マグミキサーで攪拌氏ながら70-80℃にまで加熱する。マグミキサーにヒーターがついていない 鼾№ヘ、? 閧ナ震盪しながらガスバーナーで加熱してもよい。慣れれば手でフラスコの外壁を触った感覚で温度を判定する程度でよい。 温度が上がったところで1規定水酸化ナトリウムを4-5滴加え、強く攪拌攪拌する。1-2分でほぼ完全に溶解し、底にごくわずかな顆粒を残す以外は透明になる。溶けにくい場合は、温度が低すぎるならもう少し加熱を続けるか、水酸化ナトリウムを1滴追加する。 溶解したら直ちにフラスコを流水または氷で室温程度まで冷却し、0.2Mリン酸緩衝液(pH 7.4)250 mlを加え、さらに蒸留水を加えて総量を500 mlとする。 室温または4℃で数日間の保存が可能であるが、なるべく調整当日に使用することが望ましい。 4)脱水用アルコール(50%, 70%, 80%, 90%, 95%, 100%) 99%以上のアルコールを100%と考えて、蒸留水を加えて使用する。厳密な濃度調整は必要なく、たとえば50%であればアルコール50 mlに蒸留水50 mlを加えればよい。 5)その他の試薬 トルエン:透徹用。 パラプラスト・プラス(シグマ社):包埋用、従来使用されてきたパラフィンの品質を安定させ、包埋に最適に調整された製品。以後、単にパラフィンと呼ぶ。 B.器具類1)試薬調整用のガラス容器類(フラスコ、メスシリンダー、ピペットなど) 2)手術器具(ハサミ、ピンセットなど) 3)バット(手術を行ない血液などを受ける、大型で浅いものがよい) 4)標本瓶(試料体積の40倍程度以上の容量ものが望ましい、プラスチックなどの蓋付きが便利) 5)点滴用の瓶2個、輸液チューブ、3方活栓、注射針(18G, S.B.) セットアップ:三方活栓で注射針に2個の瓶をつなぎ、落差を70 cmから1 m程度にする。一方の瓶に固定液を400-450 ml満たし、活栓までの空気を抜き、他方にはPBSを50 ml程入れ、チューブの空気を完全に抜き、止血鉗子で止める。活栓から針までの間に固定液があってはならない。PBSの潅流によって血液が洗い流されるまえに固定液が血液に触れると、血管内で血液が凝固するからである。用意した固定液のうち50 mlは後固定のため、標本瓶に入れておく。 6)恒温器(パラフィン溶融器、60℃) C.固定1)動物の麻酔 ネンブタール50 mg/kgの腹腔内注射による。エーテル麻酔の場合は、エーテル蒸気の充満したデシケーターに動物を入れ、強い呼吸抑制が現れるまで待ってから次に進む。浅い麻酔で苦痛を与えてはならない。低酸素状態では血管拡張が期待でき潅流の効果が高まるのに対し、苦痛をあたえると倫理的問題があるだけでなく、血管収縮によって潅流が不完全になる可能性もある 2)手術と瀉血 側胸壁を肋骨・皮膚とも一括して縦に切開し、横隔膜を切り離して前胸壁を上方に開き、左手で保持する、右手でハサミを使い、心膜を開いて右心耳を切開する。ハサミを捨て、右手で心尖から大動脈にむかって注射針を刺入するが、べベルが完全に隠れるまで刺入できたところで止める。ただちに止血鉗子を開き、全開でPBSを流す。開胸の開始から遅くとも1分以内にPBSの潅流を開始する。注射針の先端は左心室内にあり、注入された液は左心室から大循環に入り、右心室に戻ったところで右心耳の切開から体外に出ることになる。潅流固定は一人でできるが、慣れるまでは活栓の管理などを補助する助手が必要。 3)液の量と時間 右心耳から出る液に血液があまり混じらなくなれば(PBS 30 ml程度の潅流でよい)、活栓を切り替えて固定液を全開で流す、固定液の潅流開始直後には、筋組織が収縮するため、激しい痙攣がおきる。前胸壁を左手で、注射針を右手で、しっかり保持しておく。痙攣がおさまるころから、血管の抵抗がたかまり、流速が低下するが、そのまま潅流を続けると、約20分以内に固定液がすべて消費され、潅流固定が終了する。 4)切り出し 4) 死体を解剖し、目的とする組織を摘出する。研究目的によって異なるが、組織ブロックの大きさは5 mm角程度より小さいと以後の処理(脱水、包埋、薄切)が容易である。ブロックを標本瓶の固定液に浸漬し、後固定を行う。後固定は数時間から数日まで幅があり、多くの場合2-3時間で十分である。免疫染色など一部の染色方法では、長時間の後固定で染色性に問題が生じるが、H-Eでは問題ない。一般には、帰宅前に固定液を捨て、PBSによる洗浄にかかればよい。 D.脱水、透徹、パラフィン浸透、パラフィン包埋組織ブロックの大きさを5 mm角程度とし、それより大きい場合はすべてのステップで時間を適宜延長する。なお脱水洗浄の各ステップでは組織ブロックの体積の40倍以上の薬液を使用する。ここで説明する操作の時間は、あくまで無難な範囲であるが、脱水・パラフィン浸透は時間が短すぎると不完全で、巣が入ったようになる。一方長過ぎると組織が硬化して、薄切が困難になることもある。このため、組織の種類によっては、ブロックの大きさを制限するなどして脱水・包埋時間を最低限に抑える工夫が必要である。また、すべての操作を手動で行う場合は、時間調整のため、いずれかのステップをオーバーナイトに延長するなどの工夫が必要になる。 1)洗浄 脱水に先立ってPBSでよく洗浄する、これは組織に残留する未反応ホルムアルデヒドが染色性を阻害するからである。 合計24-36時間程度の洗浄時間中にPBSを3-4回交換して洗浄する。洗浄後、4℃のPBS中で数時間から数日間保存して時間調整を行ってもよい。 2)脱水 脱水アルコール系列は順に、50%, 70%, 80%, 90%, 95%を各1回づつ、および100%を3回とする。組織によって異なるが、各ステップに4時間程度で十分である。大きな容器にアルコール系列をつくっておき、組織ブロックを順次移動させてゆく方法と、小さな標本瓶でアルコールを交換してゆく方法がある。前者ではアルコール系列を繰り返し使用できる。 3)透徹 アルコールはパラフィンと混じりあわないので、脱水後、組織ブロックをトルエンに2回(各4時間程度)とおして透徹する。 4)パラフィン浸透 恒温器(60℃)に、蓋付き広口瓶(100 ml)3個に8分目程度パラフィンを入れて融解しておく。ただし1個はパラフィンの量を半分とし、トルエンを等量加えておく(トルエン−パラフィン)。トルエン−パラフィンに約2時間、パラフィンI, IIにそれぞれ4時間づつ浸漬し、パラフィンを浸透させる。パラフィンから組織ブロックをつまみあげるとき、パラフィンがピンセットに付着凝固するので、アルコールランプなどでピンセットを少し温めて、手早く操作するのがよい。 5)包埋 包埋には専用の磁器製容器を用いるか、折り紙細工で矩形の箱を作って用いる。5 mm角の立方体のブロックなら、底面20 mm角正方形、深さ10 mm程度の箱を用意する。磁器製容器を用いる場合、分離剤として石鹸水などを塗り、パラフィンが硬化しないよう恒温器で温めておく。容器に十分な深さのパラフィンIIを注ぎ、組織ブロックを沈め、なるべく早く冷却する。室温で保存してよいが、長期保存の場合は染色の種類に応じて冷蔵保存などが必要となる(例、免疫染色)。 |
|
パラフィン包埋ブロックを、ミクロトームを使って薄切し、スライドグラスに貼り付けるまでの操作である。この操作の大部分はミクロトームを用いるので、ミクロト−ムのタイプによって異なる。共通部分を説明する。 A.器具と消耗品1)ミクロト−ム 2)ミクロト−ム用ナイフ 3)台木(組織切片作成用として市販されている、3 cm角の立方体に近い木片) 4)パラフィン用スパーテル 5)パラフィン伸展台または温湯をいれた容器(直径20 cm程度の大型シャーレなど) 6)糊のついていない小筆、柄付き針など 7)工作ナイフ(安全カミソリ、オルファナイフ) 8)ガーゼ、キムワイプなど 9)スライドグラス(シランコートされたもの) B.薄切、貼付1)スパーテルを加熱し、パラフィンブロックの底面を加熱し、台木に固定する。 2)工作ナイフで切断面をほぼ長方形にトリミングする。 3)ミクロトームのナイフを装着する。 4)台木を試料台のチャックに固定する。 5)ミクロトームを操作し、切片を作成する。 6)ミクロト−ムナイフにのった切片を1枚ずつ、あるいは、リボン状に連続した切片をまとめてスライドグラス上に載せた蒸留水の上に浮かべ、伸展台で加温(30-40℃)して伸展し、室温または恒温器(37℃)で1-2晩置いて乾燥する。切片を温湯に浮かべて伸展した後、スライドグラスに掬いあげる方法もある。 7)上記操作では、必要に応じて小筆などを使用する。 8)切片はそのまま埃を避けて保存できるが、長期の場合、染色法によっては冷蔵・冷凍が必要になる。 |