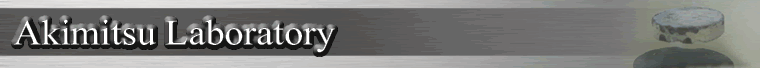 |
||||||||||
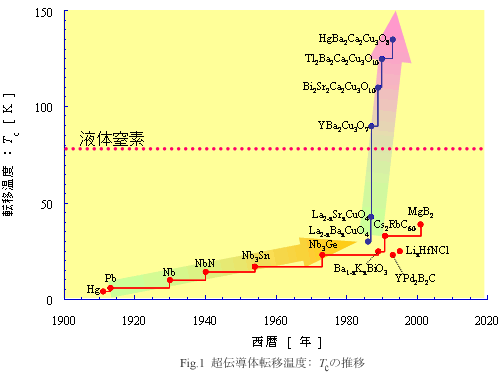
Fig.1を年代を追って見ていきますと、まずHgから始まった単体元素の超伝導体ですが、ヘリウムの液化技術の発達とともに次々と発見され、1930年ごろにはNbの9.2 K にまで達しました。
1930年を過ぎた頃からは、合金や金属間化合物の超伝導体が登場します。まずTcを塗り替えたのが、B1型構造(NaCl type)を持つ超伝導物質群です。この系では、1940年ごろ発見されたNbN[1]が17.3 Kという高いTcを記録しています。そして、B1型物質群のTcがほぼ頭打ちになった1950年代に入ると、今度はA15型構造をもつ超伝導物質群が登場します。この系では、20 Kに迫る超伝導体Nb3Sn[2]が発見されたことから、超伝導探索の主流はこのA15型物質群となっていきました。その結果、1970年代半ばにはNb3Ge[3]によるTc = 23.3 Kにまで達しました。
そして1986年、J. G. BednorzとK. A. Müllerによって発見されたLa-Ba-Cu-O系[4]から始まった一連の銅酸化物超伝導体の登場です。後に組成がLa2-xBaxCuO4と特定されたこの超伝導体は、当時の最高記録であったNb3GeのTcの2倍近くあるTc〜40 K級の超伝導を示すことがわかりました。この発見に続き、Tcの最高記録は飛躍的に上昇し、そのわずか一年後には窒素の液化温度77 Kを越える超伝導体YBa2Cu3O7-[5]が発見され、その2年後にはBi2Sr2Ca2Cu3O10[6]やTl2Ba2Ca2Cu3O10[7]などの100 Kを越える超伝導体の発見に至りました。その後の精力的な研究によって、現在ではHg2Ba2Ca2Cu3O10[8] の圧力下でしめす164 Kが最高Tcの記録となっています。これら銅酸化物超伝導体の発見までのTcの更新が1K/3年であったのに比べ、銅酸化物超伝導体の登場により、一気にその記録を破っていったことをみると、いかにその発見が衝撃的なものであったかがわかります。また、J. G. BednorzとK. A. Müllerは1987年のノーベル物理学賞を受賞しました。
当時、大学、研究機関や企業までをも巻き込んだ”銅酸化物超伝導体フィーバー”の裏側で、銅を含まない酸化物や金属間化合物などでも比較的高いTcを持つユニークな超伝導体が発見されています。1988年には銅酸化物と同じペロブスカイト構造を取る酸化物のBa1-xKxBiO3[9]が30 Kで超伝導を示す物質として発見されました。現在でも銅酸化物を除いた酸化物超伝導体の中では、最高のTcを持っています。この物質では、電荷密度波(CDW = Charge Density Wave)が超伝導と密接に関連してるのではないかといわれています。1990年に入ると、まずは60個のCがサッカーボール型に結合したフラーレン: C60が注目を集めました。通常のイオンと比較して非常に大きい塊であるC60は、金属イオンで最もイオン半径の大きいアルカリ金属類とA3C60という化合物をとることにより、最高でTc = 33 K(RbCs2C60)[10]の超伝導を示すことが発見されました。このフラーレンに続き、1994年には硼炭化物における層状構造を持つ新物質YNi2B2C(Tc = 15.4 K)[11], YPd2B2C(Tc = 23 K)[12]や、1998年のLixHfNCl(Tc = 25.5 K)[13]など、それまで金属間化合物で最高のTcであったNb3Snの23.3 Kに匹敵するTcを有した超伝導体が次々に発見されました。これらのTcは、BCS理論による限界「BCSの壁」に既に到達していると、一般に信じられており、金属間化合物のTcは頭打ちであろうと考えられていました。そして、21世紀に入りMgB2[14]が金属間化合物でそれまで最高のTcを持っていたNb3SnのTcを約2倍近く更新する39 Kという高いTcを持つ物質として発見されました。このような単純な化合物が思いも寄らない高いTcを示し、しかも試薬として販売されていたことから、原料等の類似物質の再評価が盛んになり、大きな話題を呼びました。現在のところ、MgB2は金属間化合物では最も高いTcを持っています。
[1] Aschermann, Friederich, Justi and Kramer, Z. Phys. 42 (1941) 349
[2] B. T. Matthias et al., Science 156 (1967) 645
[3] J. R. Gavaler, Appl. Phys. Lett. 23 (1973) 480
[4] J. G. Bednorz and K. A. Müller, Z. Phys. B64 (1986) 189
[5] M. K. Wu, J. R. Ashburn, C. J. Thorng, P. H. Hor, R. L. Meng, L. Gao, Z. J. Huang, Y. Q. Wang and C. W. Chu, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 908
[6] H. Maeda, Y. Tanaka, M. Fujitomo and T. Asano, Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) L209
[7] Z. Z. Sheng and A. M. Hermann, Nature 332 (1988) 138
[8] L. Gao et al., Phys. Rev. B 50 4260 (1994)
[9] R. J. Cava et al., Nature 332 (1988) 814
[10] K. Tanigaki et al., Nature 352 (1991) 222
[11] R. J. Cava, H. Takagi, H. W. Zanbergen, J. J. Krajewski, W. F. Peck, T. Siegrist, B. Batlogg, R. B. van Dover, R. J. Felder, K. Mizuhashi, J. O. Lee, H. Eisaki and S. Uchida, Nature 367 (1994) 252
[12] R. J. Cava, H. Takagi, B. Batlogg, H. W. Zanbergen, J. J. Krajewski, W. F. Peck, R. B. van Dover, R. J. Felder, T. Siegrist, K. Mizuhashi, J. O. Lee, H. Eisaki and S. Uchida, Nature 367 (1994) 146
[13] S. Yamanaka et al., Nature 392 (1998) 580
[14] J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani and J. Akimitsu, Nature 410 (2001) 63
[関連項目]
・秋光研究室の超伝導発見の歴史