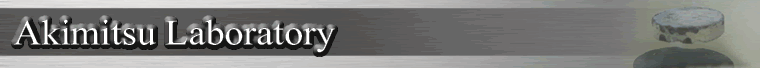 |
||||||||||
1. �����Ɏ���w�i
3. MgB2�̓d�q���
5. MgB2�̒��`���@�\ �|�d�q�i�q���ݍ�p�|
6. MgB2�̗ՊE���x����̉\���Ǝ��ӐV���`�������T��
7. �I����
�@���`���̗��j���A1911�N��H. Kameringh Onnes�ɂ��Hg(Tc=4.2 K)�̔������獏�ݎn�߂��A����܂łɎ��ɑ����̒��`���̂��P�̌��f�A�����ԉ������ɂ����Ĕ�������Ă��܂����B�����ԉ������̒��`���̂Ƃ��Ă�A15�^���`���̂��ł��ǂ��m���Ă���A���̑�����1950�N���B. T. Matthias��J. K. Hulm��̌����ɂ����̂ł��B����Ȍ�̐��͓I�Ȍ����̌��ʁANb3Ge(Tc=23 K)���A�����ԉ��������`���̒��ł͍ō���Tc�ƂȂ��Ă��܂����B�܂��A����܂łɔ������ꂽ���`���̂́A�T��BCS���_�ɂ���Đ������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��m���߂��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A1986�N��J. G. Bednorz��K. A. Müller�ɂ��La-Ba-Cu-O�n�̔�������n�܂�����A�̓��_�������`���̂̓o��ɂ���āA���̋L�^�����X�ƍX�V�����Ƌ��ɁA�]����BCS���_�ł͐����o���Ȃ����Ƃ�������Ă�������ŁA�����ԉ��������`���̂�Tc�͂قړ��ł��̏�Ԃł����B�����҂̊Ԃł́ABCS���_�ɂ��Tc�̌��E�l�uBCS�̕ǁv����30K���x�ƈ�ʂɐM�����Ă������߁A�����ԉ������ł͂���ȏ㍂��Tc�͖]�߂Ȃ����낤�ƍl�����Ă��܂����B���̂悤�ȏ̒��A�V���`����MgB2(Tc=39 K)�̑��A�Ȍ������̈挤���u�J�ڋ����_�����v�������ʕ�i2001�N1��8���`10���A���k��w�����ޗ��������j�ɂ����āA�R�w�@��w�A�H�� �������ɂ���Ĕ��\����܂����BMgB2�́A����܂ł̋����ԉ��������`���̂�Tc��2�{�߂�����A��{�I�ɂ�BCS�@�\�ł���Ȃ���A������uBCS�̕ǁv���z���������Ȃ̂ł�?�Ƃ������Ҋ������܂��āA�������ォ�炻�̒��`�������@�\�Ɋւ��đ����̌����҂̋������W�߂܂����B�܂��A���̕����͇@�y�ʊ������R�X�g�������A�A�������Ԃ̎㌋�������݂��Ȃ����ߓ��_�������`���̂������H�v���Z�X���ȕցA�B���_�������`���̂����Ȃ������ɗD���Ƃ��������b�g���������킹�Ă���A���`���ޗ��Ƃ��Ẳ��p�I���ʂ�������ɊS���W�܂��Ă��܂��B
MgB2�͌Â�����m��ꂽ�������ŁA���̌����\����Fig.1�Ɏ����܂��B���̍\����AlB2�^�\���ƌĂ�A�O���t�@�C�g�ƍ��������I�̑��i�q��̃l�b�g���[�N��g�z�E�f�̑w���A�O�p�i�q��g��Mg�̑w�ɂ���ċ��܂ꂽ�w��\���ɂȂ��Ă��܂��BAlB2�^�\�����Ƃ镨���̒��`���������Â�����悭���ׂ��Ă���A1970�N�ɂ́ACooper�炪���l�̌����\�����Ƃ��A�̕���(YB2, ZrB2, NbB2, MoB2)�̒��`��(B-rich��NbB2: Tc=3.87K, Zr0.13Mo0.87B2: Tc�`11K)����Ă��܂��B�܂�1979�N�ɂ́ALeyarovska�炪MB2(M: Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo)�������̒��`��(NbB2: Tc=0.62K)����Ă��܂��B���̂悤�ɑ����̌���������ɂ�������炸�AMgB2�݂̂����̒��`�����������肳�ꂸ�Ɏ��c����Ă����킯�ŁA��ϕs�v�c�Ȃ��Ƃƌ���˂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
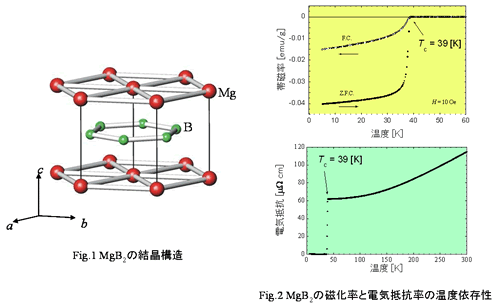
�@MgB2�̔����̕�A�Ԃ��Ȃ��AJ. Kortus��ɂ��MgB2�̃o���h�v�Z�̕��Ȃ���܂����BMgB2���ł̃z�E�f�͖I�̑��^�i�q�w���`�����Ă���A�����Mg�͂ق�+2���ŃC�I�������Ă��̒��ɏ[�U����Ă��āA�z�E�f1������1�̓d�q���������Ă��܂��B�܂�A�z�E�f�ɂ���Č`�������2�����ʂ́A�z�E�f���d�q��1�����Y�f(C)�ɂ���Č`�������O���t�@�C�g�Ɠ������ƂɂȂ�AMgB2�̃o���h�\���̓O���t�@�C�g�ƑΉ������邱�Ƃ��o���܂��B
�@�o���h�v�Z�ɂ���ē���ꂽ�t�F���~���x���ߖT�̓d�q��Ԃ́Asp2�O���ɂ���č\�������p���o���h��pz�O���ɂ���Č`�������p���o���h���琬���Ă���A�O���t�@�C�g�ł�p���o���h�̈ʒu���t�F���~���x���ɑ��Đ[���A���ׂēd�q�Ŗ��߂��Ă����(Fig.3(a))�ɑ��āAMgB2�ł�p���o���h���t�F���~�ʋߖT�Ɉʒu���Ă���(Fig.3(b))�A�~����̃z�[���̃t�F���~�ʂ��`�����Ă��܂��B����Ap���o���h��3�����I�l�b�g���[�N��L����t�F���~�ʂ��`�����Ap���o���h�̃z�[���ɂ��p���o���h�ɂ͓d�q����������Ă��āA�d�q�ʂ̓z�[���ʂɔ�ׂĔ�債�Ă��܂��B�Ɨ̉~����̃t�F���~��(p��)�Ɛ̊Ǐ�̃t�F���~��(p��)�̓z�[���ʂ�\���A�Ԃ̊Ǐ�̃t�F���~��(p��)�͓d�q�ʂ�\���Ă��܂�(Fig.4)�B���̂悤�Ɍv�Z�ɂ���ē���ꂽ�o���h�\���̓����́A���ˌ�X����܂�p����MEM(Maximum Entropy Method: �ő�G���g���s�[�@)/Rietveld(���[�g�x���g)��͂ɂ���ē���ꂽ�d�ו��z�}����A���̑Ó�����������Ă��܂��B������̑����̎����ɂ���āAMgB2�̒��`����p���o���h��ʂ��āA�L�����A���z�E�f�̓���(p���o���h)�ɋ�������A���p���o���h�����`����S���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B����Ɠ����ɁA���_�������`���̂Ƃ̗ގ��_�Ƒ���_����������ɂ���Ă��܂����B�傫�ȗގ��_�́AMgB2�Ɠ��_�����Ƃ��d�����w��Mg2+�ƃu���b�N�w�Ƃ��ꂼ�ꑶ�݂��Ă��邱�Ƃł��B��ԑ傫�ȑ���_�́AMgB2�ł͌����Ɋ֗^���Ă���p���o���h�ɒ��ڃL�����A����������Ă��邱�Ƃł��B������̑傫�ȑ���_�́A���`����S���Ă���o���h��p���o���h��p���o���h�̗����ł���Ƃ����_�ł��B���̂悤��2�̃o���h�������ɒ��`����S���Ă���͈̂ꌩ�s�v�c�Ɏv���܂����A��M, ���d�q����, �g���l������,���}���U�����̑����̑����i�ɂ���Ċm�F����Ă��܂��B
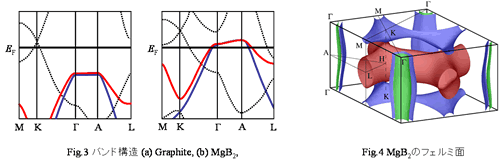
�@�G�l���M�[�M���b�v�Ɋւ��錤������A���`���M���b�v���t�H�m���ɂ�钴�`���̂ɂ����ĉ��肳��邱�Ƃ̑��������Is�g���`���M���b�v�Ƃ͈قȂ�A���d�M���b�v(2�M���b�v)�ł��邱�Ƃ����_�A�����̑o�����玦�������悤�ɂȂ�܂����B������_�@�ɁAMgB2�̓d�q��Ԃ̓����ł��鐫�i�̈قȂ�2��ނ̃o���h�ƒ��`���M���b�v�̑傫���Ƃ̊W��m�邱�Ƃ��A����Tc�̔����̃��J�j�Y���𗝉����邽�߂̌�������ƍl������悤�ɂȂ�܂����B�����̍��̌����̑����́A�^���ʂ�ϕ������`�̏�����������i�ł��������߁A2��ނ̃o���h�ƒ��`���M���b�v�Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ���ɂ͎����Ă͂��܂���ł����B���̂��߁A�^���ʂɕ��������d�q��Ԃ�m�邱�Ƃ̏o���鑪���i�ɂ�錤�����s���ƂȂ�܂����B���ł�ARPES(Angle Resolved Photoemission Spectroscopy: �p�x�������d�q����)��p���邱�Ƃɂ���āAMgB2��2�M���b�v���`���̂ł��邱�Ƃɑ��ł����ړI�ȏ؋���^���܂����B�܂��ASTS(Scanning Tunneling Spectroscopy: �����^�g���l������)�ɂ��������ʂ��L�͂�2�M���b�v���`���̏؋��ƂȂ�܂����B�����]�ډ��x(Tc=39 K)�ɑΉ�����傫�Ȓ��`���M���b�v2L(�`4kBTc)�́A�d�q�i�q���ݍ�p�̋������o���h�ɊJ���A��������o���h�ɂ́A����̖�1/3�̏����ȃM���b�v���J���܂����A���o���h�����`���Ό`���ɐϋɓI�������ʂ����Ă���Ƃ͌��݂̂Ƃ���l�����Ă��܂���B
�@
�t�H�m���ɂ�钴�`���ł́A�d�q�i�q���ݍ�p�̉^���ʈˑ���������ߎ����A�����̏ꍇ�ɂ��ǂ�������^���邱�Ƃ��ł��܂����AMgB2�ł́A�d�q�i�q���ݍ�p�̉^���ʈˑ������A���̍���Tc���܂߂����`�������ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��钴�`���̂ł��邱�Ƃ��킩���Ă����ƌ����܂��B��ʂ�2�M���b�v���`���̂�Tc�͂��܂荂���Ȃ��ƌ����Ă��܂������AMgB2�̏ꍇ�́A���o���h�����o���h�Ƃ̑��ݍ�p�����܂�傫���Ȃ����߂ɁA���o���h�����o���h�ɂ��e�������قǎ邱�ƂȂ��A�傫�ȃM���b�v��ێ��ł����̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂���ʓI�ȉ��߂ƂȂ��Ă��Ă��܂��B�܂��A���}�����������̌��ʂ���́A�d�q�U�����o���h���ƂɈقȂ�\�����w�E����A�������̈قȂ�2��ނ̃o���h���͂��ɑ��ݍ�p���Ă��邪�A�قړƗ��ɐU�镑���Ƃ����̂�MgB2�̒��`���̍ő�̓����ł��B
5. MgB2�̒��`���@�\ �|�d�q�i�q���ݍ�p�|
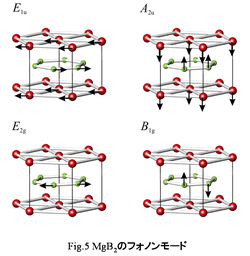
�@
����܂łɕ���Ă��������̌����ɂ��AMgB2�ɂ����钴�`�������Ƀt�H�m��(�i�q�U��)���A���炩�̌`�Ŋ֗^���Ă��邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��ɂ���܂��B���̍ł����ړI�ȏ؋��Ƃ��āA������قǂȂ��A���ʑ̌��ʂ̎���������܂����B10B��11B�ɒu�����邱�Ƃɂ����Tc����1K�ቺ���ATc��M-�Ƃ����Ƃ��̌W��B�`0.26�������Ă��܂��B�܂��A���̌����O���[�v�ɂ���āAMg�̓��ʑ̌���(24Mg, 26Mg)�̓z�E�f�̏ꍇ�ɔ�ׂ�Ɣ��ɏ������AMg�`0.02�ƂȂ邱�Ƃ�����܂����B���̂��Ƃ���A�z�E�f�ɋN�����鋭���d�q�i�q���ݍ�p���d�v�Ȗ����������Ă��邱�Ƃ������I�ɂ킩��܂����B
�@
���_�v�Z���瓾���Ă���MgB2�̃t�H�m���́A�]�[���Z���^�[(�_)�ɂ�����E1u(30-40meV), A2u(40-50meV), E2g(60-70meV), B1g(80-90meV)��4�̃t�H�m�����[�h�����݂��邱�Ƃ��m���Ă��܂��BE1u��Mg��B�̂��ꂼ��̖ʂ�ab�ʕ����ɃX���C�h���郂�[�h�AA2u��Mg��B�̂��ꂼ��̖ʂ�c�������ɐU�����郂�[�h�AE2g�ׂ͗荇��B���t�����ɖʓ��ŐU�����郂�[�h�AB1g�ׂ͗荇��B���t������c���ɉ����ĐU�����郂�[�h�ɑΉ����Ă��܂��B
�@
���̒��ł��A�z�E�f��2�����ʓ��̊i�q�U���ɑΉ�����E2g���[�h���A�ł��d�v�Ȗ������ʂ����Ă��āA�d�q�i�q�����萔�͖�1���x�Ƒ傫�Ȓl�ƂȂ邱�Ƃ����_�I�ɍl�����܂����B���̃t�H�m���Ɋւ��闝�_����̌����̑Ó����́A��e�������q�U�������A���}�����������AdHvA(de-Haas van Alphen)�����̌��ʂ���T�ˊm���߂��AMgB2�̓d�q�i�q���ݍ�p�܂蒴�`���@�\�̎���������Ă���̂��A���o���h��B���f�̖ʓ��t�H�m�����[�h�ł��邱�Ƃ������I�Ɋm������܂����B
6. MgB2�̗ՊE���x����̉\���Ǝ��ӐV���`�������T��
�@MgB2�̔����ȍ~�A�V�����J���̊ϓ_����ł����ڂ��W�߂��̂́AMgB2���X�R�̈�p�ł���̂��A����Ƃ��ɂ߂ē���Ȉ��ł���̂��Ƃ����_�ł��傤�B���`�������̗��j��R�����Ă݂�ƁAA15�^���`���̂⓺�_�������`���̂����̎���̒��ڂ��W�߁A���͓I�Ɍ������s��ꂽ�w�i�ɂ́A�������Tc�̍������v���̈�Ƃ��ċ������܂����A�֘A�����ގ����������X�Ɣ�������Ă䂭���ŁA��A�̕����Q�ɂ��n���I�Ȍ������\�ł��������Ƃ������d�v�ȗv�f�ł��������߂ł��傤�B���l�ɁAMgB2���n�߂Ƃ���AlB2�^�̕����Q�ɑ��Ă��A�����Q�Ƃ��Ă̌n���I�ȗ������w�j�Ƃ������������߂��܂����B
�@
�Â�����AlB2�^�̕����Q�̌������s���Ă������Ƃ́A��ɂ��q�ׂ܂������A�ŋ߂ł́A�֘A�����Ƃ��āABeB2, ZrB2(Tc=5.5 K), TaB2(Tc=9.5 K), NbB2�̒��`��������܂����BBeB2�Ɋւ��ẮABeB2.75�Ƃ���AlB2�^�������G�Ȍ����\�����Ƃ镨����Tc=0.72 K(10B�ւ̒u���ɂ����Tc=0.79 K�ɏ㏸)�������ABeB2�͒��`���������Ȃ��ƕ���܂����BTaB2�Ɋւ��ẮATc=9.5 K�Ƃ���������܂������A����ł�4.4K�܂ł̉��x�̈�ł͒��`���͎����Ȃ��Ƃ���������A�^�U�Ɋւ��Ă͒肩�ł͂���܂���BZrB2�Ɋւ��ẮA���ꂽTc��������f������(ZrB12: Tc=5.9 K)��Tc�ɔ��ɋ߂��A�������Ɏ�ł͂���܂������̕s���������m�F����Ă���Ƃ������_���c����Ă��܂��BNbB2�Ɋւ��ẮA���������̈Ⴂ������\�����f���萫��(1:2)���炸��邱�Ƃɂ����Tc���ω�����(0.62�`9.2 K)�ƕ���Ă������ŁA���`���������Ȃ��Ƃ���������A���̌����ɂ��Ă͖��������ɂ͎����Ă��܂���B���݁A�g����ƌ����\���Ƃ̊W����̃A�v���[�`�����݂��Ă��܂��B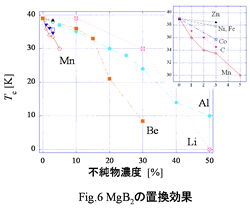
�@
����ɁAMgB2�̃L�����A�̓z�[��(���E)�ł��邱�Ƃ���A�z�[���h�[�v�ɂ���ėL���L�����A�������������Tc�̏㏸�����҂ł���̂ŁA�����̃O���[�v�ɂ���đ����f�u�������݂��܂����BFig.6�ɁA����܂łɕ��ꂽ�u�����ʂ̌��ʂ������܂��B�܂��AMg�T�C�g�ւ̑����f�u���́ALi, Mn, Al���Ɋւ�����Ȃ���Ă���A������̕ɂ����Ă�Tc�̏㏸�͊ϑ����ꂸ�A�����f�u���ɂ��Tc�̗}���Ƃ������ʂɂȂ�܂����B�������AZn��3%�u�������n�ɂ����āATc����0.2 K�㏸�����Ƃ���������܂������A��r�ɗp�����u������Ă��Ȃ�MgB2��Tc����Ⴂ(~38 K)���߁A����̍X�Ȃ錟���K�v�ł��傤�B�܂��A���̑J�ڋ�����u������������܂����A������Tc�̏㏸�͊ϑ�����Ă��܂���B����AB�T�C�g�ւ̒u���́AC, Be�Ɋւ�����Ȃ���Ă���A�����̌��f�̒u���ɂ���Ă��ATc�̒ቺ������Ă��܂��B�L�����A���z�[���ł���Ƃ����ϓ_����A�����f�u���ɂ���ēd�q��Ԗ��x���㏸�����邱�Ƃ��ł��܂����A���o���h�̃L�����A�����������Ă��܂���Tc�͗}������Ă��܂����߁A�ŗn�n�ō����ɐ������Ă��鑼���f�u���́A���̓_�Ō�����Tc�̏㏸�Ɏ��s���Ă���Ƃ����܂��B
�@Tc�㏸�ւ̕ʂ̃A�v���[�`�Ƃ��āA���͌��ʂ̎�������i�q�̎��k�ɔ�����Tc�̗}�������ꂽ���Ƃ◝�_�v�Z�̌��ʓ����āA�i�q��ϋɓI�ɍL���邱�Ƃ���j�Ƃ����������A�����琬�Z�p�𗘗p���čs���܂����B�Y���]�f(SiC)��T�t�@�C�A(Al2O3)���Ɋi�q���L������MgB2���琬���A����ɖ����𐧌䂷�邱�Ƃɂ���āA41.8 K�ɂ܂�Tc���㏸�����ƕ���܂����B����ɁA��ꌴ���v�Z�ƃ��}�����������Ƃ̔�r����A����Tc�㏸��MgB2�ɓ������͂ɂ����E2g�t�H�m�����[�h�̃\�t�g�j���O�������N������邱�Ƃ������ł��邱�Ƃ�����܂����B�܂��AC�u�������̎����Ȃǂ���AE2g�t�H�m�����[�h�̃n�[�h�j���O�ɂ����Tc�̗}���������N������邱�Ƃ��킩���Ă��邽�߁A���i�q���g�������邱�Ƃ��o����A�X�Ȃ�Tc�㏸�̉\�������҂��邱�Ƃ��o���܂��B
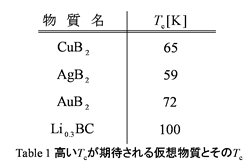
�@
���_�v�Z����́A���ɃA���J���y�ދ���(Na, Li, Ca��)��u�������ꍇ�ɁA����Tc����������Ƃ����\��������Ă��܂����A���ۂɂ̓A���J���y�ދ������g�p���������͔��ɍ���ł���A�ŗn�n���������ɓ����ɂ����ɂ���܂��B�܂��A�ŗn�n�ȊO�ɂ��֘A�����Ƃ���AuB2, AgB2, CuB2, LixBC(x~0.5)�Ƃ����������ō���Tc����������ł��낤�Ƃ����A���ɖ��͓I�ȗ\�z������Ă��܂�(Table 1)�B���������ł�����Ƃ������Ҋ��͂܂��c����Ă͂��܂����A�����̕����Ƃ��č������ꂽ�͂���܂���(LixBC�͏������ATc�͊ϑ�����Ă��܂���)�B
�@
�������A�y���f�̍������g���Ƌ�����������o���h���������ɒ��ڂ����H���ł̕����J���ɂ́A�\���Ӗ�������ƍl�����܂��B���̂悤�Ȋϓ_����A�������̌����O���[�v�́A�y���f(B��C)���܂ޕ����Q�̒��ɂ͖��������[�������������Ă���\���������ƍl���A�V�����J�����s���Ă��܂����B���̉ߒ��ɂ����āAY2C3��Tc=18K�Ƃ��������ԉ������Ƃ��Ă͔�r�I�������x�Œ��`�����������Ƃ����܂����B
�@�\�z�O�ɍ���Tc��������MgB2�̏o���ɂ���āA�uBCS�̕ǁv�Ƃ����T�O�����ł�����̂͊m���ł��B�����̃p�����[�^�Ɋւ��Č����I�ȏ������l�����ꍇ�ɂ́ABCS���`���@�\�ɂ�� Tc�̏�������݂���͂��ł����A���̏��������E�����ꍇ�ɂ́ATc�͂��̏�����z���邱�Ƃ��o����͂��ł��BMgB2�͐��ɂ��̈��ƂȂ����ƌ����܂��B�������AAlB2�^�\���̘Z������z�E�����Ƃ����J�e�S���[�̒��ł́A���̕������������قȑ��݂Ȃ̂��낤�Ƃ����l������ʓI�ł��BMgB2�́A���o���h�ɃL�����A�����݂��A����Tc�����邽�߂ɕK�v�Ȍ��w�t�H�m���Ƃ̋����������\�ƂȂ��Ă���A���ɐ▭�ȃo�����X�̏�ɐ��藧���Ă��钴�`���Ȃ̂ł��傤�B
�@���̂悤�Ȋϓ_���猩��ƁA�މ������Ƃ͕ʂ̕����ł̖͍����K�v�ł���AY2C3�Ƃ����y���f���܂����ɂ������r�I����Tc�����V�������`���̂̔����́A���̂悤�Ȍy���f���܂ޕ����Q�ɂ����āA������������Ă��Ȃ����͓I�ȕ������������݂���Ƃ��������ł���悤�Ɏv���܂��B�y���f(B��C)���܂މ������������̖����܂����Q�ł���A�����̕��X������������Ă���������K���ł��B