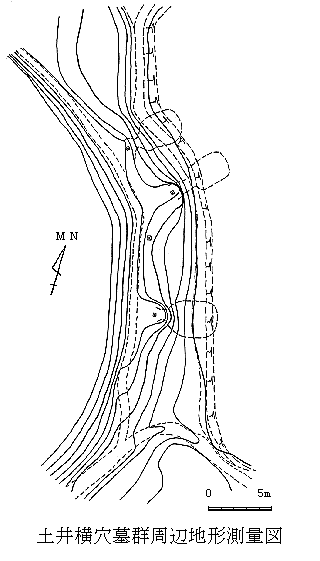 略測を行った土井横穴墓群は土井地区に所在しており、3基の横穴が谷部に開口部を向け、南北に並列してほぼ完存状態で存在している。
略測を行った土井横穴墓群は土井地区に所在しており、3基の横穴が谷部に開口部を向け、南北に並列してほぼ完存状態で存在している。
1990年度から当研究室において実施している「定プロジェクト」の一環として、昨年度調査から「定環境プロジェクト」を開始し、今年度発掘調査においてもこれを並行して実施した。
このプロジェクトは定地区を中心とした北房町の資源、生産、交通、流通、歴史などを、考古学的事象やそれ以外の多方面から分析し、包括的地域研究を行うことを目的としている。具体的には、これまでの「定プロジェクト」の成果から明らかになった本地域の古墳時代終末期首長系列の状況と、周囲の横穴式石室を有する古墳・横穴墓との関係や、古墳時代全般あるいは歴史時代の北房町の果たした地域・地縁機能を解明するための基礎資料収集がその主な作業となった。そのため昨年度調査から定東塚・西塚古墳の周辺地域の分布調査を実施している。
昨年度は大塚古墳の横穴式石室実測図製作、下村古墳写真撮影、中津井の清常、才田、定、平田、藤田地区を中心とした実地踏査などを実施し、今年度の環境プロジェクトは昨年度調査を引き継いだ形で実施した。主に、昨年度プロジェクトで分布調査を行わなかった土井地区の分布調査と、さらにその際に確認された土井横穴墓群の略測図・周辺地形測量図(左図)の製作を行った。
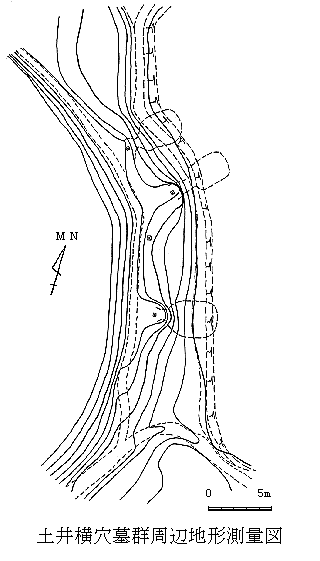 略測を行った土井横穴墓群は土井地区に所在しており、3基の横穴が谷部に開口部を向け、南北に並列してほぼ完存状態で存在している。
略測を行った土井横穴墓群は土井地区に所在しており、3基の横穴が谷部に開口部を向け、南北に並列してほぼ完存状態で存在している。
土井1号横穴墓は西南西に向かって開口している。横穴の規模は最大長約4.5m、最大幅約3.2m、最大高約1.2mを測る。平面形は隅丸長方形で、断面形はドーム状を呈している。開口部側から奥壁側にかけて流土の堆積が著しく、略測平面図はこの流土の傾斜に従って計測している。奥壁に向かって右側の側壁が左側の側壁と比較して若干張り出したような平面形で、片袖を意識したようである。
土井2号横穴墓は南西に向かって開口している。横穴の規模は玄室最大長約3.1m、玄室最大幅約2.3m、玄室最大高約1.4m、羨道最大長約1.0m、羨道最大幅約0.9m、羨道最大高約1.1mを測る。平面形は隅丸長方形で、断面形はドーム状を呈している。流土の堆積はさほど著しくなく、玄室・羨道ともに横穴床面が流土の1〜2cm下位に確認される。袖部はほぼ左右対称形を呈している。開口部からさらに外側に前庭部の存在が考えられるが、今年度調査では確認していない。開口部には段を形成した掘り込みが確認され、扉石等の閉塞施設の可能性が考えられる。
土井3号横穴墓は南西に向かって開口している。横穴の規模は最大長約4.0m、最大幅約2.8m、最大高約0.9mを測る。平面形は隅丸長方形で、断面形はドーム状を呈している。開口部側から奥壁にかけて流土の堆積が著しく、略測平面図はこの流土の傾斜に従って計測している。奥壁に向かって左側の側壁が右側の側壁と比較して若干張り出したような平面形で、片袖を意識したようである。
以上のように、これら3基の横穴墓は非常に類似した構造的特徴を有し、さらに2号横穴墓を中心とした横穴墓群全体の平面形の特徴(1号および3号の片袖形態)についても考えれば、これら3基の横穴墓は親密な関係のもとで営まれたと考えられよう。
次に、土井地区の分布調査であるが、今年度は土井地区の山塊を中心に昨年度未踏査であった地域について実地踏査を行っており、その際土井横穴墓群以外に3基の横穴墓、土井1号墳、土井3号墳、土井4号墳、貝原1号墳、貝原2号墳などを確認・記録している。
同時に、下村1号墳を中心とした下村山塊についても実地踏査を行っている。その際、昨年度分布調査で確認した下村横穴墓の略測を行っている。下村横穴墓は南西方向に開口し谷部に向かっている。横穴の規模は最大長約2.9m、最大幅約2.7m、最大高約0.9mを測る。流土の堆積が著しくはっきりとはしないが、平面形は隅丸長方形であると考えられる。奥壁に向かって右側壁が張り出しており、断面形は左右非対称のドーム状を呈している。また、その周辺で2基の横穴墓と、採石場遺構、2基の経塚を確認・記録している。
岡山大学文学部考古学研究室copyright,1997
制作者:佐々田