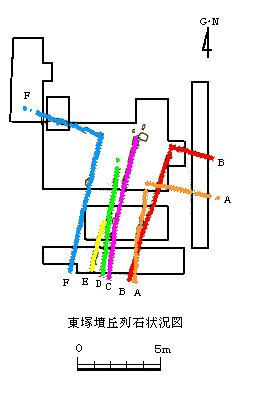 東塚墳丘では、昨年度調査した西Aトレンチの旧称第2列石の直下から検出した列石が他の列石とどのような関係をもつのかを確認するため、西Aトレンチの北に0.5m残して南北2m、東西5mの発掘区を設け、さらに土層観察のために西Aトレンチを再設定して調査を行った。
東塚墳丘では、昨年度調査した西Aトレンチの旧称第2列石の直下から検出した列石が他の列石とどのような関係をもつのかを確認するため、西Aトレンチの北に0.5m残して南北2m、東西5mの発掘区を設け、さらに土層観察のために西Aトレンチを再設定して調査を行った。
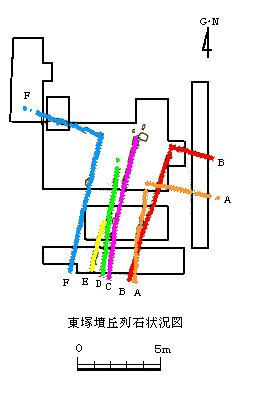 東塚墳丘では、昨年度調査した西Aトレンチの旧称第2列石の直下から検出した列石が他の列石とどのような関係をもつのかを確認するため、西Aトレンチの北に0.5m残して南北2m、東西5mの発掘区を設け、さらに土層観察のために西Aトレンチを再設定して調査を行った。
東塚墳丘では、昨年度調査した西Aトレンチの旧称第2列石の直下から検出した列石が他の列石とどのような関係をもつのかを確認するため、西Aトレンチの北に0.5m残して南北2m、東西5mの発掘区を設け、さらに土層観察のために西Aトレンチを再設定して調査を行った。
昨年度の調査で西Aトレンチ第2列石の直下から検出した列石(以下、旧称下列石)の存在によって、東塚墳丘全体の列石の巡り方について、従来の解釈の再検討が必要になった。そこで、墳丘全体の各列石の立面図、平面図および石材構成の検討によって今回の調査を前にある程度の想定を行った。
その結果、今回の調査を通して、西Aトレンチの旧称下列石・北西トレンチの第2列石と一連のものと考えられる列石(右図中B【以下同じ】・東塚第2列石)、西Aトレンチの旧称第1列石・北西トレンチの旧称第1次修築列石(C・東塚第1次修築第1列石)、西Aトレンチの旧称第1次修築列石・北西トレンチの第2次修築列石と一連のものと考えられる列石(D・東塚第2次修築列石)を確認した。また、西Aトレンチの旧称第2列石とつながる列石(A・東塚第1次修築第2列石)、西Aトレンチの旧称第2次修築列石とつながる列石(E・東塚第3次修築列石)も確認している。
これらのことより、従来東塚築造当初の列石および、墳丘上面と考えられていたものは、1回目の修築に伴うものであることがわかった。その結果、従来2回と考えられていた修築の回数は3回となることが明らかになった。
なお、土層の観察によって、東塚築造当初の墳丘上面は、1回目の修築以前に崩れたか、あるいは修築を施した際に削平された可能性があり確認出来なかったものの、2回目の修築は西塚築造とほぼ同時期であること、3回目の修築は一部崩壊した2回目の修築列石の基底の石を再利用して行っていたことも今回の調査で確認している。
岡山大学文学部考古学研究室copyright,1997
制作者:寺村