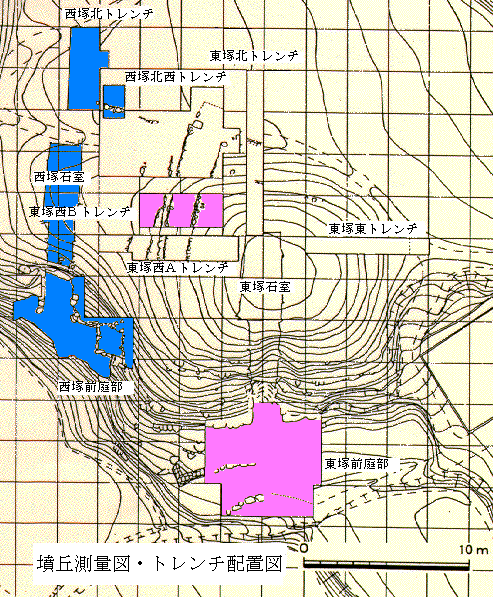 今回の調査は定東塚古墳では、墳丘と前庭部にトレンチを設け、列石や墳丘の構築過程について検討した。一方定西塚古墳では、墳丘と前庭部、石室において調査を行い、未解明であった列石や墳丘の構造等について検討した。
今回の調査は定東塚古墳では、墳丘と前庭部にトレンチを設け、列石や墳丘の構築過程について検討した。一方定西塚古墳では、墳丘と前庭部、石室において調査を行い、未解明であった列石や墳丘の構造等について検討した。
第4次調査は1997年3月1日から4月1日までの期間、岡山大学考古学研究室の1年生から3年生までのほぼ全員と4年生の一部、および大学院生と九州大学学生1名、島根大学学生1名が参加して行われた。
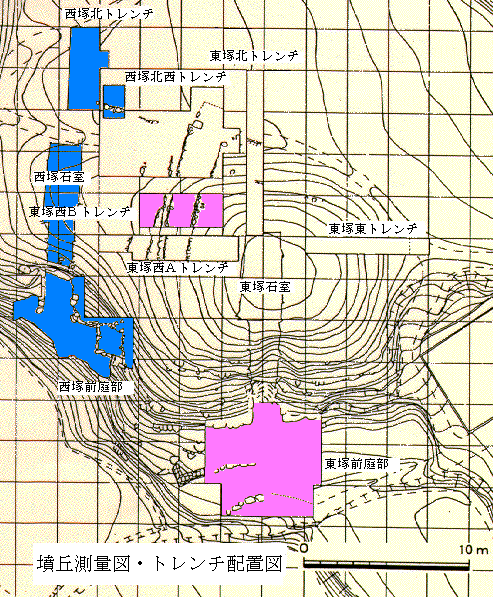 今回の調査は定東塚古墳では、墳丘と前庭部にトレンチを設け、列石や墳丘の構築過程について検討した。一方定西塚古墳では、墳丘と前庭部、石室において調査を行い、未解明であった列石や墳丘の構造等について検討した。
今回の調査は定東塚古墳では、墳丘と前庭部にトレンチを設け、列石や墳丘の構築過程について検討した。一方定西塚古墳では、墳丘と前庭部、石室において調査を行い、未解明であった列石や墳丘の構造等について検討した。
東塚の墳丘に関しては、東塚西Bトレンチにおいて調査を行った。このトレンチは、既に発掘調査を行った西Aトレンチの北にベルトを残して設定したものである。調査の過程において、列石の修築が3回行われていたことが判明した。また、昨年の調査で西Aトレンチで検出された旧称第2列石下の列石もトレンチ北側で確認し、それが北西トレンチの第2列石に連なるものである可能性が強まった。
東塚前庭部では、石室主軸に沿って断ち割りを入れた結果、旧表土上に赤色変成岩を用いた造成土を敷いて列石や石室開口部付近の側壁を構築していた状況が明らかとなった。また、前庭部の土層と東塚石室内の土層の対応関係と石室床面について調べるために、2次調査で石室主軸沿いに入れた断ち割りの再検討も行っている。
西塚墳丘に関しては、西塚北トレンチにおいて調査を行った。調査の初期段階では当初予想されていた西塚列石が検出されなかったため、トレンチ東側にベルトを残して北トレンチ拡張区を設定し、北トレンチと並行して調査を進めた。こうした過程の中で、東塚北西トレンチ・西Aトレンチで確認されていた西塚列石が検出され、西塚の北側の墳端が確認された。また、西塚列石の構築過程も明らかとなり、トレンチ南側においては西塚石室の奥壁を設置する際の裏ごめの土と作業面についても確認した。
西塚前庭部では、前庭部の東半部と東半部の拡張区において調査を行い、新たに2列の列石と初葬の床面を確認した。この2列の列石の性格については今後の検討を要するものである。また、東半部に先行トレンチを設定し、古墳築造時の前庭部の構築過程を明らかにした。
西塚石室では、方頭大刀をはじめ、今年も鉄鏃、鉄釘、須恵器等多数の遺物を出土した。3月17日、18日、20日には陶棺6基の搬出作業を行った。その後に石室床面の断ち割りと石室実測を行い、それらの作業を完成させている。
これらの発掘調査と並行して、3月3日、21日、22日、27日、28日、30日の6日間、土井地域を中心に分布調査を行った。これは、「定環境プロジェクト」の一環を成すものであるが、その際土井横穴墓群をはじめ数基の古墳・横穴墓等を発見し、土井横穴墓群に関しては略測と周辺地形の測量を行った。
3月23日には現地説明会を開催し、約160名の参加者を得ている。
なお、昨年度まで調査を行った旧称東塚西トレンチの名称を「東塚西Aトレンチ」とし、今年度東塚西Aトレンチの北にベルトを残して設定したトレンチを「東塚西Bトレンチ」とする。また、東塚墳丘における列石名称について、東塚西Bトレンチの調査の結果、昨年度調査までに東塚墳丘の各トレンチで検出された列石相互の対応関係がほぼ確定されたことにより、東塚北トレンチ、東塚北西トレンチ、東塚西Aトレンチにおける昨年度調査までの列石名称の一部が変更されることとなった(次項表)。文章の便宜上昨年度調査までの列石名称を用いる場合には、列石名の頭に「旧称」と記している。本概報で用いる古墳の正式名称は「定東塚・西塚古墳」とし、「東塚」、「西塚」等は全て略称である。
<東塚北トレンチ>
東塚第3列石 ⇒東塚第1次修築第2列石
<東塚北西トレンチ>
東塚第1次修築列石 ⇒東塚第1次修築第1列石
<東塚西Aトレンチ>
東塚第1列石 ⇒東塚第1次修築第1列石
東塚第2列石 ⇒東塚第1次修築第2列石
東塚第1次修築列石 ⇒東塚第2次修築列石
東塚第2次修築列石 ⇒東塚第3次修築列石
東塚第2列石直下の列石⇒東塚第2列石
岡山大学文学部考古学研究室copyright,1997
制作者:寺村