

「岡山の飛込み出産」 調査結果 |
||
| 第24回 岡山県母性衛生学会 シンポジウム「どうする?岡山のお産」 2007年12月8日(土) 岡山大学医学部保健学科棟3階 301大講義室 ポスター 山陽新聞2007年12月9日版 |
分娩施設のない地域の 妊産婦の不安に関する アンケート2007 山陽新聞 2008年1月24日 |
|
助産実習にご協力を! |
![]() 助産関連のNews
助産関連のNews ![]() 2006年8月25日(1)
2006年8月25日(1)
![]() 2006年8月25日(2)
2006年8月25日(2)
![]() 2006年8月25日(3)
2006年8月25日(3)

最近になって,急に注目され始めた産科医・助産師の不足に伴う「分娩過疎地帯」の拡大は国内外でも極めて重要な社会問題となって来ており,2006年になり厚生労働省も緊急の対策を具体化させようとしている.これは,以前より,確実にこのような状況になることは周産期医療の現場では周知のことであったこともあり,遅すぎる対応だが,期待をせざるを得ない状況である.
2006年報告された日本産婦人科医会の助産師充足状況の緊急調査では,全国の分娩取り扱い施設における助産師の充足率は,診療所では僅か40.6%に留まり,病院でも84.7%と低迷しており,助産師不足は大きな社会問題となっている.
この調査で,全国では,現時点で6,718名もの助産師が不足していることが明らかになっている.
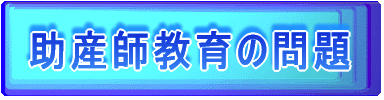
近い将来,看護基礎教育が4年間以上に延長されると考えられる.このため,助産師教育を4年制大学在籍中に行うことは不可能となり,4年制大学卒業後,看護師免許を取得し,その後に助産師教育を受ける必要が出てくると考えられる.この助産師養成課程に関しては,1年の専攻科,2年の大学院修士課程などが考えられる.しかし,いずれにしても,助産師として,十分に職務を果たすようになるためには,在学中の助産実習から卒後研修へと重点をシフトしていく必要があると考えられる.

医療事故の顕在化とともに,医療スタッフの質が問われる時代となっている.また,新卒看護職員の離職の背景として,基礎教育と看護現場で求められる能力のギャップが指摘されており,現状に見合った教育年限の必要性が強調されている.日本看護協会の調査結果によると,基礎教育の臨地実習で新卒看護職員の多くが「与薬技術」や「生体機能管理技術」などを経験しておらず,仕事を続けていく上で「配属部署の専門的な知識・技術不足」や「医療事故を起こさないか不安」,「基本的な看護技術が身に付いていない」などの悩みを抱えているという.
日本看護協会は,看護基礎教育の改革に向け,2006年5月の通常総会で「看護師の基礎教育制度の改正に向けた活動方針(案)」を承認した.この中では看護基礎教育の年限を4年以上に延長することとしている.近年,医師と歯科医師で臨床研修が義務化され,薬剤師と歯科衛生士で基礎教育年限が延長されたが,看護基礎教育の教育年限は60年近く変化がない.しかし,これは,看護師養成3年課程(大学,短大,養成所)に関する方針であり,保健師養成課程,助産師養成課程,看護師養成2年課程等は,この方針との整合性も考慮してさらに検討する.また,卒後研修の制度化促進に関しても,引き続き活動を継続している.なお,看護師の養成数は1学年定員5万2,471人(2005年4月現在)であり,3年課程が3万5,129人(67%)を占める.
日本看護協会は,看護師の基礎教育の年限を4年以上にすることを盛り込んだ要望書を川崎二郎厚生労働相や松谷有希雄厚生労働省医政局長,小坂憲次文部科学相ら2006年6月提出した.
厚生労働省は2006年3月,「看護基礎教育の充実に関する検討会」(座長=遠藤久夫・学習院大教授)の初会合を開き,看護師や保健師,助産師教育のカリキュラム見直しや基礎教育期間の延長など,健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正に向けた検討を始めている.(参考:医学書院/医学界新聞【日本看護協会プレス懇談会】,第2688号 2006年6月26日)
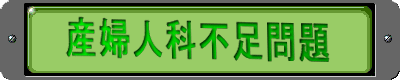
全国110の大学病院とその関連病院を対象に,2003年4月と2005年7月の時点でのデータを比較した日本産科婦人科学会の検討委員会(委員長=吉川裕之・筑波大教授)の調査では,5,151人だった常勤医は4,739人まで減少,全国の大学病院やその関連病院に勤務している産婦人科の常勤医が2年余りの間に412人(8.0%)減少している実態が明らかになった.また,分娩を取り扱う関連病院の数も1,009施設から95施設(9・4%)減少し,914施設になっていた.「読売新聞」(2006年4月24日)
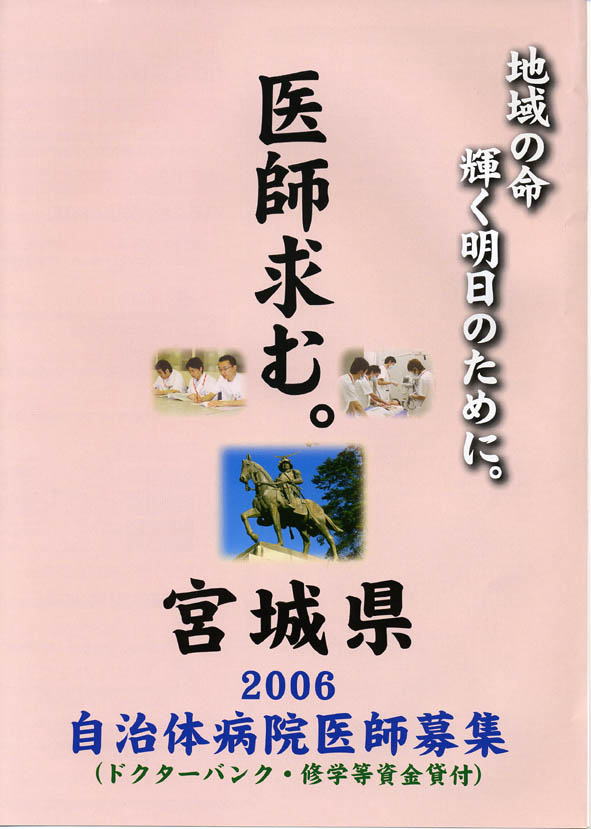 産婦人科の学会で,こんなパンフレットが配られていた.
産婦人科の学会で,こんなパンフレットが配られていた.