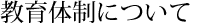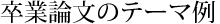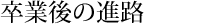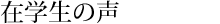入学後1年間は基礎科目などの履修を通じて考古学を含む入門的な内容を学び、2年次から歴史文化学専修コースの配属となって考古学の分野で専門的な知識や技術を身につけていきます。2年次にはとくに「考古学実習」が重要であり、前期は石器や土器などの観察や実測、後期には遺跡の測量や実測を学びます。3年次になると、自分が選んだ課題についてレポートを作成するための研究を積み重ねていきます。4年次では卒業論文のテーマを決定し、「歴史文化学課題演習」で研究の成果を発表していきます。また、英語の力をアップさせるため、2年次と3年次に考古学の文献読解などを中心とする科目の履修を薦めています。
授業科目とは別に、考古学では夏や春に発掘調査を実施しており、整理作業にも参加することを通じ実践的な研究の方法を身につけていきます。発掘調査は、チームワーク力やコミュニケーション能力、忍耐力などをアップさせる絶好の機会となります。
考古学の学生の多くは学芸員の資格を取得するために学芸員課程の科目を履修します。さらに教員免許を取得する学生もいます。


- 旧石器・縄文時代移行期の礫群と集石―南九州を中心として―
- 中国地方における縄文時代早期の遺跡動態
- 縄文時代後・晩期の関東地方における土偶の変遷と諸相
- 縄文時代墓制の展開―近畿地方を中心に―
- 遺跡における被抜歯遺骨の分布傾向
- 弥生時代の器台形土器における地域性―吉備地域を中心に―
- 弥生時代の鳥形木製品について
- 弥生時代の狩猟相―西日本を中心に―
- 弥生・古墳時代における琴の展開
- 四隅突出型墳丘墓から見る山陰弥生社会
- 古墳時代の首飾り
- 古墳時代の甲冑と甲冑形埴輪
- 古墳時代西日本における鍛冶の様相
- 鹿角製・木製刀剣装具の編年とその意義―把装具を中心として―
- 横穴式石室における棺の諸相―棺の配置と組み合わせからの考察―
- 吉備地方における群集墳の様相
考古学研究室の卒業生は、考古学を生かした仕事の他、公務員や一般企業など、さまざまな仕事に就いています。大学院に進学して、さらに専門的な知識や技能を深める人もいます。下記は就職先の例です。
- 岡山県古代吉備文化財センター|
- 島根県教育庁文化財センター|
- 三重県埋蔵文化財センター|
- 山口県埋蔵文化財センター|
- 川西市教育委員会|
- 高梁市教育委員会|
- 愛媛県教育委員会|
- 岡山市役所|
- 旭川市役所|
- 今治市役所|
- 鎌倉市役所|
- 岡山大学職員|
- 日本赤十字社|
- 岡山県警察|
- NTT西日本|
- 日本郵便|
- 三浦工業株式会社|
- 椿本チェーン|
- ZAGZAG|

文字もない時代に生きていた人々の証に直接触れられるのは考古学くらい
私は夏にある発掘で隊長を務めました。夏発掘は10日間程度の短いものですが、2回生も本格的に参加するはじめの発掘です。私の担当した年は、鳥取県の井後草里遺跡でした。宿舎を借りてとまることになるのでいろいろ大変なことはありますが、少人数で一緒に生活するので回生を越えた会話の機会が得られます。また、春の発掘では当番制でご飯を作ったりするので生活面でのスキルも磨けます。
発掘をしていれば、縄文時代や弥生時代などの遺物に遭遇するわけですが、自分たちが生きている時代よりはるか昔、文字もない時代に生きていた人々の証に直接触れられるのは考古学くらいではないでしょうか。土器に残った指の跡に自分の手が重なる瞬間などは、文献研究だけでは感じることのできないリアルな体験だと思います。私はそこに考古学の一番の魅力があると思います。
一生の思い出に残る体験をすることができる
現地調査中には、地元の方や考古学ファンの方が見学に来られます。岡山は遺跡が豊富なので、考古学に興味のある方が多いのかもしれません。現地調査中のさまざまな人との出会いは、私のもっとも楽しい思い出のひとつとなっています。考古学研究室では、一生の思い出に残る体験をすることができると思います。