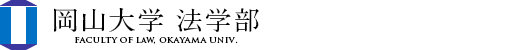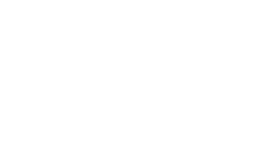ホーム > 就職・資格情報 > インターンシップ > バックナンバー > 2004年度 インターンシップ 岡山大学法学部生の就業体験実習
2004年度 インターンシップ 岡山大学法学部生の就業体験実習
岡山大学法学部におけるインターンシップについて
岡山大学法学部では,2000年よりインターンシップ(就業体験実習)を行っています。
岡山大学法学部では,2000年よりインターンシップ(就業体験実習)を行っています。
インターンシップは,在学中に一定期間,民間企業や行政官庁,法律事務所などの職場で実際に業務を体験することにより, 大学で法律学・政治学を学ぶことの意味を実践を通じて理解し,また将来的には自らに適した進路を選択する力を皆さんにつけてもらうことを目的としたカリキュラムです。
対象は原則として3年次生(場合によっては4年次生も可)で,夏季休業中の2週間に実習を行います。

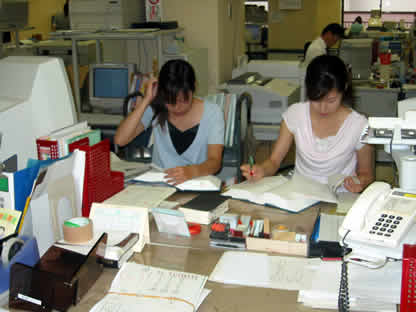

法務省岡山地方法務局でのインターンシップ実習風景
インターンシップ報告会
2004年 12月1日,インターンシップ報告会が開催されました。5年目を迎える今年は,山陽新聞社,瀬戸内海放送,OHK,岡山ネットワーク(オニビジョン),NTT西日本,ピュアリティまきび,法務省岡山地方法務局,岡山県庁,岡山市役所,法律事務所,司法書士事務所,税理士事務所の23の受入機関のご協力の下,37名の学生が就業体験をすることができました。報告会では,谷法学部長の挨拶,学生委員会委員からの概要説明の後,今年度の履修学生の代表10名が,各受入先でのインターンシップの体験を報告しました。それぞれにとても貴重な経験をしてきたこと,そして彼等がその中で成長したことが実感できました。また,下級生に対してはしっかりした目的意識を持ってインターンシップへ臨んでほしいとのアドバイスが印象に残りました。













インターンシップ報告書
岡山放送株式会社( OHK )
法学部4年 岸村 由紀子
私はOHKの報道部に、8月2日から13日までの2週間にわたってお世話になりました。報道部では取材活動やスポーツ中継に同行させて頂いた他、編集作業やデスク業務など実に様々なことを経験しました。報道の裏側、例えば、日頃私たちがさらりと聞き流している1分間のニュースでも様々なスタッフの努力と苦労があって出来上がっているということなどを自分で体験でき、改めてテレビというマスメディアを身近に感じました。また、ニュース番組においては映像を見るより文章を聞くほうに重点を置くようになり、番組作成の裏側を想像しながら今までとは違った視点からテレビを楽しんでいます。
私の自宅は姫路で近畿地区に入るためOHKの番組は映らないので、今回のインターンシップにあたりインターネットでOHKのホームページをチェックしたり、岡山在住で実際にOHKの番組を見ている友人に話を聞くなど、事前にOHKに関する知識を身に付けて臨みました。
私は、初日から取材活動に同行させて頂き、自分でも原稿を書いてみる作業に取り組みました。毎日違う記者やカメラマンに同行し数々の取材をさせて頂きましたが、地域性や季節の話題と少しずつ取材方法が違い、新しい発見の連続でした。取材活動では、後々ニュースに仕上げるときに文章と映像が符合するように記者とカメラマンとの事前の打ち合わせが非常に重要であるということを学びました。原稿作成では、1分という短時間で「これはどんなニュースなのか、何がトピックスなのか」を視聴者に分かりやすく正確に伝えるために、取材内容の取捨選択が非常に大切になってきます。時間の流れの中で一度しか聞くことの出来ない視聴者(老若男女)のことを常に念頭において、難解な言葉は言い換える、耳慣れないものには補足をつけるなど注意しながら原稿を書き上げる作業は簡単に見えて予想以上に難しいことでした。しかし、ご指導のお陰でポイントを押さえた原稿が書けるようになりました。また実務以外でも学ぶところが多く、報道スタッフの方々とお話する機会を通して、皆さんが日々視聴者のために鋭意努力していらっしゃることが伝わってきました。日常生活の中で何事にも好奇心を持つことや意外性を探し出す姿勢が報道の基本であると言われ、大きな魅力を感じました。
私が今回のインターンシップで一番大きな収穫だったと思うことは、対人関係の難しさ、礼儀、健康管理等、社会人としての常識を再確認できたことです。2週間と短期間ではありましたが、ここで得た知識と経験は今後の私生活や残り半年の大学生活においても生かしていきたいと思います。後輩の皆さんにも積極的にインターンシップに参加することをお勧めします。
最後になりましたが、このような機会を与えてくださったインターンシップ選考委員会の先生方、私を実習生として受け入れて下さったOHK様、お忙しい中貴重な時間を割いてご指導下さった報道部他関係者各位の方々に感謝すると共に心より御礼申し上げます。
菊池綜合法律事所
法学部4年 佐伯 菜緒
私はインターンシップで、裁判記録、法律相談、先生同士の打ち合わせへの同席、講演会への参加など様々な経験をさせていただき、大変貴重な体験をすることができました。
特にインターンシップ期間中、様々な裁判記録を読み、準備書面を作成する過程で弁護士の仕事には、法律だけでなく、様々な分野の専門知識と丁寧な書面作成が不可欠であることを学びました。
私が準備書面を考えた事件の依頼人は、お稽古の先生から受けたセクハラ行為のため、外傷後ストレス障害(PTSD)になり、日常生活ができなくなっていました。しかし被告は自分と被害者のPTSD症状にはなんの関係もないと主張していました。私はまず双方の証拠資料、これまでの裁判資料を読み、事案を把握しました。そして最終的な争点は、被告の行為と依頼人のPTSD症状との因果関係の有無になるということから、因果関係を立証していきました。その過程でまず私がしなければならなかったことは、様々な専門書を読んで、PTSDについて理解することでした。PTSDについての知識がなければ、被告の主張を崩すことはできませんでした。弁護士は、法律のみに精通していればよいと思っていた私にとって、これは衝撃でした。私は最終日まで暇があれば記録を読み、専門書を読み、先生と話をし、準備書面を練りました。
またある日は、宝石店店員から「このオパールには資産価値があります」と言われ資産価値があると思ってオパールを購入したが、なんの価値もないものだったという相談がありました。こちらから宝石店に訴え提起前の照会を行っており、私は宝石店からの反論を予想し、それにどう対応するか考えました。その際も私は法律書ではなく、何冊もの宝石図鑑にかじりついていました。そこでオパールの中には水分が多く含まれており、その水分がユラユラ揺れるところに価値があること、またその水分は抜けやすく、2年も経てばオパールの価値はなくなることなどを知りました。そうすると資産性があるという業者の対応は全くの嘘だし、仮に、資産性があるなど言ってないと言われても、消費者契約法4条「重用事実の不告知」にあたり、訴訟となってもこちらが負けることはないという結論に達することができました。
「一つ一つの事件に専門知識をもって、丁寧に挑まなければならない。弁護士はあらゆる分野の専門家でなければならない」と先生はおっしゃっていました。専門知識を持つことによってより力強く依頼人を守ることが出来るということを学びました。
私が因果関係の立証を体験したセクハラ訴訟では、被告がセクハラ行為をしたことは、証拠から明らかでした。そのため、弁護士によっては、因果関係立証の準備書面を「証拠より因果関係は明らかである」の一文で済ませる弁護士もいるだろうと、菊地先生はおっしゃっていました。しかし、「たとえどんなに勝つ可能性が高い事件でも、丁寧な立証をしなければならない。自分の依頼人を危険にさらすようなことがあってはならない。絶対に勝てる訴訟などないのだから。」とおっしゃっていたのが非常に印象的でした。
司法制度改革の過程で、これからどんどん弁護士の数は増えていきます。そのような中で市民に求められる弁護士とは、豊かな法律知識に加え、依頼人のために事件ごとに最大限の知識を習得し、丁寧に依頼人の権利を主張していく弁護士ではないかと思います。今回の実習でそんなこれからの社会に求められる弁護士の仕事を体験できたと思います。私は法科大学院を目指していますが、実務家となった際の、紛争解決に取り組む姿勢について学ぶことができました。
最後になりましたが、お世話になった菊池法律事務所の先生方、事務所の皆様、インターンシップ運営委員会の先生方に感謝します。ありがとうございました。
岡山県司法書士会
法学部4年 西原真弓
私は今回、インターンシップ実習生として児島司法書士事務所で研修を積ませて頂きました。二週間にわたる実習を前に私はまず、自分なりの目的と目標をそれぞれ明確にしておきました。自分が参加したインターンシップの意味を確認しておきたかったということと、実習前後の意識の違いをはっきり感じたいと思ったからです。これは途中、気を引き締め直すためにも役に立ちましたし、何より実習後の充実感を自分で計ることができる一つのよい資料となっています。
司法書士といえば通常登記が専門と考えられがちですが、その実態は、調停・裁判関係、多重債務整理、相続財産管理人そして成年後見人としての仕事等、非常に多岐にわたる仕事であり、そのほとんどの場面に同行させて頂いた毎日は驚きと発見の連続でした。中でも、新制度として始まって間もない成年後見制度には私も以前から興味があり、先生が積極的に活動されていることもあって、特に印象に強く残っています。後見人の役目は被後見人の財産管理―と言えば簡単ですが、実際には被後見人との面談のため病院、介護施設等をまわったり、被後見人宅の維持・管理のために連絡を取り合い、実際に足を運んで状況確認を行ったりと、その内容はあらゆる域に及びました。「いわゆる何でも屋ですよ。」これは、成年後見人としてある現場作業的な仕事をすることになったときに先生がおっしゃった言葉です。他人の財産を預かる、そのためにはそれだけの責任と労力、判断力の高さが要求される大変なものだということを実感しました。しかし一方で、高齢化社会が進み、今後さらに社会的弱者の増加が予想されることを考えると、司法書士が社会に貢献できる幅も広がるのではないかと、その可能性に魅力を感じました。実質10日という短い期間ではありましたが、事前に電話で依頼人の方と確認を入念に行い、事後の業務整理・報告まで欠かさない、そんな日常的な先生の姿からはどれだけ責任と信頼が重要とされる仕事かをうかがい知ることもできましたし、また時に医療・社会福祉関係の方々等多くの人々が提携し協力し合って取り組む場面もあり、司法書士としての業務だけでなく様々な職種の方々との接触から学ぶことも多く、大変有意義な研修となりました。
司法書士としてどんな風に人や社会と関わり合うことができ、社会的ニーズに応えていけるのか、その点を探りたかった私にとって、今回インターンシップに参加した意義は大変大きかったです。これからの勉強に大きな意欲を得ることができましたし、今学んでいることが実社会でどのように、どの場面で生きてくるのかを自分の目で確かめることにより、法律知識を身につける必要性もはっきりと認識することができました。そして当然のことながら、人間としての豊かさも求められることを強く実感し、これから自分が成長すべき点を見直す良い機会ともなりました。学生であるうちに一社会人としてこのような素晴らしい体験が出来たことを無駄にしないよう、今後の生活、学習への取り組みに是非生かしていこうと思います。
最後になりましたが、お忙しい中研修を受け入れてください、貴重な体験をさせてくださった児島先生、川口さん、本当にありがとうございました。そして、このような機会を設けてくださったインターンシップ実行委員会の先生方に、改めて深く感謝申し上げます。
NTT西日本岡山支店
法学部3年 臼杵 愛
私は、日常の机上の法律論ではなく、実際に企業で法律がどのように生かされているのか、またグループ会社を多く持つ大企業の体系を感じてみたいと思い、今回NTT西日本の就業体験に参加させて頂きました。文系の道をずっと進んできた私にとって、ケーブルや回線等といった専門用語は縁が無く、通信サービスを中心に業務を行っているNTTの企業活動について情報収集することから始めました。
二週間の実習のうちの半分は企業法務についての講義を受けました。企業を円滑に運営していく上では、独占禁止法、景品表示法、消費者契約法などの法律知識が不可欠であり、それらの法律が実務の面でいかに反映されているのかという事を、現実に起こった事例等を解答していくという形式で学んでいきました。ここでは、クーリング・オフや懸賞といった私たちの日常生活と密接に関係する法律関係を基に講義が行われ、過去に学んだ知識を活かして解決方法を検証しました。
また、今回の実習中に、幸運にもNTTが原告である料金滞納訴訟を見学しに行く機会に恵まれ、初めて簡易裁判所で行われる裁判上の和解というものを経験しました。前日までの講義の中で、訴状の書き方や支払督促の流れ等を教わっていたので、スムーズに訴訟の流れを理解することができました。司法の役割や、その機能を理解するためには、テキストを読んで記憶することだけではなく、実際に自分で訴状を書くなどの作業を行い、実務の面からそのシステムを身をもって覚えることが非常に重要であると感じました。
商品概要、お客様からの電話受付、設備見学・概要、インターネットの構築研修等、様々な分野における専門の方の指導を受けましたが、その中でも、ソリューション営業の部門で、「お客様に対してNTTの商品を提案する」というテーマのもと、プレゼンテーションを行ったことが大変印象に残りました。限られた時間の中で、どのようにNTTの商品をお客様にアピールするかを考えることは決して容易ではありませんでしたが、後に社員の方々から評価をしてもらい、提案ポイント、提案の態度等を教えて頂きました。そして、提案する上では、その提案内容を根拠付けるために様々な情報を収集し、相手方に理解をしてもらえるように話すことが不可欠であり、このプレゼンテーションは私が今後経験する就職活動に繋がる、大きな体験だったと思いました。
インターンシップは二週間という決められた期間でしたが、大学生活とは離れた職場という社会に身を置くことで、将来の進路を意識する良い契機になったと思います。今回、NTT西日本の社員の方々に教えて頂いた知識を活かして、あと一年余りの大学生活を有意義なものにしていこうと思います。
最後になりましたが、お忙しい中、未熟な私を快く受け入れて下さり、熱心に指導をして下さったNTT西日本の社員の皆様方に心からお礼申し上げたいと思います。記帳な体験をさせて頂き、本当に有難う御座いました。
岡山地方法務局
法学部3年 高安亜矢子
8月2日から8月13日までの2週間、私は岡山地方法務局の登記部門にインターンシップ生としてお世話になりました。これからの進路を決定する上で、実際に現場で働いてみたいという気持ちが応募のきっかけでした。
インターンシップに向けて事前に私が取り組んだことは、面接のときに頂いたパンフレットに目を通した程度でした。しかし、やはりそれだけでは勉強不足だったので、もし来年法務局に行かれる方がいるなら、特に会社法を復習して行くことをお薦めします。
実習では、様々な業務を体験させてもらいました。最初に法務局登記部門の業務概要の説明を受け、二日目以降からは実践に移りました。登記部門は大きく分けて不動産部門と商業法人部門で構成されており、当局で最も規模の大きい部門です。それゆえに業務の幅も広く、中には法務局が取り扱うとは想像できないものもありました。その代表的な業務である法17条地図作製の補助体験をさせて頂きました。法17条地図とは、不動産登記法17条に基づいて作製された図面のことをいい、今、都市部を中心として全国的に地図整備が遅れているという現状にあります。地図整備がされていないと、不動産取引や経済取引に支障をきたすことになります。そこで、法務局独自に10年計画で法17条地図作製作業を進めていると伺いました。そこで私は、そもそも法務局が地図を管理するということに違和感を抱き、質問をしてみたところ、登記の性質上土地の権利関係が重要となる故、登記申請と地図管理をセットにして業務を行った方が、便宜上都合がいいとのことでした。
実際、作製補助体験では玉野市築港三丁目・四丁目へ直接出向き、土地と土地の境界点を定めるという業務を見学しました。炎天下の中、職員の方が当事者の間に立ち、両者が納得する境界点を定める姿は、世間で言われている「公務員」像とは全く異なりました。それは17条地図作製に関わっている職員の方のみではなく、私がお世話になった職員の方々全員に共通することです。ひとりひとり担当している業務に対し、責任を持って取り組んでいる姿に、あと2年後には社会人になるであろう私自身との差をはっきりと見せつけられました。
他にも、商業法人登記調査事務を体験させて頂きました。登記は法人の戸籍と言われるくらい重要なものである為、申請された書類のひとつひとつを細かくチェックする必要があり、その作業を調査と呼んでいます。これは大変神経を使い、なおかつ日々勉強が絶えない業務でした。と言うのも、ここ数年商法大改正が行われており、かつ様々な特例も施行されていることが大きいと担当職員の方がおっしゃっていました。ここでも私は苦戦し、大学の講義における「登記」と実務における登記との違いを肌で感じました。
最後に、ご多忙の中、快く受け入れ、貴重な体験をさせて下さった岡山地方法務局の皆様、今回の実習にあたってお世話になった先生方、岡山県経営者協会の皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
ピュアリティまきび
法学部3年 竹林 美保
私は今回のインターンシップでピュアリティまきびに研修に行かせていただきました。アルバイトでフロント係をした経験からホテル業界に興味を持ち、様々な角度からホテルの仕事を経験してみたいと思っていたので、今回、宴会係として10日間行かせていただきました。
実習にあたり、事前にインターネット等でピュアリティまきびの施設や収容人数、さらに公立学校共済組合と関係しているという一般企業とは少し異なる企業形態について勉強していきましたが、実際の実習ではあまり必要ではありませんでした。実際に必要であったのは、敬語の正しい使い方を勉強しておくことだと思います。お客様に対してはもちろん、上司の方に対して、また、一緒に仕事をする人みんなに対して正しい(適切な)敬語を使えることは大切だと思います。なぜなら、ホテルは24時間稼動しているので違う時間帯に勤務している人がいれば、他の企業と同じく部署がいくつかあるので、違う部署に属している人もいる中で同じお客様にサービスを提供するので、お互いがきちんと情報を伝え、受け取ることが必要です。例えば、予約係と打ち合わせしてあるのに、宴会係とまた同じ打ち合わせをするなどということは、お客様を煩わすことになるので、予約係から宴会係に正確にお客様のプランを伝えることでそれが回避できます。その伝達の際に普段と同じ口調ではなく、敬語を使うことで正確に伝え、受け取ることができると思うので敬語の正しい使い方は重要だと思います。
実習は初日に施設の見学や宴会係の仕事内容の説明をしてくださり、すぐにお茶出しや宴会会場のセッティングを教えてくださいました。初めは、みようみまねでしていましたが、基本を教えてもらってからは次に何をするかが分かってきました。どんな仕事でも、効率よくこなすことが求められましたが、そのためには先輩に教えてもらうのが一番よいと思いました。セッティングの際の机のたたみ方ひとつとっても、先輩のやり方でやるとスピードが全然違いました。社会に出てからは自分で考えて行動することも大切だけれども、自分より優れた人から技や知識を盗んで自分のものにすることも大切だと思いました。
今回のインターンシップでたくさんのことを体験し、学びましたが、私が一番印象に残っているのは、結婚式・婚礼でのサービス実習です。一生に一度、何ヶ月も前から準備してきているものであるので、担当の方はもちろん、料理をサービスするだけの私も緊張していました。しかし、係の人がきちんと役割分担をしてくれ、それぞれが自分の仕事をきちんとこなすことで、お客様の満足のいくものができてゆくことに感動したと同時に、自分も早くその手伝いをできる立場になりたいと思いました。
最後に、このような貴重な体験をさせてくださったピュアリティまきびの皆様、また、その機会を与えてくれた岡山県経営者協会の方々、本当にありがとうございました。
山陽新聞社
法学部3年 西本 聡輔
山陽新聞社での10日間のインターンシップは大変貴重な経験となった。新聞記者という仕事に興味があったため今回参加させていただいたが、実際に新聞記者という仕事がどのようなものかを知る以上の収穫があったように思う。
新聞社での実習ということで、事前の準備として失礼のないように最低限新聞はよく読んで実習に望んだ。特に山陽新聞を中心に読み、最近のニュースや、紙面の特徴などを頭に入れていった。実習中に再三言われたことは「よく新聞を読みなさい」ということだった。テレビやインターネットなどの普及で、紙としての新聞はスピードや臨場感では劣るが、新聞は解説記事や論評などで細かく物事を理解でき、また活字で読むということで深く考えることができる。単に世の中の動きを知ることができるだけでなく、こうした新聞の利点を多くの方から聞き、新聞が身近な勉強の材料だということを改めて思った。
実習では政治部、社会部、経済部、運動部、文家部を2日間ずつまわり、実際に記者の方に同行して取材や撮影、記事の作成などをさせていただいた。実際に記事を書いてみると、普段読んでいるにもかかわらず書き方に戸惑ったのを覚えている。いかに読む人にわかりやすく正確に、伝えるべきことを伝えるかというのは想像以上に難しく、読み手と書き手の違いを知った。また同じ出来事でも視点を変えることで記事の印象も変わることから、物事を多角的にとらえることの大切さも知った。
記事の作成の仕方も勉強になったが、それ以上に印象に残っているのは各デスクの言葉だった。「文章は練習すれば書けるようになるもの。大事なのは取材相手との信頼関係や人間性だ。」取材は人に話を聞くところから始まる。信頼関係がなければ、話も聞いてくれず情報は入ってこない。しかし逆によい関係を築いていれば予想もしなかったような情報も手に入ることがあるという。これは記者という仕事に限らず言えることではないだろうか。
またあるデスクは、「単に起こった出来事に目を向けるだけでなく、なぜそうなるのかを考えることが大切」とおっしゃった。私はこれまでただ教科書に書いてあることを覚えたり、理解したふりをしたりしていたように思う。記者の方は何事にも興味を持ち、わからなければ「なぜ」と問いかけることで不明な点をなくし、理解した上で記事を書いていた。こうしたことは今後の学生生活においても十分役立つこととして勉強になった。
山陽新聞の方はみな、仕事に対するプライドを持っていた。新聞という多くの人に影響を与える仕事のため、それぞれに責任が伴う大変な仕事だが、それぞれやりがいを感じ高い意識をもって仕事にあたっていた。私も仕事にやりがいを感じたいと思うし、こうした高い意識をもって仕事をしたいと今回の実習で考えた。
最後に、お忙しい中未熟な私どものためにご指導してくださった山陽新聞社の皆様、またこのような貴重な経験の場を与えてくださった関係者の皆様に感謝申し上げます。
一井・光成法律事務所
法学部3年 野村 賢一郎
今回、私は、一井・光成法律事務所で夏休みの10日間お世話になり、就業体験をさせていただきました。事前に指導教官よりご指導を受けたのですが、その話を踏まえたうえで、私自身この就業体験を通じ、「“仕事をこなす”ということはどういうことか」を学び取ろうと考えていました。私は仕事をこなすには知識も必要だと思い、就業体験前には、実務で必要と思われる手続法(民事訴訟法と刑事訴訟法)を中心に大学で習った範囲を復習していきました。いざ実習に入ると、手続上の言葉や書面の名前が飛び交う毎日だったので、もちろん私の頭に知識として定着していない書面の名前も多々ありましたが、事前の復習はある程度役に立ったと思います。
次に、具体的な就業体験の内容とそこで私自身が学び取った内容についてお話したいと思います。この10日間で、ここで書くことができないくらいたくさんの体験をさせていただきましので、この報告書ではそのうちの一部を述べてみたいと思います。一番印象が強かったことは、現実に裁判所や法務局、市役所に提出する書類を書かせていただいたことです。中でも、裁判所に提出する訴状を書かせていただいたことが心に残っています。一井先生から、「自分で考えて、この事件の訴状を書いてみなさい」と言われ、事件の資料と何冊かの教科書を示していただき、他の事件の訴状等のサンプルを見ながら、暗中模索の状態で訴状を書き始めました。完成までに何度も何度も一井先生に訂正を受けましたが、なんとか一枚仕上げることができました。やはり実務は、大学での勉強とは一味も二味も違うものだと実感した瞬間です。大学で学んだ知識が思うように使いこなすことのできない歯痒さを覚えましたが、この時の達成感はとても大きなものでした。この体験からは、私自身が仕事に対して積極的になればなるほど、一井先生や事務員の方が私のことにかかりっきりになってしまうので、先生や事務員の方自身の仕事の時間を削ってしまい、かといって、逆に消極的になればなるほど、この就業体験実習に参加した意味もなくなってしまうので、ここのバランスを調節することが非常に難しかった、ということを感じ取りました。事務員の方もここに非常に頭を悩まされることが多い、と話されておられました。
また、刑事事件の依頼があったため、ある警察署の接見室にも連れていっていただけました。まさにドラマで見たことのある状態がそこにはありました。しかし、雰囲気はとても殺風景なもので、ドラマの中のものとは似ても似つかないものでした。現実の雰囲気をダイレクトに感じることができ、よい経験になりました。一井先生も、フィクションのようなことがノンフィクションで毎日起こる、勉強においては間違いを何度も何度も訂正できるが、実務は毎日、全ての問題がぶっつけ本番で間違えることは基本的に許されないんだ、と話されておられました。ここでも大学の勉強と実務の差を見つけることができました。
今回、以上を含めた多くの体験を通じて、私は仕事をきちんとこなすことの難しさを垣間見ることができたと思います。もちろん、10日間という極短い期間で、きちんと仕事をこなすとはどういうことかを身につけることはできませんでしたが、こなしている状況を見ることができただけでも大変大きな成果だったと考えています。
最後になりましたが、今回の就業体験実習について手取り足取りご指導していただいた弁護士の一井先生、事務員の桑原さん、森さん、そして、運営委員会の先生方、指導教官である西原先生には心から感謝しています。今後の進路選択や仕事をするときにこの就業体験は多いに参考になると思います。本当にありがとうございました。
岡山県庁生活環境部青少年課
法学部3年 吉田真規子
私は、8月16日から8月27日にわたり、岡山県庁生活環境部青少年課で修業体験を受けさせていただきました。参加した動機は、以前から県庁の業務に興味はあったものの、実際にどのような業務が行われているのかは自分の目で見て体験してみなければ分からないと思ったこと、そして、社会に出る前に「働く」という意味を自分なりに理解して、これからの大学生活に生かしていきたいと考えたからです。
実習前には、事前訪問時に頂いた資料を読んで学習したり、インターネットなどで青少年問題について自分なりに調べたりと業務内容について理解するよう努力しましたが、実際の職場に配属されると思うとやはり不安になりました。
青少年課では、実に有意義な体験をさせていただきました。「少年の主張岡山大会」では、大会運営スタッフの一員として録音の担当をさせていただいたり、ボランティアの高校生を指導する担当をさせていただいたりと、貴重な体験をさせていただくことができました。仕事では、「努力した」とか「頑張った」だけでは通用しないことや、年齢に関わらず指導的立場になることがあることを知り、働くことの厳しさや責任を理解することができました。また、県庁の仕事はデスクワークだけではなく、現場での作業も数多くあるということを身をもって体験できたと思います。例えば、自然とのふれあいや、自然の厳しさを通じて青少年が人間本来の生き方を追求する場所として生まれた「岡山県青少年の島」の備品チェックに同行させていただいたり、青少年の居場所施設である「みらいふるシ-ポ」で一日駐在体験をさせていただいたりしました。さらに、県政に青少年の意見を反映するとともに、社会心・自立心を育てることにより青少年の健全育成を目的とした「ユースチャレンジ21会議」にも参加させていただくことができました。青少年と対等な立場に立ち、岡山県をよりよくするためにはどうすればよいかを青少年とともに真剣に考える姿は、私の中の今までの公務員のイメージとは全く異なり、実にすばらしいものでした。公務員とは本当に国民のために働く仕事なのだと再認識できる貴重な体験となりました。青少年総合相談センターでは、相談員の方の生の声を聞く機会を与えていただき、現代の青少年の抱えている問題や対応の仕方など詳しい説明を聞くこともできました。
今回のインターンシップを通じて様々な方と出会う機会に恵まれました。そして、現場の貴重な話を聞くことによって見識を広めることができ、さらに成長できたと思います。「研修前とは別人のように積極的になれている」と最終日に言っていただけたことが、今でも私の心の中に残っています。10日間にわたり、お忙しい中、未熟な私を温かく受け入れてくださった青少年課のみなさんに心からお礼申し上げたいと思います。そして、このような貴重な機会を与えてくださったインターンシップ運営委員の先生方に深く感謝いたします。ありがとうございました。
岡山市役所市民局市民サービス部市民課
法学部3年 溝田 恵子
私は、8月4日から8月17日までの期間を、岡山市役所市民局市民サービス部市民課にお世話になりました。市民課というのは住民票や戸籍を扱う課であり、我々市民にとって一番なじみ深い課だといっても過言ではないと思います。それゆえ、市民課の窓口のイメージが、市民にとっての市役所全体のイメージに大きく影響します。インターンシップ生とはいえ、市民の目からみれば私も一職員として映るため、このことを肝に銘じながら研修に取り組んでいました。
今回のインターンシップにあたり、なにか事前に取り組んだということはありませんでした。それは、我々インターンシップ生のお世話をしてくださった森さんが、予備知識よりもむしろ職員のように内部の人間ではわからなくなってしまっている、市民の目からみた率直な意見や提案を大切にしたいとおっしゃっていたからです。
今回のインターンシップでは、書類作り、窓口業務の補助、窓口サービス向上のためのアンケート取り、お客様の案内、印鑑登録書の整理、会議の設置準備・撤収などを行いました。市民課の業務というのは高度な専門知識がいり、また、ミスが決して許されない仕事であるため、インターンシップ生が扱ってよい仕事というのは必然的に限られてきます。ゆえに、今回扱ったのは市民課業務の中でもごく一部分だけですが、いろいろ学ぶことができました。印鑑登録など、今まであまりよく知らなかった業務にも触れ、市民課業務への理解が深まるとともに、興味が増していくのを感じました。
インターンシップにおいてつくづく思ったのは、仕事というのは正確性はもちろんのこと、迅速性も必要不可欠だということです。これはなにも市役所に限ったことではないかもしれませんが、市民課の業務は、特にこの二つが要求されているといえます。市民課には一日に大量の申請書や届出がくるのですが、職員の方はそれを確実に実践されており、尊敬の念を感じずにはいられませんでした。正確性と迅速性、この二つはすぐに身につくというものではありません。だからこそ、社会に出る前にこの姿勢の基礎部分だけでも身につけておきたいと思いました。
研修の終わりごろに、私の目からみた市民課業務の改善案をいくつか出しました。実際それが採用されるかはわかりませんが、少しでも市民課の改善に貢献できたらと思っています。
このインターンシップでは、社会人としての心構えなど、大学では学べないことを学ぶことができました。また、私の今後の進路選択に大いに参考になりました。頭のなかでこの仕事はこういうものだと思っていても、実際働いてみないとわからない部分も大きいと思います。インターンシップという機会がなければ、私はわからずにいたことや気付かずにいたことがたくさんあったでしょう。ゆえに、インターンシップに参加することができて本当によかったと思っています。
最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださった法学部学生委員会の方々、岡山県経営者協会の方々、そしてお忙しい中私を受け入れてくださった岡山市役所市民局市民サービス部市民課の皆様方にお礼を述べたいと思います。ありがとうございました。