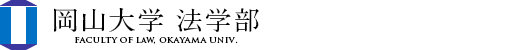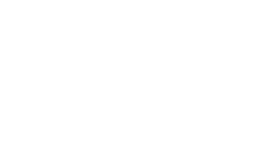ホーム > 就職・資格情報 > インターンシップ > バックナンバー > 2005年度 インターンシップ 岡山大学法学部生の就業体験実習
2005年度 インターンシップ 岡山大学法学部生の就業体験実習
岡山大学法学部におけるインターンシップについて
岡山大学法学部では,2000年よりインターンシップ(就業体験実習)を行っています。
インターンシップは,在学中に一定期間,民間企業や行政官庁,法律事務所などの職場で実際に業務を体験することにより, 大学で法律学・政治学を学ぶことの意味を実践を通じて理解し,また将来的には自らに適した進路を選択する力を皆さんにつけてもらうことを目的としたカリキュラムです。
対象は原則として3年次生(場合によっては4年次生も可)で,夏季休業中の2週間に実習を行います。



オークラフロンティアホテル海老名でのインターンシップ実習風景(2005年度)
隈田原 恵さん ( 法学部 3年 )
2005年9月9日~2005年9月22日の2週間
インターンシップ報告会
2005年 11月30日,インターンシップ報告会が開催されました。6年目を迎える今年は,山陽新聞社,岡山ネットワーク(オニビジョン),岡山放送(OHK),オークラフロンティアホテル海老名,瀬戸内海放送,西日本法規出版株式会社,西日本電信電話株式会社(岡山支店),法務省岡山地方法務局,岡山市役所,岡山県庁,税理士事務所,司法書士事務所,弁護士事務所の28の受入機関のご協力の下,42名の学生が就業体験をすることができました。
報告会では,学生委員会委員からの概要説明の後,今年度の履修学生の代表8名が,各受入先でのインターンシップの体験を報告しました。それぞれにとても貴重な経験をしてきたこと,そして彼等がその中で成長したことが実感できました。また,下級生に対してはしっかりした目的意識を持ってインターンシップへ臨んでほしいとのアドバイスが印象に残りました。毎年思うのですが、岡大法学部生の優秀さを改めて感じさせるものでした。












インターンシップ報告書
河田英正法律事務所
法学部3年 大角 由希
私は、この度のインターンシップにおいて、河田英正法律事務所で、約2週間お世話になりました。たった2週間という短い間ではありましたが、中身の濃い、充実したインターンを送ることができました。インターン中に経験したことは何もかも私にとって重要で、甲乙付けがたいのですが、その中でも忘れられない事を挙げたいと思います。
まず、弁護士はある種の研究者だと感じました。それは、一つ事件を担当するにしても、専門的に特化された事件であれば、その研究が必要です。昨今増加している先物取引犯罪などが良い例であり、弁護士の先生方は勉強会を開くなどしてこの種の事件に対応できるようにしています。また、依頼人の主張を自分のものとするためには、法律に関係ないことが重要になってくるのです。それが分かった時、私は法律から離れてみることにしました。インターネットショッピングで高額な品を多数売りつけられ、買ったものの、商品が最初から使えないとして、支払い拒否を求める事件がありました。この商品の中に輸入掃除機がありました。30万以上の不当な金額で買わされていたので、私はこの製造元のアメリカの会社を調べ、慣れない英文を読みながらアメリカのサイトでこの掃除機の現地価格を調べました。アメリカの現地価格は約2000ドル、日本円にしておよそ20万位です。そこから輸入税なども調べましたが、全部あわせても30万という金額にはなりませんでした。こういう関係のないと思われる作業が、1つ1つの立証につながるのだと考えました。そのことを河田先生に伝えたところ、あるものを見せて下さいました。それは事務所の別室にある、膨大な裁判資料と、宗教関係に関する山のような本です。河田先生は、あの有名な「青春を返せ裁判」で逆転勝訴をした弁護団の団長を務められた方です。10年以上という長い年月をかけて勝ち取った判決であり、また何よりもこの種の事例においてのリーディングケースとなる判例を作ったのです。たった1つ掃除機の値段を調べるのにも時間がかかったのに、その資料の山を見た時、10年という重みを感じるとともに、真の立証の難しさも理解することが出来ました。 また、鳥取の簡易裁判所で裁判を傍聴した日もありました。岡山にいる河田先生がなぜ鳥取まで出向いて裁判をするのか不思議でした。その理由は、鳥取の弁護士数は全国で一番少なく27人しかいないため、依頼者の弁護をしたくても全てカバーできないということです。実際、今回傍聴した事件以外にも、鳥取での裁判は何件か持っているとのことでした。この実習では、法律家が少ないということは以前から主張されていますが、それを身近に実感することができ、司法の現状を考えるきっかけにもなりました。
今回のインターンで河田先生が終始一貫して私に伝えたかったことは「法と社会のあり方をどう考えるか」ということだったと考えます。実際に事務所に持ち込まれる事件は、授業で聞く何の変哲もない学説の争いではなく、社会を通した臨場感ある生の争いだからです。そのような争いは、実際学校の外に出ないと当然分からないものです。
そこで来年法律事務所のインターンに参加しようと考えている方に伝えたいことは、インターンに参加することで、生きた法律の姿を知ってもらいたいということです。現実の社会、紛争の中に法律がどのように生きているかを知ることは、法律をより良く理解するために、ひいては、紛争解決の道具として法律を使いこなせるようになるために、大いに資するものとなるはずです。また、法を上手く使いこなす技量も大切ですが、それ以上に、事件を適格に把握し、両当事者それぞれの立場にたって、あるいは第三者の視点から、多角的に物事を捉えることの大切さも実感することができると思います。このようなことは、紛争解決の学問としての法学には不可欠なものです。ともかく、インターンに参加することでそうした事に気づいてもらいたいと思います。
余談になりますが、河田先生は大変正義感が強く、年齢を感じさせないほど行動派な先生です。多忙にもかかわらず、お昼は必ず一緒に食べてくださり、私とのコミュニケーションをたくさん取って下さいました。趣味の旅行や家族、大学時代のこと、法律科目の勉強法から最近の出来事まで幅広く、私のつまらない世間話にも笑って応えてくれました。河田先生の下でインターンを経験できたおかげで、今では、弁護士という漠然とした夢だったものが、「河田先生のような、人から信頼される弁護士になる」という目標に変わりました。インターン最終日、河田先生からの「弁護士になって帰って来てくれるのが、最高の恩返し」という言葉は忘れません。2週間お世話になり、残りの大学生活にも多分ない程の大きな影響を与えてくれた恩返しは、必ずします。
最後になりましたが、河田先生をはじめ、事務所の皆さんには心から感謝しています。大本先生は弁護士会の法律相談へ一緒に連れて行ってくださり、勉強や内容証明の書き方を教えていただき、大変感謝しています。また、いつも明るい事務の深井さん、秋本さん、平嶋さん、久本さん、そして、このようなすばらしい機会を与えてくださった、学生委員の先生方にもこの場をお借りしてお礼を申し上げます。本当に皆さんありがとうございました。
岡山市役所企画局総合政策部文化政策課
法学部3年 岡本 知子
私は、8月22日から9月2日までの12日間、岡山市役所企画局総合政策部文化政策課で実習を受けさせていただきました。私は、社会で実際に働いている人と関わっていくことで自分の進みたい道をはっきりさせることができるのではないだろうかという期待からインターンシップを受けてみようと決意しました。そして、「文化による町づくり」という文化政策課の業務に興味を抱き、是非この業務に携わってみたいと思ったことからインターンシップ先として岡山市役所文化政策課を希望しました。
今回のインターンシップにあたり私が事前に取り組んだことは、文化政策課のホームページに目を通したことそして事前訪問の際に戴いた資料に目を通したことです。特に事前訪問の際に戴いた資料には数多くの冊子・パンフレットがあり、文化政策課の業務を理解するのに非常に役立ちました。これらの資料により、文化政策課が市の主催するイベントである「おかやま音楽祭」「岡山市芸術祭」「岡山市文学賞」の開催を中心に様々な事業を手がけていることを知り、より一層文化政策課の業務について興味が深まりました。
インターンシップでの研修テーマは「地域文化の振興にあたり、文化芸術活動に関する情報収集・発信をどのように進めるか」でした。このテーマのもとで、企画・立案の際によく用いられるブレインストーミングという手法を用いて他のインターンシップ生とともに「おかやま音楽祭」の広報宣伝方法について考えたり、文化政策課事業のラジオ宣伝シナリオをつくったりという作業を行いました。また、市内の様々な文化施設の見学をし文化施設の関係者の方々のお話を聞く機会、デジタルミュージアムの会館補助・おかやま音楽祭の開会補助作業に携わる機会を作っていただきました。このようにイベントが行われている表舞台とイベントの裏側にある準備段階の作業の両方を体感できたことで、研修テーマである情報発信についても理解を深めることができ、その重要性を認識できました。
課の方々は常に「市民協働」を意識されており、市が押し付ける形ではなく市民の方々と一体となってイベントを成功させていこうという態度で仕事に臨まれている姿が印象的でした。このような文化政策課の方々の仕事への姿勢から、自分の立場からだけではなく相手の立場に立って物事を考えることの必要性を改めて痛感しました。
このインターンシップ中に様々な活動をしていく中で今の自分に不足しているものは何か、何が必要であるかをじっくりと考えることができたと思います。また、自分がどのような環境で働きたいのかを明確にすることができました。本当に得るものの多いインターンシップとなったと思います。
最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださった岡山県経営者協会の皆様、岡山大学法学部学生委員会の皆様、そして、お忙しい中私を受け入れてくださった岡山市役所企画局総合政策部文化政策課の皆様に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
岡山県庁生活環境部男女共同参画課岡山県男女共同参画推進センター(愛称:ウィズセンター)
法学部3年 栗 良太
私は岡山県庁生活環境部の男女共同参画課とウィズセンターでそれぞれ1週間ずつ就業体験をさせていただきました。今回、このインターンシップに参加した動機は、以前から興味のあった公務員の業務を体験し、将来の進路を決定する上での参考にし、またたるみがちになってしまっている自分に喝を入れ、残り少ない大学生活にはりを持たせようというものでした。
まず、実習先に電話で質問しましところ、実習に先立って事前訪問や事前学習は不要と担当の方に言われましたので、特別何の準備もせずに実習に臨みました。そのせいで、実習に重大な支障が生じたというわけではありませんが、スムーズに実習を進め、よりよいものにするためには個人的に事前学習を行う必要があったと思われます。
さて、実習ではいろいろ貴重な体験をさせていただき、非常に勉強になりました。県庁の男女共同参画課の方では、男女共同参画社会の実現に向けて、県で策定されていた「おかやまウィズプラン21」という基本計画の5年に一度の改正の時期でして、この基本計画を改正するための審議会に参加させていただきました。県の現状と課題を踏まえながら丁寧な検討がなされていまして、また、基本計画内のひとつの文言の言い回しにさえも、かなりの時間をかけて議論がなされており、志高く、読みやすい、わかりやすいプランを作成することは大変であるなと身をもって感じさせられました。説得力があり、人の心を捉える意見やプランを作り出すには、大学で身につけられる知識、教養などのバックボーンも必要なことは言うまでもないでしょう。またその上に、特に、このような仕事には(どんな職種にも言えることでしょうが)、主体的に物事を考え、またそれをはっきりと表現する能力が要求されます。最近の学生はこの能力に乏しいとよく言われますが、この重要性をあらかじめ認識していれば、学生のうちに危機感を持ってこの能力を鍛えることも可能であると考えられます。特にゼミでの発表や議論にまじめにしっかり取り組んでいくことが最も効果的な訓練になるのではないかなと考える次第です。
さて、県庁(男女共同参画課)の業務ですが、時期が時期だっただけに審議会などの会議関連のものが中心だったのですが、もちろんそれだけをやっているわけではなく、それぞれの人がそれぞれ別の他の仕事(市町村合併に伴う様々な資料の改正とか、意識調査みたいなものとか、関連機関との接触とか、相談業務など)と掛け持っていて、休む暇もない感じでした。実際、男女共同参画課の方々の全員がそろってそれぞれのデスクに座っている機会はめったになく、県庁職員の仕事=自分の机での(黙々とやる)仕事というものでもないということがよく分かりました。
次に、ウィズセンターの方ですがこれは県の出先機関で、ここでは主に、情報提供や各種講座、相談業務や就業支援、各種団体の活動・交流の場と機会の提供などを業務として行なっています。ここは具体的活動のできる、まさに現場といった感じで、男女共同参画社会づくりを推進していくための総合拠点施設として県民の生活や取り組みをサポートしており、その役割は重要です。ここでは、県民と直に接触することが多く、その分刺激を受ける環境でした。当事者(県民)と直接接していくことは実に気苦労の多い仕事ですが、ただその分やりがいのある仕事ではあるなと感じさせられました。
また、今回の実習で、多くの方々から男女共同参画社会の必要性、重要性についてご指導いただきました。少子高齢化に対応していくため、経済活動の成熟化等を実現するためにも男女共同参画社会の実現は必要であり、法律でもってその実現は21世紀のわが国の社会を決定する最重要事項であると位置づけている事にもうなずけます。理想的社会の実現のためには社会環境の整備だけでは足りず、問題の実質的解決のためには我々1人1人の意識改革が必要とされています。このことを念頭に置き、わたしたちは自ら考えた上で、常に様々なことに問題意識を持ち、行動に生かしていくべきです。このような視点は、今後の大学での勉学の上でも、社会に出てからも役立つことでしょう。また、ウィズセンターで一般相談業務をされている方との会話の中で、相談の専門家としての志の高さに心を動かされました。相談員の方々は相手の方によりよいサービスを提供できるように自主研修や自主学習をされて、ご自分の知識やコミュニケーション能力等を高めておられて、専門家としての責任の重さ、大変さを感じさせられました。相手の方の苦しみを共感、共有し、ご自分の精神をすり減らしてでも県民のために真剣に働かれておられる姿は非常に尊敬できるものでした。私も向上心を失わず、世間や人の役に立てるような人間になれるよう、勉学に励み、自らを高めるよう努力をしていきたいと思っております。インターンシップを通じて、私に欠けているものは何か、これからどのような力をつけていくべきなのかと、自分を見つめなおし、前向きに軌道修正する機会を得ることができたと感じております。このように、インターンシップは価値ある貴重な体験をすることができますので、ぜひ参加されることをおすすめします。
最後になりましたが、大変お忙しい中、貴重な経験をさせていただきました岡山県庁生活環境部男女共同参画課の皆様、ウィズセンターの皆様、またこのような貴重な機会を与えてくださった岡山大学法学部学生委員会の皆様、その他関係者各位の皆様に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
NTT西日本岡山支店
法学部3年 中 安也美
私は、NTT西日本岡山支店において2週間のインターンシップ研修を受けました。その動機は、就職活動を始めるにあたって「企業の内部を見る機会」が必要だと感じたからです。そして、この貴重な機会を十分に生かすために、インターンシップが始まる前、私は2つの課題を自分に課しました。まず、学生として受身で行動しないこと、そして企業で働く人たちから、この機会を生かしてなるべく多くのことを吸収することです。
NTT西日本岡山支店のインターンシップカリキュラムは、1週目が企業内の各部門に関する研修で、2週目が企業法務実習です。
1週目は、業務内容についての説明に加えて、通信設備見学やソリューション営業に関するプレゼンテーション実習、インターネットの接続実習等の企業活動を実際に体験しました。企業の中で、商品やサービスをつくり、お客様に提案・提供し、さらにサービスを維持するために対策を講じるという企業活動の一連の流れを理解することができました。特に印象に残ったのはソリューション営業実習で、商品紹介のプレゼンテーションを行ったことです。社員の方々から直接講評を頂き、自分の考えを正確に相手に伝えて説得することの難しさを知りました。
2週目は企業法務に関する法律と、事例問題や具体例を題材にして解決への考え方を学びました。企業法務は法律の知識だけではなく、ケースや相手方の状況を把握する広い視野と、周囲との信頼関係が必要な仕事だと感じました。
インターンシップ実習記録の中で、私が最も使った言葉は「実感」でした。私が実感したこととは、「営業とは人(顧客)と問題を共有し、本気で考えることだ」とか、「法務で必要なものは信頼である」、「企業の核は、商品・サービスではなく人である」など、説明を受ければおそらく誰でも理解できるであろう事ばかりです。けれども、体験を通して実感したことや、実際業務をなさっている方の言葉にはすごく力があり、自分の中に根付いていくような気がします。さらに、私は今回それらの「実感」を通して、今の自分にとって何が足りないか、今後の自分に対する課題を見つけることができました。これは、普段の学生生活ではけして得られないものであって、大学から少し外に出て、企業という吸収することが非常に多い場所に一歩踏み込んだからこそ見つけることのできた財産だと思います。
最後になりましたが、お忙しい中、貴重な体験の機会を与え、熱心に指導してくださったNTT西日本岡山支店の社員の皆様と、そうした機会を設けてくださった学生委員会の先生方に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
弁護士法人岡山パブリック法律事務所
法学部3年 福摩 恵吾
私は、今回、岡山パブリック法律事務所で2週間お世話になりました。インターンシップに行く前には、大学入学当初考えていたロースクールに行くという希望が揺らいでいて、実務に触れることで、もう一度自分の気持ちを確かめようと思っていました。
インターンシップ前は特にこれといった準備は行いませんでした。事前に行ったことは、ホームページでお世話になる法律事務所がどんなところなのかを調べたこと、事前訪問で担当の水谷先生が利息制限法を読んできてとおっしゃっていたので、それに目を通したことぐらいでした。
インターンシップ中は、裁判傍聴、調停見学、法律相談立会い、依頼人訪問、事務的なことまで幅広く体験させていたただきました。
特に、私が印象深く覚えているのは、成年後見制度を利用した被後見人の方の自宅や入所されている施設を訪問した時のことです。弁護士の仕事において、依頼者との信頼関係が重要だということは、どんな事件でも同じだと思います。ただ、成年後見人選任の場合は特に慎重にならなければならないのだと感じました。弁護士が後見人に選任されれば、被後見人の財産も管理することになります。けれども、被後見人の家族にとって弁護士は赤の他人であり、後見人になったことを必ずしも快く受け入れてくれるとは限りません。また、相続問題が絡んでくることもあります。だからこそ、被後見人やその家族と繰り返し会って、被後見人の体調や近況を気にしながら、信頼関係を築いていくことが重要なのだと思いました。
また、事務所では後見事務の研修があり、私も同席させてもらいました。後見人は苦労する面も多いですが、お年寄りが増える中、介護・福祉サービス事業者との契約などの関係で、成年後見のニーズは高まっているそうです。私にとって、弁護士の仕事での介護・福祉に関する部分のイメージはあまりなかったので新鮮でした。
そして、事務の仕事もいろいろさせていただきました。弁護士は、裁判や法律相談で多くの時間を使っているので、その他裁判所や相手弁護士に資料を送ったり、自己破産事件でサラ金業者と連絡を取ったりするのは事務局の仕事です。私も、サラ金業者に取引開示請求のFAXを送ったり、依頼者がサラ金業者に払いすぎたお金(過払い金)を返還してもらうための電話をしました。利息制限法は過払い金の計算に使いました。普段電話するような相手ではないので緊張しましたが、相手との交渉はよい経験になりました。
岡山パブリック法律事務所は公設ということもあり、他の事務所に比べ困難な事件が回ってくることもあるそうです。また、来年から始まる被疑者の国選弁護制度や弁護士過疎地の現状(新見など)などにも関心が高く、そういう点でも刺激を受けました。水谷先生以外に他の弁護士の方とも話す機会があり、私の将来のことも少し相談できました。インターンシップを終え、ロースクールをもう一度選択肢として考え、そのために勉強しなければならないと思っています。
最後になりましたが、ご多忙にもかかわらず貴重な機会を与えてくださった岡山パブリック法律事務所の先生方、事務局の方々、法学部学生委員会の先生方に、深く感謝いたします。
西日本法規出版株式会社
法学部3年 藤原 弥都
私は、西日本法規出版株式会社に実質10日間、インターンシップに行きました。学部上、公務員や法曹関係の職業には少なからず知識が身に付くものですが、一般企業というのにはあまり縁が無くこれを機に一般企業というのはどの様なシステムで動いているのか、そう言ったことを知るために、今回参加した一番の動機でした。
私が事前にしたことと言えば、会社の概要を知ることは勿論、出版会社なので一応の確認として業界用語というのを多少確認していきましたが、ほとんど何をすれば良いのか検討がつかないという状態でした。勿論、岡山経営者協会が主催した事前研修には参加することで、企業の従業員としてのマナーなどを習うことも事前にしたことの一部ですし、それで安心を買っていたという感じでした。実際に職場に就いてみれば、私が事前にやったことで役に立ったことは会社の概要について知っていたことだけで、あとは全てインターンシップ先での教習によって身に付けていくしかない、という状況だったのです。しかし、事前にやっていたことがほとんど役に立たなかったことを後悔すると言うより、逆に付け焼き刃な知識を身に付けていなかったからこそ、教えて頂くことに、驚きを感じ、わからないところをどんどん質問していき更に知識を増やしていく、経験を増やしていく、ということに繋がり、その点では非常に良かったのではないか、と思いました。
また、今回の実習内容の一つとして営業同行というのがありました。営業同行とは、実際の打ち合わせに立ち会わせて頂いたり、納品にいったりするのを手伝ったりということをします。私達が電話ですませてしまうような、ほんの些細なことでも実際に出向いて確認をとることをかかさず、また、間違いの無いように相手に確実に「伝える」ということをこの営業同行では学びました。「伝える」ということは、相手に「言った」、書類に「書いた」、ということでは足りないのです。それを相手が本当に理解しているのか、書類に書いたのであれば、相手がそれに目を通しそれを把握してくれているのか、確実にしなければ、企業ではそれが致命的なことになりかねません。リスクを減らし、また、相手方にも気持ちよく仕事をすすめ、執筆をすすめて貰う為にも「伝える」というのは非常に大切なのだと思われました。普段は、あまり気にも掛けていない事が、実は重要なことであるというのは新しい発見でしたし、私がこれから様々に立ち会う事に対して「伝える」ということを実践していきたく思いました。特に、就職活動や公務員の面接では相手にいかに自分はどのような人間であり、またいかにその職場で働いていくのかを「伝える」というところに注目し、いかしていきたいと考えました。
さらに、雑務をこなすということも重要であると思いました。実にシンプルで、簡単な事ばかりですが、それによって作業は円滑に進み、より活発に動くことができるというのを実感できるのです。雑務に気を取られていたら、営業に行くにも、県外に出ることの多い従業員の方はなかなか自由に動くことができなくなってしまうでしょう。そこを上手くサポートしていくというのが、前述したいかにもシンプルな働きなのです。そこには培ってきた素早く雑務をこなしていく技術がいかされ、私にとって時間がかかることがあっという間に終わってしまうのです。それは、見習うべきところであり、そういう技術を盗むことができたというのも、また私のこの実習での体験の中の大切な学んだ所です。
多くのことを学ぶことができたのも、忙しい中、様々に工夫し、時間を工面して下さった、西日本法規出版株式会社の皆様のおかげです。最後ですが、インターンシップ期間中、大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
岡山県司法書士会
法学部3年 宮林 邦子
私は、今回のインターンシップで児島司法書士事務所に2週間お世話になりました。その間先生の業務を見学させて頂いたのですが、児島先生は、登記申請よりも簡裁訴訟代理や成年後見を多く扱われている先生であったため、裁判の傍聴や、被保佐人や被後見人の方との面会等に同行することが中心となりました。私が司法書士事務所へのインターンシップを希望したのは、そういった登記申請以外の司法書士業務がイメージできなかったからであったため、実際にそれらを見学することによって、司法書士業務の理解を深めることができ、私は何をするために、なぜ司法書士を目指すのかという、当然ではあるものの私が持ち得ていなかった司法書士の資格取得の意義を見出すことができ、非常に有意義なものとなりました。
とりわけ、業者事件の裁判を傍聴したことが、私にとって多くのことを考えさせる最も印象的なものとなりました。業者事件とは、消費者金融等が原告となり、債務者を被告として貸金請求訴訟を提起するというものですが、そのほとんどの裁判で、被告は準備書面の提出もすることなく欠席するため、業者側の主張が全て認められることとなるのです。しかし、消費者金融等の利息は、利息制限法の制限利率を超えているため、その部分は無効となり、支払う義務はなく、過払いが生じていれば不当利得として返還請求できるかもしれないのです。私が傍聴した日は、午前中だけで32件もの事件があり、その大半が業者事件でしたが、被告欠席のため、一件の事件にかかる時間はほんの数分であり、次々と事件が処理されていく光景に私は衝撃を受けました。この日の傍聴以前に、児島先生が債務者の代理人となって業者に対して提起した過払い金の不当利得返還請求事件を傍聴していたため、司法書士としても裁判で役に立つことができるのだと実感し、司法書士の簡裁訴訟代理業務に魅力を感じていただけでなく、初めて民事事件を傍聴したことで、実際に裁判によって困っている人が助けられているのだという裁判自体への新鮮な気持ちを持ったばかりであったため、業者事件の事務的な処理はなおさら衝撃的なものとなりました。司法書士の先生方も業者事件を傍聴すると、裁判が取り立ての手段に使われているようでとてもやるせない気持ちになると仰っていましたが、私も少なからずそのような想いを実感することとなり、専門知識を持つ人の重要性と知識の普及の必要性を痛感しました。
成年後見については、“財産管理だけが成年後見ではない”という先生の言葉どおり、2週間の間に、ケアハウスの入居申込みから箪笥の購入、被後見人の方が番号を忘れてしまった金庫の鍵を開けるということまで、非常に多岐にわたる仕事を見学させて頂きました。児島先生は、ケアハウスを選ぶ際には被保佐人の方の通院の便利さにも配慮し、入居申し込みの時には施設内の見学もさせてもらったり、箪笥の購入についても被保佐人の方の暮らし振りから必要であるだろうということを察して、使い勝手のいいものをこだわりを持って探していらっしゃったりと、ただ財産管理をしているというのではなく、被後見人や被保佐人の方々の生活の向上に尽力されているということが見受けられることがしばしばありました。そのような先生に対して、被保佐人の方の先生への感謝の気持ちは見てとることができ、成年後見では真摯に務めるほど大きなやりがいを手にすることができるのであると非常に魅力を感じました。さらに、私は児島先生から、成年後見は、法律の知識はもちろんのこと、例えば被後見人の方の病気のことなど、さまざまな知識が必要であり、そのように多方面にわたる知識を持っているからこそ勤まる大変な仕事であるということ、しかし、その分やりがいのとても大きい仕事であるということを教わりました。
インターンシップで私は多くの貴重な経験をすることができました。しかし何より嬉しく、有難く思ったことは、司法書士の先生方のお話を伺うことができたということです。私が目指している人たちであり、人生の大先輩でもある先生方のお話は非常に興味深く、多くのことを学ぶことができました。同時に、自分のコミュニケーションの拙さを痛感することとなり、今後の自分の新たな課題も見つけることもできました。私の日常生活の大学やアルバイトといった狭い世界では決して関ることのできない方々から受ける刺激はとても大きく、非常に充実した2週間を過ごすことができました。
最後になりましたが、ご多忙にもかかわらず快く受け入れてくださいました児島司法書士事務所の皆様方に心からお礼を申し上げます。そして、このような貴重な機会を与えてくださいましたインターンシップ運営委員会の先生方に深く感謝いたします。ありがとうございました。
岡山放送株式会社 報道局報道部
法学部3年 室井 孝之
今回私はOHKの報道部で10日間実習を行いました。放送局にも会社の運営を行う総務局、民放で番組を放送するために必要なスポンサー契約を行う営業局、どのような番組をどの時間帯で放送するかを考える編成局など多くの部署がありますが、私の実習先の報道局は番組作りに直接携わるところで、毎日放送されるニュースや定期的に放送されるドキュメンタリーやスポーツの番組を作る「商品開発の工場」です。
実習の事前には、実際放送されているOHK制作のニュース番組を見て、今社会で何が起こっているのか、また他局のニュースと比較しながら、この企業の独自性、目指しているものなどをできる限り理解するように努めました。
実習では、実際に記者・カメラマンの方と取材現場へ同行させてもらい、まずその取材内容の幅の広さに驚かされました。(裁判や会議のように堅いもの、デパートでの展覧会、スポーツのイベントなど地元に密着したもの、またあるときは山中での蜂の巣駆除や駅に登場した鈴虫の取材など)ニュースのトピックとしては、多くの局が共通で取り上げるものも多くありますが、OHKが独自で取り上げる地域密着型の旬の話題や丹念な取材・調査に基づくドキュメントは、視聴者により近い立場で、あるいは視聴者の「声」を反映させる形で創られるもので、ニュース番組制作の可能性の大きさを改めて実感しました。
私がこの実習で特に力を入れて取り組んだのは、ニュース原稿の作成です。1つのトピックの中で放送できる原稿の長さに制約があり、事実を忠実に伝えることに徹するため、どこか形式的で堅いものというイメージが自分の中にはありました。しかし、実際に原稿を自分で書いてみて、それをプロの記者の方に添削していただくという過程を通して分かったのは、形式を守ることもさることながら、「想像し創造していくこと」の大切さです。限られた文量の中で、TVというメディアに特有の映像をイメージしながら、視聴者の目線で分かりやすく、興味を持ってもらえるような原稿を創り上げていくことは熟練を要する作業ですが、わずか10日間の実習の中でもそのおもしろさが少し分かるようになった気がします。
自分が長年憧れていた職場で実習をしてみて、その責任の重大さを一番に痛感しました。1回の放送が何十万人もの人たちに見られている、その影響力は大きいです。何か放送上のミスや誤った・不適切な表現があればすぐにクレームの問い合わせがある、一方で視聴者が興味を持ってくれたトピックについても視聴者はすぐにリアクションを起こしてくれる。TVを支える視聴者の力は予想以上に偉大なものでした。番組に多くの期待を寄せる視聴者に応えるべく、その視聴者に何を伝えたいかという目的を持ち、少しのミスも許されない現場で働く人たちに接することができたのは今回の実習で一番の収穫でした。
お忙しい中、私に濃やかな指導を行って下さったOHKの皆様方、また今回このような機会を与えて下さった学生委員会の先生方、ありがとうございました。これから、今の自分にはまだ足りない責任感や目的意識を培い、社会に臨みたいと思います。