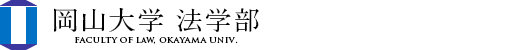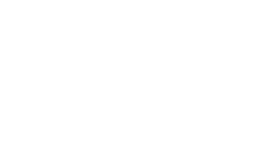ホーム > 就職・資格情報 > インターンシップ > バックナンバー > 2006年度 インターンシップ 岡山大学法学部生の就業体験実習
2006年度 インターンシップ 岡山大学法学部生の就業体験実習
岡山大学法学部におけるインターンシップについて
岡山大学法学部では,2000年よりインターンシップ(就業体験実習)を行っています。
インターンシップは,在学中に一定期間,民間企業や行政官庁,法律事務所などの職場で実際に業務を体験することにより, 大学で法律学・政治学を学ぶことの意味を実践を通じて理解し,また将来的には自らに適した進路を選択する力を皆さんにつけてもらうことを目的としたカリキュラムです。
対象は原則として3年次生(場合によっては4年次生も可)で,夏季休業中の2週間に実習を行います。

司法書士事務所でのインターンシップ風景
インターンシップ報告会
2006年 11月29日,インターンシップ報告会が開催されました。7年目を迎える今年は,岡山市役所,笠岡市役所,岡山県庁,法務省岡山地方法務局,株式会社瀬戸内海放送,岡山放送株式会社,岡山ネットワーク株式会社,西日本電信電話株式会社(岡山支店),株式会社山陽新聞社,株式会社ホテルグランビア岡山,株式会社キャリアプランニング,株式会社中国銀行,税理士事務所,司法書士事務所,弁護士事務所の36の受入機関のご協力の下,46名の学生が就業体験をすることができました。
報告会では,学生委員会委員からの概要説明の後,今年度の履修学生の代表8名が,各受入先でのインターンシップの体験を報告しました。それぞれにとても貴重な経験をしてきたこと,そして彼等がその中で成長したことが実感できました。また,下級生に対してはしっかりした目的意識を持ってインターンシップへ臨んでほしいとのアドバイスが印象に残りました。










インターンシップ報告書
山陽新聞社
法学部3年 城仙剛史
志望動機:高校生の頃からジャーナリズムに興味があったこと、新聞が大好きなこと、社会経験を積みたかったこと以上の理由で私は就業体験先を新聞社に決めた。単純な動機である。面接では「新聞記者になるつもりなの?」という質問に対して「そんな気は全くありません」と答えてしまい、ひどく反感をかってしまった。今はまだ分からないので・・・という意味であったのだが、含蓄ない表現は使わぬが吉である。なぜパスしたのか未だに分からない。とにかく就業体験が始まった。新聞は普段から気になる記事、表現などはメモしていたので、事前準備は特に何もしなかったが、山陽新聞は一週間かなり丁寧に読んだ記憶がある。
研修内容:山陽新聞社は市役所、警察署、商工会議所などにその一室を借りて「記者クラブ」というものを構えている。それぞれ政治部、社会部、経済部として機能し、支社としての役割を果たす。今回の就業体験では岡大ほか三大学の学生が集まり、計六人が三組になって各部署をローテーションしてまわった。基本的にどの部署でも、1.挨拶 2.その日の取材説明 3.取材同行 4.部署に帰って記事作成 5.添削というパターンであった。若干の違いはあるが、概ね上記の展開で毎日が過ぎていった。毎回担当の記者が変わり、その都度(取材の移動中などに)話される視点が変化するので、就業体験中のささやかな楽しみであった。取材に同行させて頂いた後は専用のパソコンで試行錯誤しながら記事を書き、鬼のように添削を受けるのであるが、その作業は非常に楽しいものだった。実際の記者が書いた記事にはとても敵わないが、たかだか三十行程度の記事に、読みやすいようどれだけの時間がかかっているかを知り、新鮮な驚きが生まれた。
感想:慣れない環境では体調を崩しやすい。職場の雰囲気はそうでもないのだが、私は初日から緊張しっぱなしで三日間はずっとお腹を壊して過ごした。今考えるとある程度失礼でも学生という身分で許されることをフルに活用してもっと貪欲に新聞社についての疑問やシステムについてぶつけていけばよかったのであるが、萎縮してしまった。また、新聞社に関わらず社会は非常に厳しい世界であると当たり前のことを思い知らされた。学生がいかに恵まれていることか・・・。全力で勉強出来るのも、思い切り遊べるのも、正に学生の間だけであると痛いほど感じた。今回の体験では将来を見据えるいい機会になったと同時に、限りある学生生活をもっと有意義に過ごす重要性を改めて思った。
最後に、このような貴重な体験を与えて下さった大学の先生がた、経営者協会の皆様、そして人事百般ご教授頂いた山陽新聞社の方々、この場をかりてお礼申し上げます。誠にありがとうございました。
岡山県生活環境部文化振興課、岡山県立美術館、岡山県天神山文化プラザ
法学部3年 永野 貴史
私は、岡山県生活環境部文化振興課で4日間、県立美術館で3日間、天神山文化プラザで3日間、計10日間就業体験をさせていただきました。インターンシップに参加した動機は、社会というものを体感して、将来社会に出て行くために必要なことを実体験を交えて学びたい、また、希望の進路が公務員であることから、実際に公務員の職場を体験し目標を明確にしたいというものでした。実習前の連絡で、事前訪問、事前学習は不要だと担当の方に言われていたので、事前に取り組んだことといえば、県のホームページに目を通す程度のことでした。しかし、どの研修先でもまずその業務概要、方針等を説明していただき、特に美術館、文化プラザでは、当該施設の理念、特徴なども説明していただいたおかげで、実際に業務体験をさせていただく際には、説明していただいたことを念頭に置きながら、スムーズに、かつ、自分が行っている業務の意味をよく理解しながら行うことができ、大変有難かったです。
県立美術館、天神山文化プラザでの実習では、公的文化施設の特徴として施設管理・運営業務が挙げられるため、当施設の職員の方々は通常の行政業務に加えてやや異なった独特かつ多様な業務も行っておられ、一人当たりの担当業務も多様で大変苦労なさっているように感じました。
文化振興課での実習中、「文化」とは何か、なぜ県行政が「文化」を業務に取り入れているのか、という難問について、職員の方に指導していただきました。「文化」とは「暮らしのあり方」そのもの、すなわち衣食住であり、このうち、受け継がれるものは伝統文化になり、高尚なものになると芸術文化にもなります。この暮らしの水準、レベルを高めることは、県民の福祉になり得ることから、県は「文化」を業務に取り入れているのです。近年、文化振興の重要性が主張されていますが、国民の生活をより良いものにすることを目的とする行政サービスと行政が文化振興を行うこととは密接な関係にあることを、実習を通じて理解することができました。
実際の業務体験で最も印象に残ったのは、天神山文化プラザでのワークショップの補助でした。参加者の方々にとっては私も正規の職員として認識されており、職員の方のお手伝いをしているという形ではなく、限りなく本物に近い業務体験ができたように感じられ、大変有意義でした。
私は、今回のインターンシップで職員の方々から様々なものを見聞きさせていただき、自身の見識を広げることができたと確信しています。2週間という短い期間でありながらも社会に飛び込んでみたことで、社会に出るためには、広い視野・勉強・コミュニケーション能力・規範意識など、様々なことが必要であり、自分に欠けている部分が多々あると感じました。残りの大学生活では、これを意識して将来に向けて成長していけるよう努めていきたいと思っています。
最後になりましたが、ご多忙の中、親切に指導してくださった文化振興課、県立美術館、天神山文化プラザの皆様、また、このような貴重な体験の機会を与えてくださった法学部学生委員会の皆様、その他関係者各位の皆様に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
岡山市役所市民局文化振興課
法学部3年 大盛真緒
私は、「まちづくり」に関わる仕事がしたいという気持ちから、ただ漠然と公務員を志望していました。そこで、実際に市役所の仕事を体験し将来の進路決定の参考にしたいと思い、インターンシップに参加させていただきました。文化振興課は、市民と協働するかたちで「おかやま音楽祭」などの文化事業を行っており、文化振興という面からまちづくりを考えることに大変興味をもちました。
実習前には、文化振興課のホームページや文化施設のパンフレットに目を通しました。実習が始まってからも多くの資料をいただいたので、家に帰ってから毎日資料調べをしました。
実習では、ブレインストーミングという手法を用いながらインターンシップ生で、宣伝のためのラジオ原稿やイベントで配る歌詞カードを作る機会を与えていただきました。お互いの意見を言いあうことはとても刺激的で、実際に私達の考えたものが「かたち」になることに大きな喜びを感じました。また、イベント運営のお手伝いでは、まさに現場での臨機応変な対応が要求されました。その他にも、細かい事務作業や文化施設の裏側を教えていただいたり、「仕事」のあらゆる面を体験させていただきました。そしてイベントの華やかな表舞台の裏側にある、それを支える多くの仕事が見えてきました。宣伝から打ち合わせ、当日の運営、その後の報告、文化施設の管理・維持も大変な仕事でした。最終日には「地域文化を振興する意義」をテーマに課の方々の前でレポート発表を行い、自分の考えをわかりやすく伝えることの難しさを痛感しました。このような体験をすることで、「想像力」の大切さを学びました。どんなに小さなことでもこういうことが起こるかもしれないなどと、物事をあらゆる面から見、判断し、そして想像することは、今後何をするときにも必要であると感じました。
市役所の仕事は、私のイメージしていたものとは大きく違っていました。文化振興課では、イベントが多いことから現場での仕事や市民の方々と直接話し合う機会を多く持っていました。一体となってイベントに取り組む姿は、私にとってとても魅力的であり、地方分権の進む今の市役所の姿であると感じました。
インターンシップ参加前に、自分自身への目標として「受身にならず、今感じ、学び取れることを最大限に吸収すること」と決めました。不安はありましたが職員の方々が本当に優しく、質問にも多く答えていただき、とても充実した2週間となりました。インターンシップに参加することで、目標が明確になり、それに向かって頑張るエネルギーをいただきました。課の方が、「‘想像力’と‘素朴な疑問’、そして‘普通の一般市民の目線’をなくさないでくださいね。」と最後にいってくださいました。そのことを忘れず、今後も目標にむかって頑張りたいです。
最後になりましたが、お忙しい中、未熟な私を受け入れてくださった文化振興課の皆様、このような貴重な機会を与えてくださった岡山県経営者協会の皆様、岡山大学法学部学生委員会の皆様に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
株式会社中国銀行
法学部3年 寄国麻衣
私は、8月28日から9月8日までの2週間、株式会社中国銀行でインターンシップを体験させていただきました。就職を考えるにあたり、銀行に興味があり、実際に内部を見て多くの事を知りたい、経験してみたいと考えていたので、今回インターンシップに応募しました。
インターンシップにあたって、事前にいただいた中国銀行のディスクロージャー誌や、銀行やローンなどについての数種類のパンフレットに目を通しましたが、正直な話、満足いくほどの準備ができていたとは言えません。ただ、この2週間で実際の行員の方々から様々なことを学びたい、吸収したいという思いがあり、受け身でなく積極的に参加したいと思っていました。
実習生は全員で10人でしたが、最初はとにかく緊張して不安だらけでした。しかし、常に担当の方々が和やかな雰囲気を作ってくださり、緊張も解けて楽しく実習することができました。実習の内容は、思っていたよりも広く深い範囲のものでした。1週目は、銀行業務やマナーなどの基礎知識や、資産運用について、また銀行内の見学や他の支店の見学などを行いました。マナーでは、実際のお客様へのご案内やお茶出しも経験させていただきました。資産運用では、金融商品をFAの方を相手に販売説明するロールプレイングをしました。2週目は、個人ローンや事業性融資、商品開発などの講義と演習でした。1週目よりも内容は専門的になり、理解するのに必死でしたが、「わからないことは、どんな小さなことでもいいから質問しよう」など言っていただき、本当に言葉の意味でさえも丁寧に教えて下さいました。演習では、具体的な金額を計算して見積書を作る手順を習いました。
私は、「お客様あっての銀行」ということを強く感じました。ただお金に関する業務をしているのではないということが新発見でした。短い時間であっても、その時間内でいかにお客様に好印象を持ってもらえるかが大切だと学び、その積み重ねが、お客様の銀行に対する信用や信頼関係を築くのだと感じました。お金は誰にとっても大切なものであり、やはり信頼できる人に任せたいと思うものです。その大切なお客様のために、どのような資金運用をするのがいいのか、多面から検討することの大切さを実感し学べたと思います。
今回のこの経験は、大学生活はもちろん、今後社会に出ても役立つものであると思います。社会に出て働くことの厳しさや責任など、今まで私が思っていたものよりはるかに重大なものだと思いました。また、経済や金融に対してますます興味が深まったので、これから積極的に新聞などに目を通して触れていきたいと思います。そして、将来を考える際の参考にしたいです。毎日が新鮮で本当に貴重な経験ができ、普段聞けないお話をしていただき、様々なことを吸収できたのではないかと思います。
最後になりましたが、大変お忙しい中、私を暖かく受け入れて下さり、丁寧に指導してくださいました藤原調査役、水田さん、江木さんをはじめとする中国銀行の皆様、またこのような貴重な機会を与えて下さった岡山大学法学部学生委員会の皆様、岡山県経営者協会の皆様、その他関係者各位の皆様に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
太陽綜合法律事務所
法学部3年 青田 夢
私は、この度のインターンシップで太陽綜合法律事務所に2週間お世話になりました。私が、今回インターンシップに参加させていただいたのは、目指している弁護士という職業がどのようなものなのか実際に見たことがなく、「とにかく見てみたい。」それが一番の理由でした。そして、弁護士の実際の仕事を見ていく中で、自分自身を感化させたいという思いもありました。
しかし、そのやる気の反面、インターンシップにあたり事前に取り組んだことといえば、民法の参考書を読んだ程度でした。今思えば、事前に、民法はもちろんのこと、民事訴訟法や商法、会社法の教科書までしっかり読み、知識の復習をした上でインターンシップに臨めばよかったと悔むばかりです。
事前の準備不足のせいもあってか、実習が近づくにつれ、実習への意欲や期待よりも不安ばかりが頭をよぎるようになりました。しかし、実際実習が始まってみると、先生方の人柄のよさと弁護士の業務に同行できる楽しさで不安など感じている暇もありませんでした。実習中は法律相談に立ち合わせていただくのが主な内容でしたが、その他にも接見に同行させていただいたり、管財事件における業務も見せていただいたりと、普段一般人としては見ることもできないような弁護士の業務も見せていただき、本当に貴重な経験となりました。特に管財事件については、驚きの連続でした。弁護士がこんな仕事までするのかと、弁護士の仕事の新たな一面を見ることができたように思います。
今回、インターンシップに参加し実際に弁護士の業務に触れて、自分の知識のなさを痛感すると同時に、多くのことを学ぶことができました。法律の解釈や適用の仕方といった学問的なことは勿論のこと、弁護士という職業の持つ魅力やその大変さ、弁護士としての姿勢、弁護士にとって大切なもの等々、一言では言い切れないほど多くの机上では学べないことを得ることができ、それは私の大きな財産となっています。普段身近に接することのない弁護士の先生方と様々なお話をさせていただいたり、先生方同士の会話をお聞きしたりするうちに、理想や想像のものではない本当の弁護士の姿を知り、それまで私の中にあった弁護士像は見事に打ち崩されました。そして、それが打ち崩されたことで、新たに具体的な目標を持つことができるようになりました。今までは漠然と「人の役に立つような弁護士」になりたいと思っていただけでしたが、インターンシップを終えた今、人から信頼され、何かあればあの先生のところにいこうと一番に頭に浮かぶ、そんな弁護士になりたいと強く思っています。まさしく太陽綜合法律事務所の先生方のような・・・。そして、その具体的目標は今後の学修の原動力となることは間違いありません。
最後になりましたが、お忙しい中未熟な私に沢山のことを教えてくださった近藤先生、藤原先生、上西先生、藤田先生、河本先生と、いつも笑顔で優しく接してくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちが尽きません。また、相談に同席することを快く許可してくださいました依頼者の皆様、このような貴重な機会を与えてくださったインターンシップ実行委員会の先生方にもこの場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
横田法律事務所
法学部3年 井筒智子
私は今回のインターンシップで横田法律事務所にお世話になりました。私は、以前から漠然とロースクールに進学して法曹を目指したいと考えていました。しかし、新旧に関わらず司法試験突破は非常に厳しく困難な道のりでありますし、このまま強い意志も持たずボーっとしていても何も始まらない事は自分でもよく分かっていました。また、このままの状態でロースクールに進学してもモチベーションを高く維持できるか非常に不安でした。
インターンシップへの参加を決めたのは、法律事務所で体験する全ての事に基づいて自分が「弁護士になりたい」「弁護士になるために、もっと勉強しなくちゃいけない」と強く思えたら、きっとモチベーションを高く維持しながら勉強できるはずだと考えたからです。実習前は、先生のアドバイスもあったので司法試験の過去問を解こうと努力しましたが無理でした。勉強が全然足りないと痛感させられた実習前数週間でした。
実習中は、たくさんの事件資料を閲読させていただいたり、債務引受弁済契約書の作成にも挑戦させていただいたりして本当にたくさんの事を体験させていただきました。実習1日目は、事件記録を読むのも、何をどう読めばいいかがさっぱり分からず大変悔しい思いをしましたが、先生が丁寧に教えてくださったおかげで実習6日目あたりからは少しずつ要領よく読めた気がします。
特に印象に残っているのは、先生が依頼者と共に陳述書を作成する席に同席し、資料の整理や作成の補助作業をさせていただいた事です。原告が証拠として提出している資料の文章一文一文に丁寧に反論していく作業は先生の真剣さと熱意が伝わってきて、同席できたことは非常に有意義でした。また、依頼者の話の要点をつかんで、裁判所が求める文章に仕上げていく作業はとても面白いと感じました。
大学の授業では今まで民事訴訟法や刑事訴訟法は教科書を読んでも全然実感を伴うことができず、結果、用語も裁判の流れも全然覚えることができませんでしたが、実習中に事件記録を読んだこと、先生がわざわざ実習に日程が合うように入れて下さった刑事裁判を傍聴したことで、単語に意味を持たせて読むことができるようになったことは大きな収穫でした。また、法律を巡る争いは日常的に起こっており身近なものだということにも気付きました。
実習では、先生から色々な事を教えていただきましたが、勉強不足のため消化不良に陥り大変悔しい思いをしました。司法試験の壁の高さと自分の勉強不足を痛感した9日間でした。
「勉強しよう」という意志をもつことは、インターンシップ参加の目的の一つでもあったので参加して本当に良かったと思います。また、勉強面だけに限らず得たものはとても多く、先生には感謝の気持ちでいっぱいです。
最後にはなりましたが、お忙しい中私を受け入れてくださり親切にしてくださった横田事務所の皆様、同席することを許してくださった依頼者の皆様、このような機会を与えてくださった大学の先生方、本当に貴重な体験ができました。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
岡山県司法書士会
法学部3年 雨河 宏尚
私は、司法書士の実務、日常を実際に自分の目で見て学習し、体験したいと思い、インターンシップに応募しました。実務を具体的にイメージできることは、資格取得に向けて勉強していく上で必ず有益になると思ったし、実情をより詳しく知ることで、勉強に対する意欲の向上につながると思ったからです。振り返ると実際には、それ以上のものを得ることができたと思います。司法書士業務の魅力や大変さを知ることで理解を深めることができたし、業務に対する事務所の方々の取り組みを見て、実務の重要性、実務をする上で重要なことを学ぶことができ、非常に有意義な経験をすることができました。
今回、私は佐野司法書士事務所にお世話になりましたが、実務上、佐野先生が多く扱われている債務整理の相談に来られる依頼者が多く、その相談内容も実に様々でした。そうしたなかで、先生は、債務の現状と今の依頼者の経済状況等を事細かに聞かれ、依頼者に応じたアドバイスをされていました。その上で、依頼者とよく相談し、とるべき解決方法を提案されていました。このように、単に業務をこなすことが実務ではなく、その前提として、法律相談等を通じて依頼者との信頼関係を築き上げること、依頼者に応じた柔軟な対応ができるように準備をしておくことが重要な仕事であると感じました。
また、今回の研修中では、債務整理の一環としての不動産売買取引の立会いにも同席させていただきました。取引、立会い自体は手筈どおり進みましたが、その取引を成功させるまでに事務所の方々は大変な労力を費やされていました。そして、立会い後は事務所に戻り、登記申請書作成、添付書類の確認を全員で、本当に迅速かつ正確に行っておられました。その一連の流れの早さ、確認作業の徹底さには驚きました。この機会でしか体験しえない実務の重要性を肌で感じることができたと思います。また、無事に申請を終えた後の事務所の方々のほっとした表情がとても印象的で、これも責任をもって仕事に取り組まれた結果の充実感なのだろうな、と思いました。
今回のインターンシップを通じて、司法書士の魅力、やりがいを感じましたが、とりわけ、業務の厳しさを痛感したと思います。膨大な知識が必要となるのはもちろん、内容次第では、依頼者の人生を左右しかねないので、とても責任が重く、ミスは許されません。しかし、このような厳しさを知ることで、あるべき司法書士の姿を学ぶことができたと思います。このことが、今回の実習での一番の収穫であると考えています。また、この機会で学び、感じたことは絶対に忘れないし、目指すべき資格取得のはっきりとした動機となったと思います。今回、インターンシップに参加して本当によかったと思っています。これも一重に、お忙しい中、温かいご指導をして下さった事務所の方々、そして法学部学生委員会の先生方のおかげです。深く感謝し、心より御礼を申しあげます。本当にありがとうございました。
岡山県司法書士会
法学部3年 岩本裕香利
私は今回、入江司法書士事務所で二週間のインターンシップをさせて頂きました。司法書士事務所での実習を希望したのは、私が進路の選択肢として考えていた司法書士の業務を実際に自分自身の目で見て、そして体験することで司法書士という職業をより深く知りたいと思ったからです。実習前には登記法を復習する以外に特別なことはしていなかったので、実習への不安はありました。しかし登記を行う上で必要な謄本等の書類を法務局で取るといった初歩的なことから、申請書の書き方、法務局への登記申請など登記の一連の流れを入江先生に詳しくご説明頂いたため、徐々に理解することができました。今までは登記申請に必要な書類といってもテキストを丸暗記するだけでしたが、今回の実習によってなぜこの登記にこの書類が必要なのかという理由の部分が分かったことで登記法の勉強が以前より面白く感じられるようになりました。
業務内容には所有権移転登記をはじめ様々なものがありましたが、自分と最も身近に感じたのは相続登記でした。ご遺族の方のお話を伺い、それに基づいて登記を行うという業務の中で司法書士が「町の法律家」と言われ、市民に近い存在であることを改めて感じさせられました。司法書士は遺族に代わって相続登記を行うことで、亡くなった方やご遺族の意思を形にするための非常に重要な役割を果たしているのだと思います。また相続登記は相続人が誰になるのか、遺産分割協議書や遺言書があるか否かによって登記の方法・登録免許税の額などが大きく異なります。このような事情を考慮した上で、遺族にとって最も負担の軽い方法での相続を提案することが司法書士には求められるのだと学びました。
さらに、銀行での決済にも何度か同行させて頂きました。決済は不動産の売買などにおいて所有権が動き、それに伴い売買代金も動く手続きが行われる場なのですが、登記の権利者・義務者の方々が揃う中で、手際良く署名や印鑑を頂いたり、その登記に必要な書類が揃っているかを確認したりする先生の姿に感動し自分もいつか先生のようになりたいと思いました。決済は、その場で多額のお金が動くためにミスや遅れが決して許されないそうです。司法書士という職業には大きな責任が伴うことを痛感させられました。また、最終日には実際に一連の決済を私に任せて頂くという非常に貴重な体験をさせて頂きました。
今回のインターンシップで司法書士の業務には実に様々なものがあることを知りました。私が特に印象に残っているのが「100人の司法書士がいれば100通りのやり方がある」という先生の言葉です。私は今まで司法書士のイメージを掴むことができなかったのですが、司法書士とはこのようなものと決め付けること自体が不可能であるのだと知ったことで、幅広い業務を行うことの出来る司法書士という職業にさらなる魅力を感じることが出来ました。今回の実習で得た様々な経験や知識を今後の勉強に活かしたいと思います。
最後になりましたが、大変お忙しい中、私のために時間を割いて熱心にご指導いただきました入江司法書士事務所の皆様、そしてこのような機会を与えてくださった法学部学生委員会の皆様に深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。