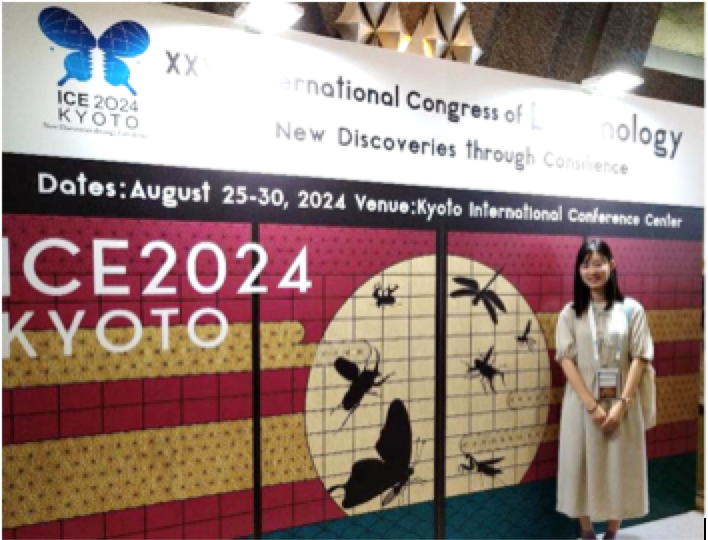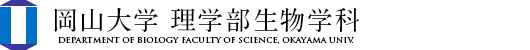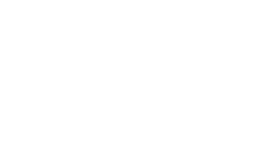ホーム > 修了生・同窓生の方 > 生物学科の学生活動報告(寄付金報告) > 生物学科の学生活動報告(寄付金報告2024)
生物学科の学生活動報告(2024年度寄付金報告)
2024年に生物学科の卒業生より、生物学科の学生奨学と研究のための寄付金を受け入れました。この寄付金による学生および大学院生の活動をこのページで報告させていただきます。ここでは学生が筆頭で発表する国内外の学会の参加報告、学生がファーストオーサー(筆頭著者)となっている論文の学生本人による紹介文、各研究室の活動などが掲載されます。#4 第50回日本神経内分泌学会学術集会での発表(神経行動研究室・博士前期課程・兼光 匠)
2024年10月26〜27日に、埼玉県さいたま市RaiBoC Hallレイボックホールで第50回日本神経内分泌学会学術集会に参加し、「オスの性機能に関わる腰髄-視床室傍核ガストリン放出ペプチドニューロン系」というタイトルで口頭発表を行いました。雄ラットの脊髄には脊髄レベルで射精を制御する脊髄ガストリン放出ペプチド(GRP)ニューロン群が存在します(Sakamoto et al., Nat. Neurosci, 2008)。私はアデノ随伴ウイルスベクターとCre-LoxPシステムを活用し、脊髄GRPニューロンを軸索末端まで蛍光タンパク質で標識することで、脊髄GRPニューロンが全ての感覚情報を統合する視床領域に存在する室傍核に投射することを発見しました。また、GRP受容体発現ニューロンが赤色蛍光タンパク質で標識される遺伝子改変ラットを用いて視床室傍核のGRP受容体発現ニューロンが射精後に活性化されることを発見しました。 初めて全国大会に参加し、大変緊張しましたが、全国各地の先生方や学生の発表を聞くことや、ディスカッションを通じて、自分の今後の課題を見つけることができました。本学会への参加にあたっては、生物学科にご寄付いただいた予算を活用させていただきました。おかげさまで大変貴重な経験を得ることができました。これを励みに今後も研究活動に邁進していきたいと思います。
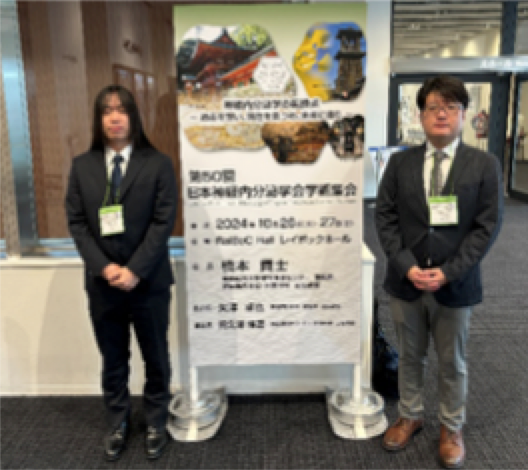
#3 日本分子生物学会第47回年会参加記 (分子機能研究室)
2024年11月27-29日に日本分子生物学会年会が博多市で開催され,M2 学生4名がポスター発表を行いました.学会参加の費用は,生物学科への寄附金を活用させていただきました.以下,学生の発表題目と学会参加の感想です.
【大常】小分子ペプチドを介したショウジョウバエオス附属腺細胞の機能分化
本学会で,哺乳類の生殖器官の研究者や,肝臓や腎臓の研究者と活発な交流を持つことができました.これにより,昆虫と哺乳類の基礎研究をつなぐ橋渡し役になることができたと考えています.さらに,私が注目していた遺伝子を長年研究されている先生方からご指導いただける機会にも恵まれ,現在の研究に大いに活かすことができています.
【白樫】ショウジョウバエのオス附属腺における脂質輸送を介したストレス応答機構
幅広い分野の研究者の方々がポスター発表を見に来てくださり,ディッスカッションを通して自身の研究に対する理解が深まりました.また,他の研究者の発表も聞くことができ,新しい知識を得たり視野を広げたりすることができました.貴重な機会をいただきありがとうございました.
【城尾】ショウジョウバエ筋肉細胞における転写制御因子Dveの機能解析
ポスター発表では,幅広い専門分野の方から助言をいただき,その後の研究への視野が広がりました.また,他分野の発表を理解する難しさを実感し,自身の未熟さを痛感しました.この経験を通じて,研究に限らず柔軟な思考や学び続ける姿勢の大切さを学びました.ご支援をいただいたおかげで貴重な機会を得られたことに心より感謝申し上げます.
【高田】ショウジョウバエ雄の求愛行動制御に関わるdve 発現細胞
専門領域を問わず多くの研究者の方々から助言を頂き,有意義で楽しい時間を過ごすことができました.会場には興味深い研究テーマが数多く並んでおり,実験アプローチや考察の視点は多種多様で,自身の研究にも繋がる学びを得られたと感じています.学会を通じたこれらの貴重な経験は,今後の研究における大きな励みとなりました
#2 学科OBによるセミナーと研究交流会の開催 (植物発生研究室・本瀬宏康)
2024年9月26日に生物科学セミナーと研究交流会を開催しました。セミナーでは「植物細胞の分裂面はどのようにして決定されるか?」について、最新の研究成果を名古屋大学の高谷彰吾博士(生物学科OB)にお話ししていただきました。細胞が分裂する位置を決める微小管という中空のタンパクの繊維がいったん細胞内でランダムに配置され、それまでの空間情報がキャンセルされることが重要、という意外な結果について活発な議論が行われました。
セミナー後は、さまざまな分野で研究を行っている学生・若手スタッフによる簡単な研究紹介を交えつつ研究交流会を行い、議論と交流を深めました。約30名の参加があり、日頃は会う機会が少ない人とも交流ができ、楽しかったというコメントを多くいただきました。この場をお借りして、このような場が寄付金にて援助をいただきまして御礼申し上げます。学科OBによるセミナーとあって在籍学生への影響も大きかったのではと思います。今後もこのような機会をいただければ実施してみたいと考えております。
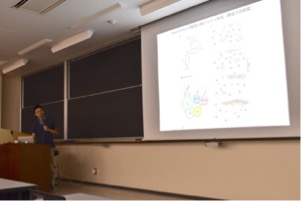
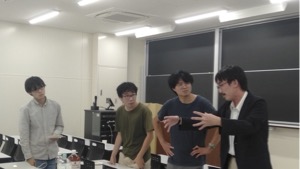
国際昆虫学会議(ICE2024Kyoto)参加記 (時間生物学研究室・博士前期課程・相川紗英)
2024年8月25日~30日に、京都国際会館で国際昆虫学会議(International Congress of Entomology)が開催されました。国際昆虫学会議は、昆虫学における最も包括的な国際会議で、1910年にベルギーで開催されて以来(第二次世界大戦の時期を除く)、ほぼ4年ごとに開催されてきました。日本では1980年に京都で開催されています。本会議では、日本学術会議との共同主催となり、開会式は秋篠宮皇嗣同妃両殿下御臨席のもと、厳かに挙行されました。82の国と地域から4,041名が参加しました。
私は”Flies with circadian activity rhythms have a better chance of survival.”という題で、キイロショウジョウバエを用いた概日リズムと生存競争についてポスター発表を行いました。国内外の著名な研究者から助言をいただき、自身の研究に対する理解を深めることができました。イベントブースには、折り紙やヨーヨーすくい、駄菓子などが設けられていました。会場で知り合った研究者と日本らしいアイテムでコミュニケーションを取ることができ、楽しい時間となりました。参加費等の一部は、生物学科にご寄付頂いた予算を活用させて頂きました。多額の寄付金を頂戴し、心より感謝いたします。おかげで貴重な経験を得ることができました。本学会で得た学びを今後の研究活動に活かしたいと思います。