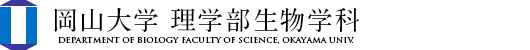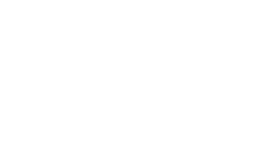ホーム > 修了生・同窓生の方 > 生物学科の学生活動報告(寄付金報告)
生物学科の学生活動報告
2024年に生物学科の卒業生より、生物学科の学生奨学と研究のための寄付金を受け入れました。この寄付金による学生および大学院生の活動をこのページで報告させていただきます。・学生が筆頭で発表する国内外の学会の参加報告
・学生がファーストオーサー(筆頭著者)となっている論文の学生本人による紹介文
・各研究室の活動
・奨学金授与者の研究紹介 などが掲載されます。
年度別のこちらのリンクからどうぞ。
生物学科の学生活動報告(寄付金報告2024)
生物学科の学生活動報告(寄付金報告2025)
奨学金受賞者の研究紹介(2025)