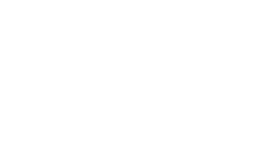H4:2025年度
ID:20250918
AP:談話会『過去・現在・将来における 北極温暖化増幅のメカニズム:統合的理解に向けて』吉森正和 先生(2025.09.18)
AM:談話会『過去・現在・将来における 北極温暖化増幅のメカニズム:統合的理解に向けて』
TR:講師:吉森正和 先生(東京大学大気海洋研究所)
TR:日時:令和7年9月18日(木)16:00~(質疑込み1時間程度)
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
PS:この談話会は大学院集中講義(地球科学特別講義Ib)の一環として開催するものです。履修登録している院生は必ず出席してください。
ID:20250908
AP:談話会『めざせマントル!ペリドットから超深海底への潜航へ』道林克禎 先生(2025.09.08)
AM:談話会『めざせマントル!ペリドットから超深海底への潜航へ』
TR:講師:道林克禎 先生(名古屋大学)
TR:日時:令和7年9月8日(月)16:00から1時間程度
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
PS:この談話会は大学院集中講義(地球科学特別講義Ia)の一環として開催するものです。履修登録している院生は出席してください。
ID:20250904
AP:談話会『環境試料に含まれる水銀の“履歴”を読む:同位体分析による追跡とその応用』山川茜 先生(2025.09.04)
AM:談話会『環境試料に含まれる水銀の“履歴”を読む:同位体分析による追跡とその応用』
TR:講師:山川茜 先生(国立環境研究所)
TR:日時:令和7年9月4日(木)16:30~(質疑込みで50分程度)
TR:場所:理学部本館3階 31講義室
TR:概要:本談話会では、水銀の環境中でのふるまいに関する基礎的な話から始め、同位体分析によって水銀の起源や環境中での挙動をどのように追跡できるかを紹介します。 これまでの研究事例や現在進行中のプロジェクトを交えながら、環境試料の前処理や分析精度管理の工夫についても触れます。 最後に、私が担当している環境標準物質の開発・活用についても簡単にご紹介します。
PS:興味のある人はぜひご参加ください。
H4:2024年度
ID:20240910
AP:談話会『大気エアロゾルの健康影響-黄砂・PM2.5・バイオエアロゾル』小島知子 准教授(2024.09.10)
AM:談話会『大気エアロゾルの健康影響-黄砂・PM2.5・バイオエアロゾル』
TR:講師:小島知子 准教授(熊本大学)
TR:日時:令和6年9月10日(火)16:30から1時間程度
TR:場所:理学部本館2階 23講義室
PS:本談話会は9月9日(月)6限~9月11日(水)4限に開講される大学院集中講義「地球科学特別講義IIb」の一環として行われます。大学院生向けの授業ですが、学部生でも参加できます(ただし単位は出ません)。興味のある人はぜひご参加ください。
ID:20240905
AP:談話会『氷岩石微惑星の集積成長と熱進化』木村淳 先生(2024.09.05)
AM:談話会『氷岩石微惑星の集積成長と熱進化』
TR:講師:木村淳 先生(大阪大学理学研究科)
TR:日時:令和6年9月5日(木)13:30~(質疑込みで90分程度)
TR:場所:理学部本館2階 24講義室
TR:内容:太陽系天体が持つ多彩な特徴、特に内部構造の多様性の起源を理解することにおいて、その初期状態となる微惑星の進化は重要な鍵となる。隕石やリターンサンプルは微惑星の熱史を記録しており、最近はその分析を通して経験温度やその時期が次第に明らかになりつつある。我々は、氷岩石微惑星の水質変成と集積成長・衝突加熱、加熱脱水や内部対流を考慮し、天体成長と内部分化に至る固体天体の初期進化を記述する数値モデルを開発している中で、今回はリュウグウ試料から推定された母天体の温度(低温)環境や、鉄隕石の起源となるM型小惑星の高温環境を説明するモデル計算例を紹介する。
PS:この談話会は、集中講義「地球科学特講Ⅰ」に合わせ開催されます。興味ある方は誰でもご参加ください。
ID:20240828
AP:談話会『氷期の気候変動と大西洋深層循環』岡顕 准教授(2024.08.28)
AM:談話会『氷期の気候変動と大西洋深層循環』
TR:講師:岡顕 准教授(東京大学大気海洋研究所)
TR:日時:令和6年8月28日(水)16:00から1時間程度
TR:場所:
理学部本館3階 31講義室
※台風のためオンラインに変更
PS:地球科学特講2の一環として、教室談話会を行います。どなたでも自由に参加できますので、ぜひご参加ください。
H4:2023年度
ID:20240110
AP:談話会『氷衛星のクレーター年代学(仮)』Emily Wong 先生(2024.01.10)
AM:談話会『氷衛星のクレーター年代学(仮)』
TR:演者:Emily Wong 先生 (ELSI)
TR:日時:令和6年1月10日(水)13:30~14:30
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
TR:内容:衝突の記録であるクレーターを用いて太陽系の力学進化を解き明かす話(たぶん)。
PS:言語は英語になると思いますが、Emilyさんは日本語もだいたい理解するので、質問は日本語でも可。誰でも参加可。
ID:20231128
AP:Workshop on Interiors of planetesimals and terrestrial planets(微惑星と地球型惑星の内部ワークショップ)(2023.11.28)
AM:Workshop on Interiors of planetesimals and terrestrial planets(微惑星と地球型惑星の内部ワークショップ)
TR:日時:令和5年11月28日(火)13:30~17:20
TR:場所:理学部本館2階 23講義室
TR:内容:国内外の研究者を招いて微惑星や地球型惑星の内部分化や進化に関する発表会です。詳細は
プログラムをご参照ください。
PS:学生・教職員どなたでも自由に参加できますので、興味ある方はぜひご参加ください!
途中のみの部分的な参加も歓迎します。
ID:20230922
AP:談話会『FIB-TEMを使った研究紹介』三宅亮 先生(2023.09.22)
AM:談話会『FIB-TEMを使った研究紹介』
TR:講師:三宅亮 先生(京都大学)
TR:日時:令和5年9月22日(金)11:45~12:35
TR:場所:理学部本館2階 22講義室
PS:大学院講義「地球科学特別講義Ia」(鉱物学)に伴って、三宅先生に談話会を行って頂きます。興味のある方はご参加ください。よろしくお願いいたします。
ID:20230914
AP:談話会『接地境界層での乱流と大気の光学的ゆらぎの観測』玉川一郎 教授(2023.09.14)
AM:談話会『接地境界層での乱流と大気の光学的ゆらぎの観測』
TR:講師:玉川一郎 教授(岐阜大学)
TR:日時:令和5年9月14日(木)16:00から1時間程度
TR:場所:理学部本館2階 24講義室
PS:本談話会は 9/13(水)午後~15(金)午前 に開講される大学院集中講義「地球科学特別講義Ib」の一環として行われます。大学院生向けの授業ですが、学部生でも参加できます。貴重な機会ですので、興味のある人はぜひ参加して下さい。
ID:20230905
AP:談話会『海洋資源の開発と環境影響評価』鈴木淳 先生(2023.09.05)
AM:談話会『海洋資源の開発と環境影響評価』
TR:講師:鈴木淳 先生(産業技術総合研究所 地質情報研究部門 海洋環境地質研究グループ)
TR:日時:令和5年9月5日(火)16:30から1時間程度
TR:場所:理学部本館3階 31講義室
PS:※この談話会は,集中講義「地球科学特講 4」の授業の一環として開催するものです。授業履修生は必ず出席してください。
鈴木先生は、タイトルにもある通り、海洋資源開発やそれに伴う海洋における環境影響評価などの研究を進められています。また海洋(主にサンゴ礁)の炭素循環やサンゴ年輪気候学などもご専門です。ご自由にご参加下さい。
ID:20230821
AP:談話会『高温高圧下中性子回折実験の現状と鉄水素化反応に与える軽元素などの影響』鍵裕之 教授(2023.08.21)
AM:談話会『高温高圧下中性子回折実験の現状と鉄水素化反応に与える軽元素などの影響』
TR:講師:鍵裕之 教授(東京大学大学院理学研究科・地殻化学実験施設)
TR:日時:令和5年8月21日(月)16:00-17:30
TR:場所:理学部2号館4階 第9講義室
PS:集中講義に合わせて,教室談話会を上記の日時に開催します。
鍵先生のご専門は,地球化学と地球内部物性です。
ID:20230511
AP:談話会『完新世におけるサンゴ礁地域の地形形成と生態系の変遷史』佐野亘 助教(2023.04.18)
AM:談話会『完新世におけるサンゴ礁地域の地形形成と生態系の変遷史』
TR:講師:佐野亘 助教(教育学部理科教育講座地球領域(地学))
教育学部のHP
TR:日時:令和5年5月11日(木)16:00-質疑応答含め1時間程度を予定
TR:場所:理学部本館3階 31講義室
PS:この4月から、教育学部の地球領域(地学)に新しく助教として佐野先生が着任されました。こちらに来られる前は九州大学に所属されていて、サンゴ礁など主に浅海域の地形形成などを研究されていました。
3月まで九州大学で学生でしたので、皆さんにも比較的身近な存在だと思います。今回、佐野先生にお願いして、講演を引き受けて頂きましたので、上記の内容で談話会を開催したいと思います。
教養科目や教職関係の授業はあるかもしれませんが、専門の授業がない時(木曜7-8限)を選びましたので、なるべく多くの方に参加してもらえれば、と思います。なお、参加は自由ですので、事前の連絡などは必要ありません。
お気軽にご参加ください!
H4:2022年度
ID:20220912
AP:談話会『ベンガル平野の水と堆積物のストロンチウム安定同位体(
88Sr/
86Sr)組成と風化の効率性』吉村寿紘 博士(2022.09.12)
AM:談話会『ベンガル平野の水と堆積物のストロンチウム安定同位体(
88Sr/
86Sr)組成と風化の効率性』
TR:講師:吉村寿紘 博士(JAMSTEC: 海洋研究開発機構)
https://www.jamstec.go.jp/biogeochem/member/yoshimura/index.html
TR:日時:令和4年9月12日(月)16:30から1時間程度
TR:場所:理学部本館2階 25講義室
PS:誰でも参加できます。(集中講義の履修生は必ず出席して下さい。)学部生も遠慮なく参加してみて下さい。
ID:20220905
AP:談話会『ハビタブル惑星の起源に迫る火星衛星探査計画MMX』倉本圭 教授(2022.09.05)
AM:談話会『ハビタブル惑星の起源に迫る火星衛星探査計画MMX』
TR:講師:倉本圭 教授(北海道大学)
TR:日時:令和4年9月5日(月)16:30から1時間程度
TR:場所:理学部本館3階 31講義室
TR:問合せ先:はしもとじょーじ
PS:2024年の打ち上げにむけて開発が進んでいるMMX計画について,その科学面を中心に紹介します。学部生から教員まで,誰でも参加可,です。
ID:20220810
AP:談話会『上部マントルの再肥沃化について―幌満かんらん岩の例―』高澤栄一 先生(2022.08.10)
AM:談話会『上部マントルの再肥沃化について―幌満かんらん岩の例―』
TR:講師:高澤栄一 先生(新潟大学)
TR:日時:令和4年8月10日(水)16:00~17:00
TR:場所:理学部本館2階 21講義室
PS:この談話会は,集中講義「地球科学特講1」の授業の一環として開催するものです。授業履修生は必ず出席してください。
ID:20220620
AP:談話会『地球上部マントルにおける水素挙動に関する実験的研究』櫻井萌 助教(2022.06.20)
AM:談話会『地球上部マントルにおける水素挙動に関する実験的研究』
TR:講師:櫻井萌 助教
TR:日時:令和4年6月20日(月)12:40~13:15
TR:場所:理学部本館2階 24講義室
TR:連絡先:野沢徹
PS:本年4月に着任された櫻井萌 助教にご講演いただきます。どなたでも自由に参加できます。興味のある方はぜひご参加ください。
H4:2021年度
ID:20211216
AP:談話会『エコンドライト隕石から知る原始惑星での火山活動について』山口亮 先生(2021.12.16)
AM:談話会『エコンドライト隕石から知る原始惑星での火山活動について』
TR:講師:山口亮 先生(国立極地研究所)
TR:日時:令和3年12月16日(木)10:45(3限目)から1時間程度
TR:場所:理学部本館1階 大会議室
TR:要旨:小惑星起源のエコンドライトは、太陽系誕生直後に存在した分化微惑星や原始惑星の生き残りであるとされる。現在回収されている隕石の中では5%ほどしか占めないが、太陽系初期の分化天体の進化過程を知る上で非常に重要な試料である。本セミナーでは、最近発見されたエコンドライト(Erg Chech 002)の成因について紹介したい。この隕石は、安山岩質隕石の一つであり、年代学的研究から太陽系最古の火山岩であることがわかった。安山岩質隕石はこれまで稀にしか回収されておらず、また、この岩石の分光学的特徴を持つ小惑星が現在のところ見つかっていないことから、現在の太陽系には非常に少ないタイプの岩石であると考えられる。これは、ほとんどの原始惑星が衝突により破砕され失われたためだと考えられる。これらの岩石を詳細に研究することで、太陽系最初期に形成した分化原始惑星の進化過程を知ることができる。
TR:世話人:寺﨑英紀
PS:どなたでも自由に参加できます。興味のある方はぜひご参加ください。
ID:20210902
AP:談話会『接地境界層乱流での気象観測とレーザー光の大気揺らぎ』玉川一郎 先生(2021.09.02)
AM:談話会『接地境界層乱流での気象観測とレーザー光の大気揺らぎ』
TR:講師:玉川一郎 先生(岐阜大学)
TR:日時:令和3年9月2日(木)15:30~16:30
TR:場所:オンライン
TR:概要:接地境界層での屈折率の揺らぎに関しては、Monin-Obukhovの相似則に基づく理論があり、レーザー光のシンチレーションの計測から、顕熱フラックスを評価するシンチロメータという装置が実用的に使われているが、ここでは、もう一度基礎に戻って大気乱流から光学揺らぎへと考える。
TR:世話人:野沢徹
PS:どなたでも自由に参加できます。興味のある方はぜひご参加ください。
H4:2020年度
ID:20201119
AP:談話会『水星の特異な磁場を作るダイナモのメカニズム』高橋太 准教授(2020.11.19)
AM:談話会『水星の特異な磁場を作るダイナモのメカニズム』
TR:講師:高橋太 准教授(九州大学大学院理学研究院)
TR:日時:令和2年11月19日(木)16:00~17:30
TR:場所:理学部本館1階 11講義室
PS:集中講義に来る,高橋先生に学科向けの談話会でお話をして頂きます。ふるってご参加下さい。
ID:20200901
AP:談話会『季節予報の社会実装に向けた気候形成・変動研究』植田宏昭 教授(2020.09.01)
AM:談話会『季節予報の社会実装に向けた気候形成・変動研究』
TR:講師:植田宏昭 教授(筑波大学)
TR:日時:令和2年9月1日(火)16:20~18:20(7~8限)
TR:場所:理学部本館2階 21講義室
TR:概要:多雨、猛暑、暖冬、豪雪、台風襲来などの気候変動(異常気象)を引き起こした要因について、グローバル気候システムの観点で実施した研究を紹介する。半年から一年先までの「季節予報」の利活用に向けた産官学連携の現状と課題についても触れる予定である。最後にこれらの基礎研究を下支えする「気候形成論」を皆様と議論したい。
TR:世話人:野沢徹
H4:2019年度
ID:20190902
AP:談話会『木星の雲対流』杉山耕一朗 准教授(2019.09.02)
AM:談話会『木星の雲対流』
TR:講師:杉山耕一朗 准教授(松江高専)
TR:日時:令和元年9月2日(月)16:20~18:20(7~8限)
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
TR:概要:木星には活発な積雲が存在することが知られており、水だけでなくアンモニアや硫化水素アンモニウムが凝結すると考えられている。これらの凝結性成分の分子量は主成分 (水素・ヘリウム) の分子量に比べて10倍以上大きいため、木星では地球から単純に類推できない独特な対流構造の存在が予想される。 今回は数値シミュレーション結果を元に木星の雲対流の特徴を紹介する。
TR:世話人:はしもとじょーじ
H4:2018年度
ID:20180919
AP:談話会『日本の暖候期に見られる停滞性降水系の出現特徴と環境条件』竹見哲也 先生(2018.09.19)
AM:談話会『日本の暖候期に見られる停滞性降水系の出現特徴と環境条件』
TR:講師:竹見哲也 先生(京都大学)
TR:日時:平成30年9月19日(水)16:20~18:20(7~8限)
TR:場所:理学部本館2階 24講義室
TR:概要:日本では、梅雨期や台風期にしばしば集中豪雨が発生する。集中豪雨の多くは停滞性の降水系により発生し、それら降水系は線状に組織化する形態を取る場合が多い(いわゆる線状降水帯)。頻繁に発生する現象であるにも係わらず、停滞性降水系に関する統計的な性状については十分に調べられていなかった。ここでは、最近の我々の研究により明らかとなった暖候期の停滞性降水系の出現特性と環境条件についての研究成果について述べる。また、平成29年7月九州北部豪雨や平成30年7月豪雨といった最近の事象の解析結果についても報告する。
TR:世話人:野沢徹
ID:20180911
AP:談話会『北陸地方で地震・津波や防災教育を考える』大堀道広 先生(2018.09.11)
AM:談話会『北陸地方で地震・津波や防災教育を考える』
TR:講師:大堀道広 先生(福井大学附属国際原子力工学研究所)
TR:日時:平成30年9月11日(火)16:20~17:20(7限)
TR:場所:理学部本館2階 25講義室
TR:概要:2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震による津波被害はたいへん衝撃的であったが、北陸3県は有感地震が少なく、津波被害の経験も少ないこともあり、いまなお防災意識が低いのが実状である。各県独自の津波シミュレーションが行われているが、想定する海域断層の違いや、県単位(さらには市町村単位)のハザードマップは、防災教育に向けた津波の全体像の理解や災害時の広域連携を検討するには利用しづらい面がある。本研究では、北陸3県の津波ハザード評価を行い、全体を俯瞰した上で、防災教育を優先的に進めるためのモデル地域を抽出を試みたので、今後の検討課題も含めて報告する。
TR:世話人:竹中博士
PS:皆さんぜひお気軽にご参加ください。なお、この談話会は9月10~12日の集中講義(地球科学特別講義IIa)の一部でもありますので、受講生は必ず参加してください。(教室に注意。このときだけ教室は25講義室ですが、それ以外は地球科学科リフレッシュコーナーです。)
ID:20180905
AP:談話会『プレートテクトニクスに伴うヒ素・水銀の循環』益田晴恵 先生(2018.09.05)
AM:談話会『プレートテクトニクスに伴うヒ素・水銀の循環』
TR:講師:益田晴恵 先生(大阪市立大学)
TR:日時:平成30年9月5日(水)16:20~(7~8限)
TR:場所:理学部本館2階 25講義室
TR:概要:ヒ素と水銀は生物毒性が高く、環境中の濃度が厳しく規制されている微量元素である。天然由来のヒ素・水銀汚染は世界的に出現するが、出現地域は火成活動や大きな浸食活動などと関連する活動的なテクトニクス場と密接に関係している特徴がある。ヒ素・水銀の地球化学的特徴に着目して、プレートテクトニクスによる地殻と水圏付近でのリサイクル過程に関する研究成果を紹介する。
TR:世話人:井上麻夕里
PS:益田先生は現在日本地球化学会の会長をされており、地球化学の分野で幅広く活躍されている方です。話も面白いので、学生の皆さんも是非参加してみて下さい。
H4:2017年度
ID:20171201
AP:談話会『From the microstructure to the big ice sheets: why snow is important』Dr. Martin Schneebeli(2017.12.01)
AM:談話会『From the microstructure to the big ice sheets: why snow is important』
TR:講師:Dr. Martin Schneebeli(WSL Institute for Snow and Avalanche Research, Switzerland)
TR:日時:平成29年12月1日(金)16:20~17:20(7限)
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
TR:概要:Snow is a special material, nothing else on Earth is constantly so close to its melting point. In this seminar I will introduce some basic concepts of snow physics, and then go to their application on the big ice sheets, Antarctica and Greenland. I will illustrate the huge effect snow has on climate, and why we need to understand it in more detail.
TR:世話人:青木輝夫
PS:スイス連邦「雪・雪崩研究所」の Martin Schneebeli 博士は積雪粒径、変態過程、積雪層構造などの積雪の物理特性に関する研究分野の第一人者です。このセミナーでは積雪の物理特性に関する基本概念、グリーンランドや南極におけるそれらの観測結果、そして、雪と気候との関わりについて講演して頂きます。
ID:20170904
AP:談話会『火星表面におけるDust Devil Track,火星気象学入門』栗田敬 先生(2017.09.04)
AM:談話会『火星表面におけるDust Devil Track,火星気象学入門』
TR:講師:栗田敬 先生(東京大学)
TR:日時:平成29年9月4日(月)16:20~18:20(7~8限)
TR:場所:理学部本館3階 31講義室
TR:概要:火星には薄い二酸化炭素の大気が存在し、様々な大気活動・気象現象が生じている。その基本は薄い大気・太陽放射・地表面熱特性・地形と言う4つの特性できまり、地球上の気象現象よりも単純であり、気象学入門として最適な題材が多い。それらの中で本セミナーでは火星表面で極めて一般的に存在する Dust Devil をとりあげ説明する。 Dust Devil は小型のつむじ風であり、その風により表層の微細粒子層:レゴリスをはね飛ばし除去するために表層のアルベドにコントラストを作り出し、 Dust Devil Track としてその活動が表層画像・地質に痕跡として残されている。講演では Dust Devil Track に関する一つの謎を紹介し、それを説明するモデルを提示する。
TR:世話人:はしもとじょーじ
H4:2016年度
ID:20161124
AP:セミナー『北海道における気候変動適応研究』稲津將 准教授(2016.11.24)
AM:セミナー『北海道における気候変動適応研究』
TR:講師:稲津將 准教授(北海道大学大学院理学研究院)
TR:日時:平成28年11月24日(木)15:00~(1時間程度)
TR:場所:理学部本館2階 24講義室
TR:世話人:野沢徹
PS:稲津先生は気象学、気候学、特に大気海洋相互作用がご専門で、学部生にも分かりやすくお話してもらえるようにお願いしています。多くの学生さんのご参加をお待ちしています。
ID:20160808
AP:談話会『海洋観測維新 ~資源の探査・環境影響調査市場を土佐から変える~』野口拓郎 准教授(2016.08.08)
AM:談話会『海洋観測維新 ~資源の探査・環境影響調査市場を土佐から変える~』
TR:講師:野口拓郎 准教授(高知大学)
TR:日時:平成28年8月8日(月)16:20~(7限)
TR:場所:理学部本館2階 23講義室
TR:世話人:山中寿朗
PS:この4月に高知大学に開学部した農林海洋科学部で教鞭を執る若手の先生にお話いただきます。ふるってご参加ください。
ID:20160801
AP:談話会『金星へカメラを飛ばした』岩上直幹 先生(2016.08.01)
AM:談話会『金星へカメラを飛ばした』
TR:講師:岩上直幹 先生(専修大学非常勤講師)
TR:日時:平成28年8月1日(月)16:20~17:20(7限)
TR:場所:理学部本館2階 22講義室
TR:世話人:はしもとじょーじ
PS:金星探査機あかつきに搭載された近赤外線カメラを作った人です。学部生やその他の素人さんの聴講も歓迎します。
H4:2015年度
ID:20150910
AP:談話会『小惑星探査機「はやぶさ」観測データから見た小惑星イトカワの地質学』平田成 准教授(2015.09.10)
AM:談話会『小惑星探査機「はやぶさ」観測データから見た小惑星イトカワの地質学』
TR:講師:平田成 准教授(会津大学)
TR:日時:平成27年9月10日(木)16:15~17:45(5限)
TR:場所:理学部本館2階 22講義室
TR:世話人:はしもとじょーじ
ID:20150907
AP:談話会『マグマの流れ ― マグマの発生・上昇・噴火、マグマレオロジー』隅田育郎 准教授(2015.09.07)
AM:談話会『マグマの流れ ― マグマの発生・上昇・噴火、マグマレオロジー』
TR:講師:隅田育郎 准教授(金沢大学)
TR:日時:平成27年9月7日(月)16:15~17:45(5限)
TR:場所:理学部本館2階 22講義室
TR:世話人:はしもとじょーじ
H4:2014年度
ID:20150218
AP:講演会『Climatic Scenario and Rainfall Induced Landslide Hazards in Chittagong, Bangladesh』A.T.M.Shakhawat Hossain 教授(2015.02.18)
AM:講演会『Climatic Scenario and Rainfall Induced Landslide Hazards in Chittagong, Bangladesh』
TR:講師:A.T.M.Shakhawat Hossain 教授(Jahangirnagar University)
TR:日時:平成27年2月18日(水)17:00~(1時間程度)
TR:場所:理学部本館3階 第2演習室(A338)
TR:世話人:鈴木茂之
PS:バングラデシュのジャハンギルナガール大学からシャカワット先生が本学科を訪問される予定で、講演をお願いしています。自然災害がテーマです。バングラデシュの地形・地質や気候を知る良い機会ですのでどうぞご参加下さい。
ID:20141128
AP:談話会『日本からみつかった巨大隕石衝突の記録』尾上哲治 准教授(2014.11.28)
AM:談話会『日本からみつかった巨大隕石衝突の記録』
TR:講師:尾上哲治 准教授(熊本大学)
TR:日時:平成26年11月28日(金)16:15~17:45
TR:場所:理学部本館2階 21講義室
TR:概要:「恐竜は巨大隕石の衝突により絶滅した」 ― このような説が1980年アルバレツ親子により提唱されてから、約30年が過ぎました。この間研究者は、恐竜が絶滅した6500万年前の「白亜紀/古第三紀境界」とよばれる時代以外からも隕石衝突の痕跡が見つかるはずと考え、これまで多くの研究がなされてきました。しかし実際に生物の絶滅を引き起こしたような隕石衝突は、白亜紀/古第三紀境界以外からはみつかっていません。そのため、生物の絶滅を引き起こすほどの巨大な隕石衝突は、白亜紀/古第三紀境界だけだったのではないかと考えられるようになってきました。ところが最近になって、岐阜県の木曽川川岸に露出する「チャート」とよれる約2億1500万年前(三畳紀後期)の地層から隕石衝突の証拠がみつかりました。推定された衝突隕石のサイズは最大で直径約8kmと巨大なもので、この衝突が当時の地球環境に大きな影響を与えたことが予想されます。本講演では、日本から世界で初めて明らかになった隕石衝突の証拠とその研究を中心に紹介します。
TR:世話人:山下勝行
ID:20140930
AP:談話会『北極海氷変動が中緯度の気候に及ぼす影響』浮田甚郎 教授(2014.09.30)
AM:談話会『北極海氷変動が中緯度の気候に及ぼす影響』
TR:講師:浮田甚郎 教授(新潟大学自然科学系・理学部)
TR:日時:平成26年9月30日(火)15:00~17:00(質疑応答を含む)
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
TR:世話人:野沢徹
ID:20140925
AP:講演会『付加体の深部地下圏でのメタン生成メカニズムと炭素・窒素循環~地域で利用する自立分散型エネルギー生産システムの創成を目指して~』木村浩之 准教授(2014.09.25)
AM:講演会『付加体の深部地下圏でのメタン生成メカニズムと炭素・窒素循環~地域で利用する自立分散型エネルギー生産システムの創成を目指して~』
TR:講師:木村浩之 准教授(静岡大学大学院理学研究科地球科学専攻)
TR:日時:平成26年9月25日(木)14:30~(60分程度)
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
TR:対象:誰でも参加できます。
TR:世話人:山中寿朗
H4:2013年度
ID:20140218
AP:講演会『地震と防災:災害史に学ぶ』武村雅之 教授(2014.02.18)
AM:講演会『地震と防災:災害史に学ぶ』
TR:講師:武村雅之 教授(名古屋大学減災連携研究センター)
TR:日時:平成26年2月18日(火)3限(12:45~14:15)
TR:場所:理学部本館2階 22講義室
TR:対象:どなたでも参加できます
TR:概要:科学技術は我々に選択枝の幅は広げてくれるが、選択を誤ると却って人は不幸になる。大正12年の関東大震災で東京が被った未曾有の被害が語る教訓である。震災後、二度と繰り返さないとの誓いのもとに耐震基準が造られた。そのわずか二十年後の昭和19年、いともたやすく誓いを無視して悲劇を繰り返した東南海地震での名古屋や半田の軍需工場、そしてその結末は敗戦。何度同じ失敗を繰り返しても懲りない歴史は、東日本大震災にも受け継がれている。来たるべき南海トラフの地震の結末も自明であろう。本当にこれでいいのだろうか?。
TR:世話人:隈元崇
ID:20131226
AP:講演会『日本の大陸棚と大陸棚限界委員会』浦辺徹郎 先生(2013.12.26)
AM:講演会『日本の大陸棚と大陸棚限界委員会』
TR:講師:浦辺徹郎 先生(東京大学名誉教授)
TR:日時:平成25年12月26日(木)15:00~
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
TR:対象:誰でも参加できます。
TR:概要:大陸棚限界委員会とは国連海洋法条約で扱われている海洋の利用・開発とその規則に関する国際法上の権利義務関係を定めのうち、200海里を越える大陸棚延長申請に対し勧告を出す任務を負っています。国家間の利権の調整に当たる重要な委員会です。年間21週間に渡り、国連ビルで会議が行われます。浦辺先生は現在この委員会の委員を務めておられます。最近資源開発と絡んだ国境問題が身近な話題の一つとなっていますが、国連がこの問題についてどのような枠組みで対応しようとしているかお話し頂ける予定です。
TR:世話人:山中寿朗
ID:20130610
AP:公開セミナー『GPS機器・機能を野外調査に活かすノウハウ』小林昇 先生(2013.06.10,07.22)
AM:公開セミナー『GPS機器・機能を野外調査に活かすノウハウ』
TR:講師:小林昇 先生((株)ジオブレイン代表取締役)
TR:日時:平成25年6月10日(月)18:00~ 第一回
平成25年7月22日(月)18:00~ 第二回
TR:場所:理学部本館1階 地球科学実験室(A143)
TR:目的:カーナビ、携帯電話やスマートフォンなどGPS機能は身近になり、また廉価なGPS機器も市販されている。これらを野外調査やその成果の図化に活かすための事例やノウハウを提供する。
TR:内容:◇第一回(パソコンでのプレゼン、電卓を各自用意)
1。GPSシステムの概要
2。地球の形とGPS座標系
3。GPS機器の種類と利用形態
4。軌跡やポイントデータの保存・抽出
5。測位データ変換後の測量座標系とCAD上での関係
6。調査事例の紹介
◇第二回(できればPCでの実習形態に、可能なら各自ノートPC持参)
1。各種地形図の取り扱い
国土地理院1/25000地形図、森林基本図1/5000、都市計画図1/2500、
実測図面(1/1000~1/500)、グーグルマップ・ゼンリン地図(縮尺任意)
2。現場写真と地図(撮影位置図)とのリンク
3。踏査経路・軌跡CAD(AutoCAD)図面上での操作方法
4。オリジナル地形図のGPS機器への組込
5。スマートフォンの上手な利用形態(今後の展望)
使用環境:WindowsXP以降PC、Bluetooth利用可(GPSロガー接続用)、
Wi-fiルータ(インターネット接続用)、Android対応スマートフォン、iPhone4,5
主たる使用ソフト:グーグルマップ、カシミール3D、その他GPSロガー添付のツールソフト
TR:世話人:鈴木茂之
PS:専門家をお招きしてセミナーを行います。内容は講師の小林さんが国道防災点検のための地質精査を行うなかで実用化されたものです。野外調査や試料採取において正確な位置情報を取得し、それを地図におとして図を作成する手法を紹介して下さいます。多くの方々に役にたつものです。どうぞ多数ご参加ください。
H4:2012年度
ID:20121026
AP:講演会『硝石生産を支えた幕末維新期の舎密学』溝田智俊 先生(2012.10.26)
AM:講演会『硝石生産を支えた幕末維新期の舎密学』
TR:講師:溝田智俊 先生(岩手大学名誉教授,現・別府大学)
TR:日時:平成24年10月26日(金)16:20~
TR:場所:理学部本館2階 26講義室
TR:概要:硝石(硝酸カリウム:KNO
3)は黒色火薬の主要成分であるために、歴史を動かす重要な軍事物資である。約200年前(19世紀半ば)に頻発した内戦、たとえば合衆国での南北戦争、日本の戊辰および西南戦争に際して大きな需要を生んだ。硝石原料は天然にはほとんど産しないために、アンモニア酸化菌の工業的培養と塩類の分別晶出技術に支えられて生産された。この講演では、当時の硝石産業を支えた化学(=舎密学)を現代化学に照らし合わせて解説する。
TR:世話人:山中寿朗
PS:化学の小難しい話ではなく、インド(大英帝国領)のカースト制度と環境汚染が大量の硝石生産にとって重要な役割を演じたことや、世界遺産の合掌造りで有名な白川郷では、あの合掌造りの家屋の中でカイコの飼育で生じる糞から硝石を生産する話、さらに、日本近代史を地球化学の目で読むと、新しい発見があることなどをわかりやすく紹介して下さります。
H4:2011年度
ID:20110629
AP:講演会『鉱物は細菌たちの貯蔵庫』服部勉 先生(2011.06.29)
AM:講演会『鉱物は細菌たちの貯蔵庫』
TR:講師:服部勉 先生(東北大学名誉教授)
TR:日時:平成23年6月29日(水)2限
TR:場所:理学部本館2階 22番講義室
TR:概要:服部勉先生は土壌中の微生物を研究されています。これまで、岩波新書「大地の微生物学」、新潮選書「微生物を探る」、養賢堂 「土の微生物学」など多数の書籍も書かれています。先生の研究手法が独創的であり、真摯に研究に取り組まれていることは定評です。地球環境を支える土壌は地球科学分野でも重要な研究対象ですので、先生のご講演からきっと有益な収穫があると思います。皆様のご参加を期待しています。
TR:世話人:鈴木茂之
H4:2009年度
ID:20091106
AP:講演会『中国初期被子植物研究の最前線』孫革 教授(2009.11.06)
AM:講演会『中国初期被子植物研究の最前線』
TR:講師:孫革 教授(吉林大学古生物学地層学研究所所長,瀋陽師範大学古生物学研究所所長,遼寧古生物博物館館長,教育省北東アジア進化古環境変遷重点研究室主任)
TR:日時:平成21年11月6日(金)9:00~(1時間程度)
TR:場所:理学部本館2階 23講義室
TR:概要:孫先生は地球で最も初めの被子植物化石の研究で知られ、これに関する研究は Science 誌に3編掲載されています。ダーウインが古生物学で最も難解な課題の一つにあげた、被子植物の起源に関して、一般向けに講演して下さいます。また問題の植物化石を産出する地層(ジュラ紀~白亜紀)は、初期の鳥の化石が多産することでも話題になっていますが、これらのすばらしい化石も紹介される予定です。
TR:世話人:鈴木茂之
ID:20090608
AP:講演会『Dating igneous and detrital zircons in the Philippines - new insights into the evolution of the Palawan Continental Terrane in Mindoro 岩石中のジルコンの年代から推測されるフィリピン島弧形成史』Dr. Ulrich Knitte(2009.06.08)
AM:講演会『Dating igneous and detrital zircons in the Philippines - new insights into the evolution of the Palawan Continental Terrane in Mindoro 岩石中のジルコンの年代から推測されるフィリピン島弧形成史』
TR:講師:Dr. Ulrich Knitte(Department of Geosciences, National Taiwan University 国立台湾大学地球科学科)
TR:日時:平成21年6月8日(月)17:30~18:30
TR:場所:理学部本館3階 第2演習室(A338)
TR:概要:The Palawan Continental Terrane is thought to be a rifted portion of the eastern margin of Asia rifted from South China as a consequence of the opening of the South China Sea. Dating of the meta-igneous gneiss from Mindoro has yielded the oldest radiometric age so far available for the Philippines. Dating of detrital zircons of recent sediments provides insights into the geology of the catchment areas, whereas dating of detrital zircons from sandstones provides insights into source areas.
Knittel 博士が調査されているフィリピンのミンドロ島は、大陸から分離してきたパラワン地塊とフィリピンの初生的な島弧が衝突した場所と考えられています。フィリピンの島弧は白亜紀後期以後形成されたものですので、博士が新たに見いだした古い年代のジルコンからどのようなフィリピン島弧の形成史が明らかになったか期待されます。
TR:世話人:鈴木茂之