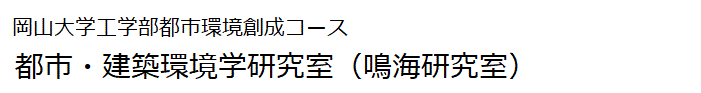研究内容
鳴海研究室の研究・教育目標
人間活動を維持するためにはエネルギーを消費しなければなりません。しかしながら、エネルギーを消費することは資源枯渇や地球温暖化などの地球規模の環境問題を引き起こすだけでなく、ヒートアイランド現象や大気汚染などの地域(都市)規模の環境問題も引き起こします。鳴海研究室では、持続可能な地球を維持しつつ、快適な都市環境を実現するために、これから構築していくべきエネルギーシステムの在り方やその利用に関わるリテラシーを明らかにするための研究教育を行なっています。主な研究テーマは以下の通りです。
● ゼロカーボンシティ実現に向けた持続可能都市・建築のあり方
日本政府は2050年にカーボンニュートラルの実現を目指していますが、この実現のためには、再生可能エネルギーの積極的な導入はもちろんのこと、都市構造の変革やZEB・ZEHの実用化・普及など、脱炭素化に向けたイノベーション創出を継続的に推進していくことが不可欠です。鳴海研究室では、近未来の持続可能都市・建築設計手法の在り方を確立すべく、高密都市から農山村地域までを対象として、シミュレーションを用いたCO2削減対策の評価をおこなっています。
● 都市における気候変動の暑熱影響と適応策
東京や大阪などの大都市では地球温暖化に加えてヒートアイランド現象の影響により急速に温暖化が進行し、エネルギー・資源や健康リスク,大気汚染など、都市生活者に様々な影響を与えています。鳴海研究室では、ヒートアイランド現象の都市生活者に対する環境問題としての側面に着目し、ヒートアイランド現象に伴う功罪を可能な限り定量化するとともに、ヒートアイランド対応に関わるルール作りを提言すべく種々の検討を行っています。
● エネルギー消費行動とエネルギーリテラシーの関係性
ゼロカーボンシティを実現するためには、そこに住まう人々が意識を持って日々生活することが重要であり、環境に配慮したエネルギー消費行動とエネルギーリテラシーには大きな関係があると考えられています。鳴海研究室では、省エネルギー行動や地産地消型電力会社の選好の背景にある価値観・意識に関する心理モデルを構築することで、人々を環境に配慮したエネルギー消費行動に導く情報提供や環境教育の在り方について検討を行っています。
本年度の研究テーマ
(括弧内は共同・連携研究先)● 中山間地域の再設計を視野に入れた脱炭素シナリオ設計
(岡山県真庭市、瀬戸内市など) ※2・3
● 「環境・エネルギーまちづくり」を通じた地域社会イノベーション
(国立環境研究所、東京大学、岡山県真庭市、ライフデザイン・カバヤなど) ※2・3
● 多様なエネルギーリソースを有する街区のエネルギーマネジメント
(中部電力) ※4
● 地球・都市温暖化が都市生活に与える影響と回避シナリオ
(Lawrence Berkeley National Laboratory、東京大学など) ※5
● エネルギー行動の意思決定構造分析および行動促進アプローチ
(東京大学など) ※1
※末尾の数字は関連する研究キーワード(下記)の番号を表わします
研究キーワード
1.エネルギー消費行動と心理研究希望等の問い合わせについては、鳴海までご連絡下さい。
narumi-daisuke(at)okayama-u.ac.jp *(at)は@に変更して下さい