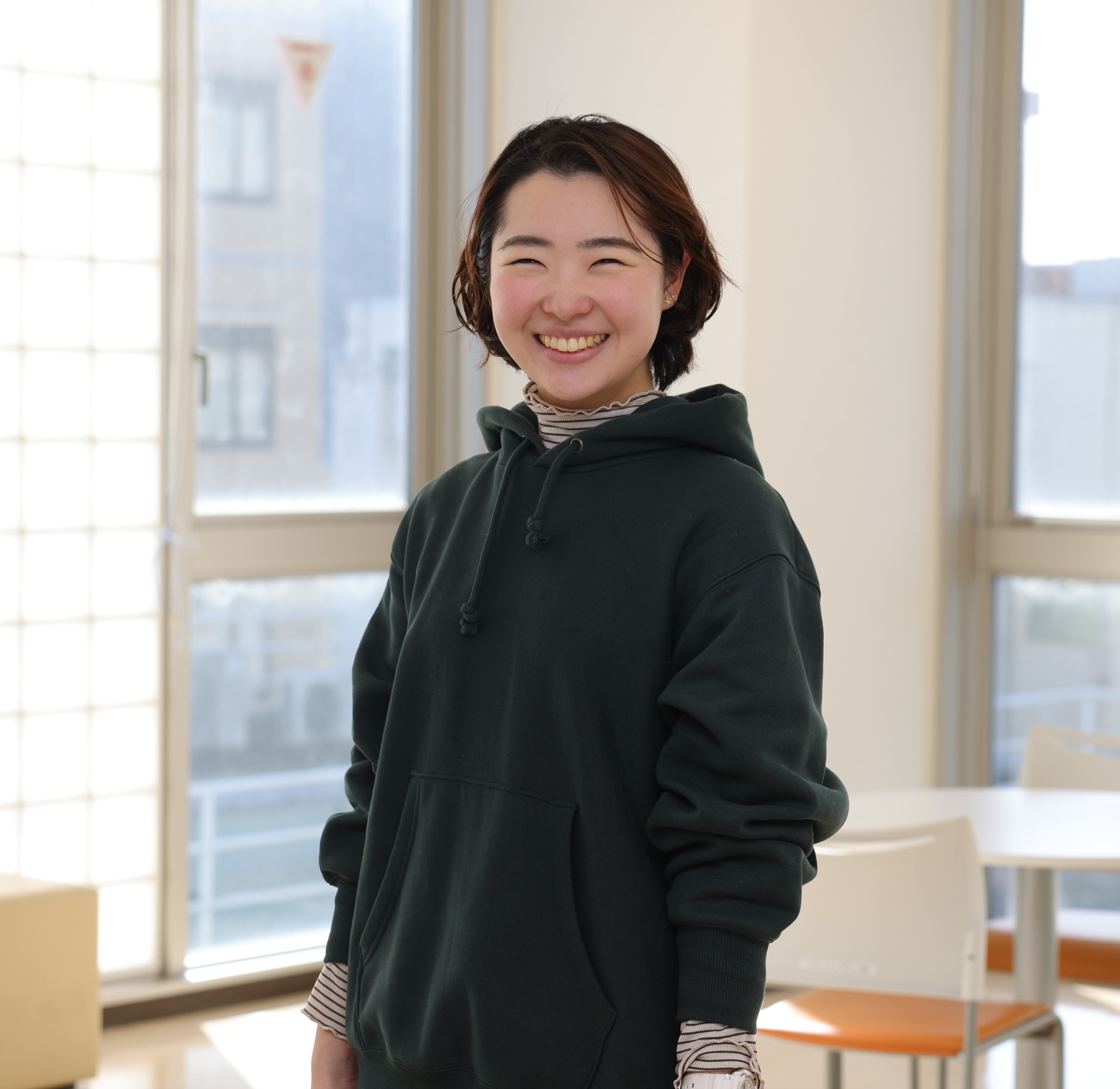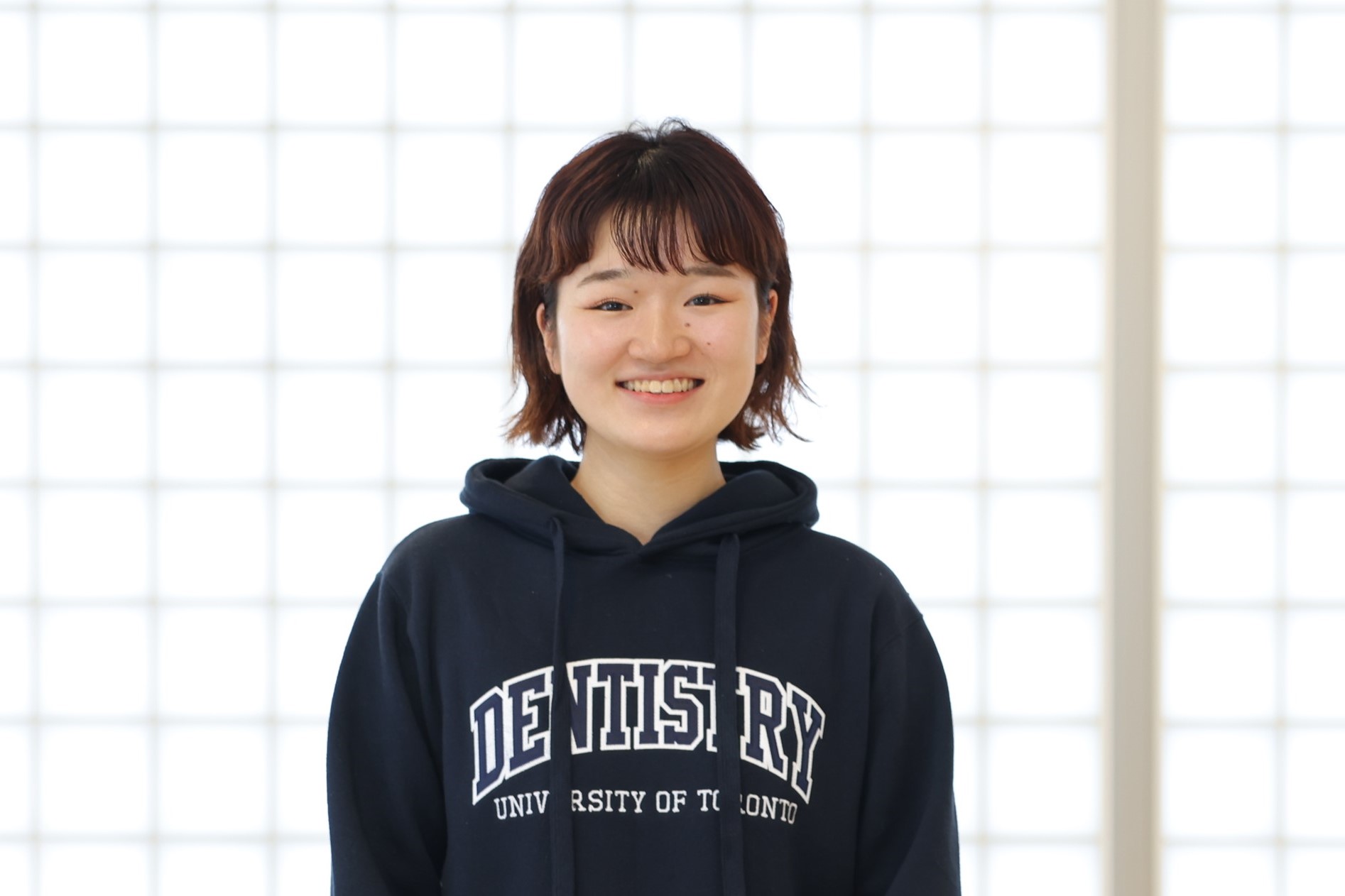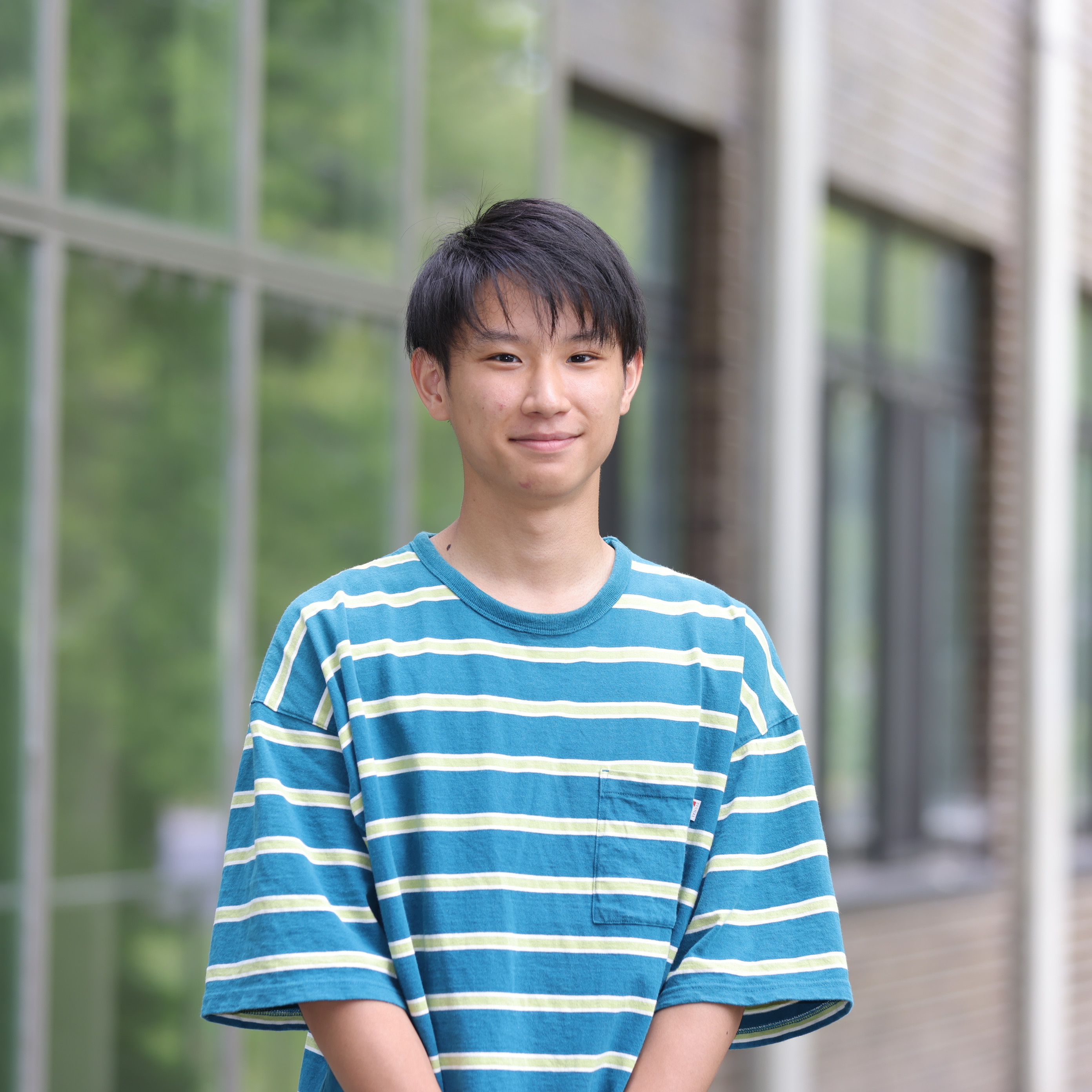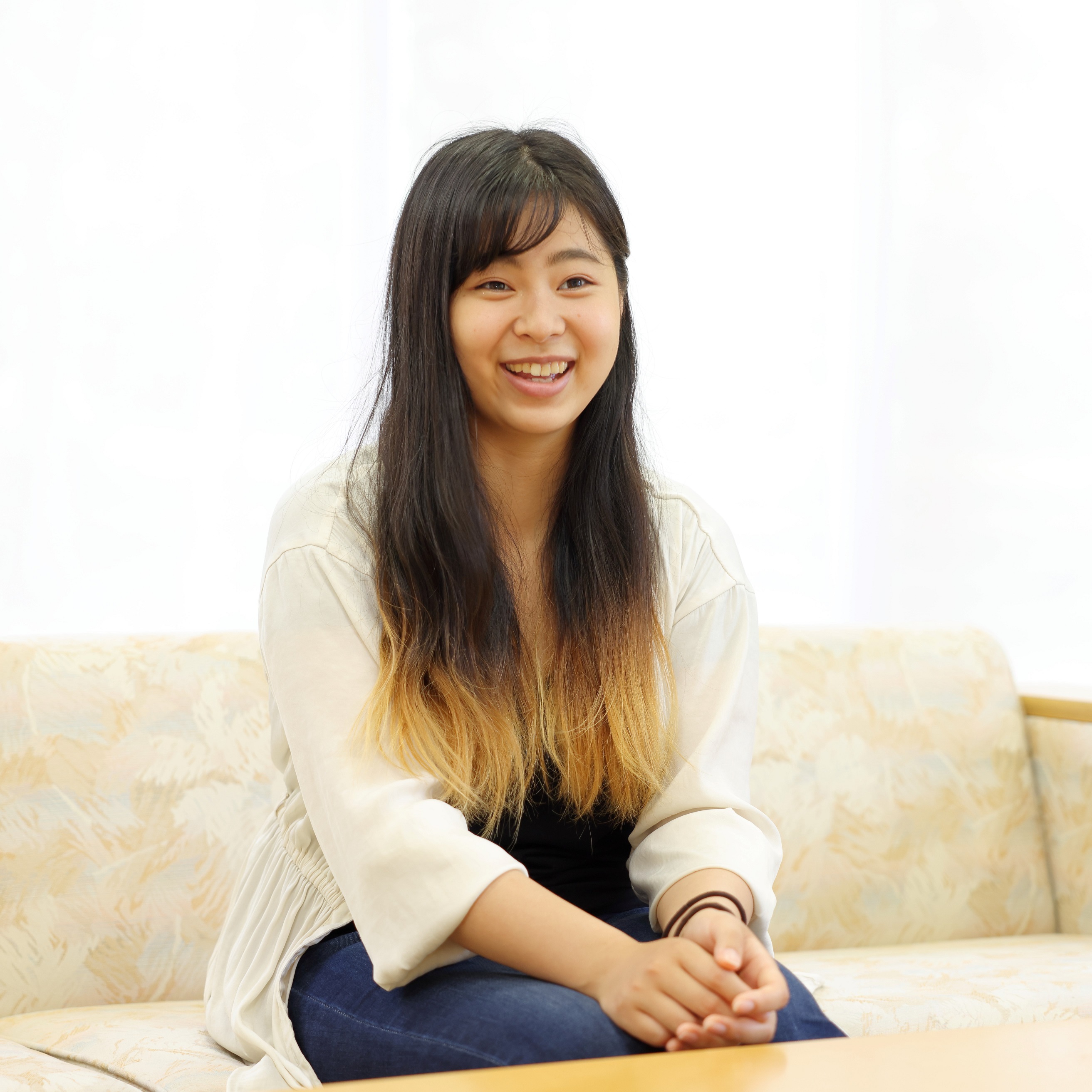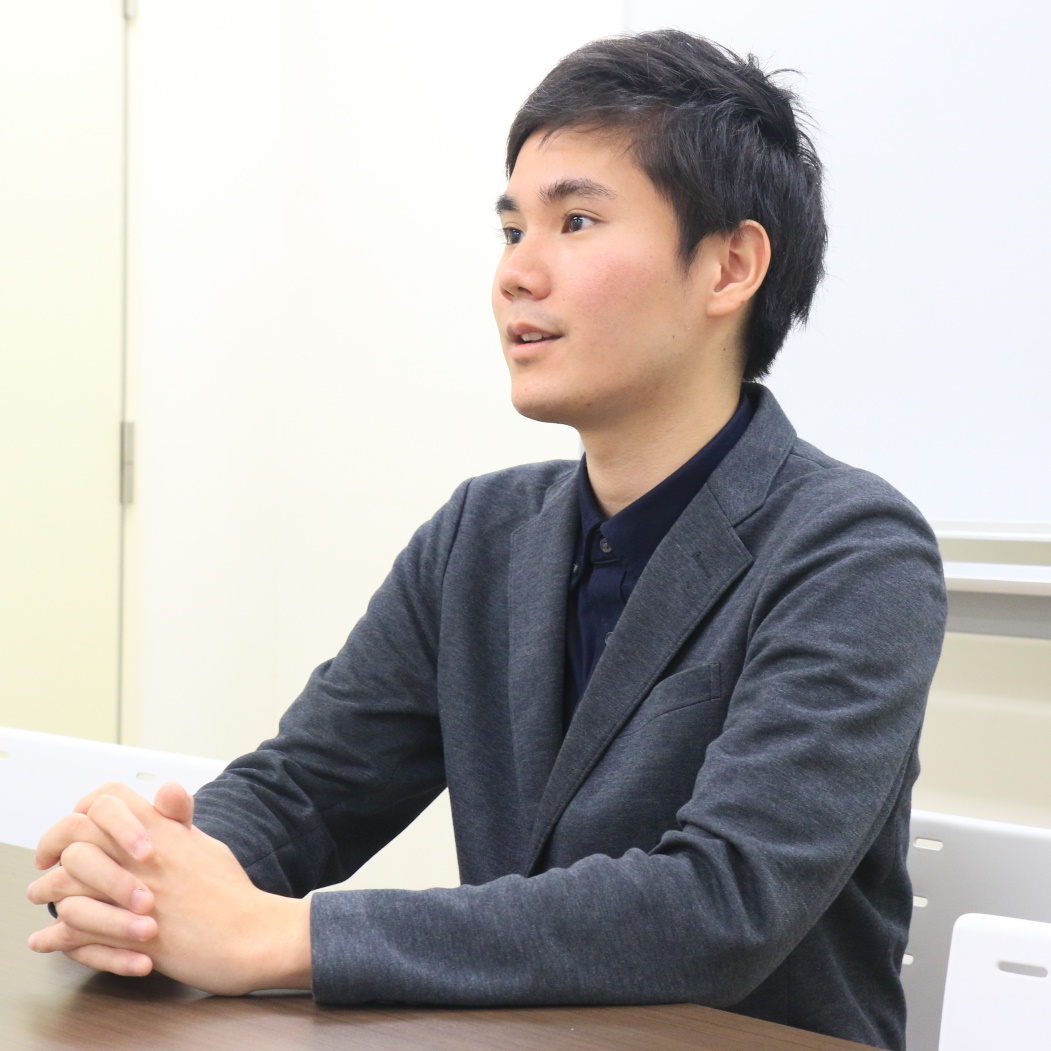IB生の声
岡山大学にIB入試で入学した学生たちの声を集めました。
世界中のIB生が戦友に!国際看護師に向かって踏み出した一歩
医学部保健学科4年 茂ハード里紗さん
―IB校に入ったきっかけ
―IB校での経験
(2025.1.31)
中学生で踏み出した産婦人科医への道
医学部医学科3年 市野楠奈さん
―IB校に入るまでの学びの環境
―IB校での経験
(2024.12.5)
大好きな日本とタイをつなぐ人材になりたい
グローバル・ディスカバリー・プログラム2年 サンセムサップ・アンポンさん
―IB校に入るまでの学びの環境
―IB校での経験
(2024.11.15)
培ったのは最後まで諦めない気持ち
工学部工学科機械システム系機械工学コース3年 砂田凜太郎さん
―IB校に入るまでの学びの環境
―IB校での経験
(2024.10.8)
英語を強みとして持つ薬剤師を目指して
薬学部薬学科3年 冨田依里さん
―IB校に入るまでの学びの環境
―IB校での経験
(2024.9.4)
今が一生ものになる。自分を強くしてくれた価値のある経験
医学部医学科3年 松岡あさひさん
―IB校に入るまでの学びの環境
―IB校での経験
(2024.3.18)
時間をフル活用して勉強も部活も趣味も楽しむ!それがバランスを保つ秘訣
歯学部歯学科3年 金子晴姫さん
―IB校に入るまでの学びの環境
―岡山大学に進学した理由Learner Profile :IB生にどのような人物になって欲しいか、という理想の人物像を言語化したもの。「探求する人」「知識のある人」など10個の項目がある。
(2024.3.7)
感謝の気持ちをもって学ぶことの大切さを伝えられる教員になりたい
教育学部学校教育教員養成課程小学校教育コース4年 山部雅帆さん
―IB校に入るまでの学びの環境
―岡山大学に進学した理由EPOK を利用して、念願の韓国留学を果たしました。コロナ禍の影響もあり、当初希望していた通りのスケジュールではなかったものの、欧米からの留学生たちとともに韓国語を学ぶことができました。今回は交換留学(EPOK)を利用して留学したので協定校が限られていましたが、行けたことに満足しています。これからも韓国語の勉強も続けていきたいと思っています。
(2024.2.2)
「得意」を最大限に生かすより、今は「好き」を伸ばしたい!
工学部機械システム系ロボティクス知能システムコース3年 穂迫大輝さん
―IB校について
―岡山大学を選んだ理由
(2023.8.23)
薬学の英語に触れたい!高山さんが目指す進路とは?
薬学部創薬科学科3年 高山祥吾さん
―IB校について
―岡山大学を選んだ理由
(2023.8.9)
香港に住んで18年!寺島さんが岡山大学を選んだ理由とは?
医学部医学科3年 寺島美優さん
―IB校について
―岡山大学を選んだ理由医学研究インターンシップ(MRI) で留学していました。留学先では若年性肥満に起因するガンの国ごとの傾向をコンピュータで解析する研究を行いました。この研究は帰国してからも続けたいなと思えるほど楽しく、非常に充実した3カ月でした!
(2022.12.21)
好奇心を持って積極的にチャレンジ!西村さんが目指す医師像とは?
医学部医学科5年 西村晏夕眸さん
―IB校について
―岡山大学を選んだ理由医学研究インターンシップ(MRI) の制度があり、進学先を日本とアメリカで迷っていた私にとっては、日本にいながら国際的なチャレンジができることが大切なポイントでした。
三俣診療班 」に参加しています。北アルプス奥地にある標高2545mの三俣診療所で、診療所が開く7~8月に医師・看護師の診療の補助、安全登山講習会などをボランティアで行います。
(2022.8.24)
岡山大学で探求中!帰国子女として感じた社会の違和感とは?
グローバル・ディスカバリー・プログラム3年 長谷元紀さん
―IB校について
―岡山大学を選んだ理由グローバル・ディスカバリー・プログラム(GDP) を選びました。実際に入学してどちらも学んでみて、今はより面白かった文化人類学にどっぷり浸かっている感じです(笑)
学生誌Polyphony の作成に携わっています。編集部として、学生の論文や旅日記、詩、短編小説を集めて編集することはもちろん、小説を読んでの考察やオンラインゲームの効果についての論説など寄稿しています。この春には東京大学の学生誌Komaba Timesの編集部と「日本の大学で英語の学生誌を発刊することの意義」について対談し、Komaba Timesに記事として掲載しました。 Polyphonyは今年9月ごろに発刊する予定なので、皆さんにもぜひ読んでいただきたいです!
(2022.7.29)
IB校での経験を生かし、新しい環境で挑戦する
大学院環境生命科学研究科 博士前期課程生物生産科学専攻1年 寺岡真緒さん
―IB校について
―岡山大学を選んだ理由グローバル・ディスカバリー・プログラム(GDP) があったのが大きな理由です。
IB校では文理選択等もなかったので、入学してから進路を決められるGDPが私にはピッタリでした。このような制度のある大学って、他にあまり無いと思います。
私はIB入試ではなく、GDP国際入試を利用しましたが、IB校の内申点を考慮してくれたのも嬉しいポイントでしたね。
(2022.6.22)
SCRP日本代表選抜大会で優勝、研究に励む
歯学部歯学科4年 棚井 あいりさん
海外経験が豊富な両親の勧めで、1歳からAoba Japan International School(東京)に通い始めました。また、日本人として日本の文化や習慣も大切にしたいと、インターナショナルスクールが長期休暇の時期は公立の小中学校にも通いました。5歳から始めた「そろばん」は9段で、中学1年から大学進学までの6年間は、現役生ながらアシスト講師として指導も行いました。
※1 、Volunteer for the Homeless※2 、Yearbook Committee※3 やSoccer Club(プレイヤー)など12の部活に所属し5つの部活で部長を務め、課外活動にとても積極的に取り組みました。
岡山大学への進学を決めたのは、サビナ先生が高校訪問に来られ、その後岡山大学を訪問する機会を作ってくださったのがきっかけでした。私は岡山大学歯学部に入学した最初のIB生です。日本語での大学の講義や実習は初めてであり当初戸惑いましたが、周りの同級生や先生方から温かいサポートを頂き、岡山大学の雰囲気にすぐに馴染むことができました。
※4 で研究を行っていました)。現在も、課外活動として口腔形態学分野で研究を継続しています。口腔形態学分野では、自分自身で考える経験やたくさんの未知の課題にチャレンジする機会を与えていただきました。この1年間で歯科基礎医学会のJournal of Oral Biosciences誌に筆頭著者として総説を発表し、学会発表を5回経験いたしました。
※1 Women's Education Support Committee(女性教育支援部):アフリカにおける女性の教育環境の改善を目指すNPO団体を支援する。また、社会に対してアフリカを含む世界の女性教育の現状や重要性についての啓発を行う。
※2 Volunteer for the Homeless(ホームレスに対するボランティア):ホームレスの方に自分たちで調理した食事を提供する。<
※3 Yearbook Committee(アルバム編集部):毎年、全学年(幼稚園児から高校生)及び教員に配付するアルバムの作成や写真編集等を行う。
※4 ARCOCS:Advanced Research Center for Oral and Craniofacial Science;歯学部先端領域研究センター
(2021.11.19)
研究者を目指し、博士後期課程へ進学
大学院自然科学研究科 博士前期課程生物科学専攻2年 関口 学さん
小学校3年生からインターナショナルスクールに通い、高校課程でIBプログラムを受けました。
現在は博士前期課程に在籍し、ショウジョウバエを研究対象とし、生理、代謝、行動などのもつ約24時間周期のリズムを調整する体内時計の研究を行っています。ショウジョウバエは、卵から親になるまで10日と短く、目の色や羽の形など身体的な特徴が明らかなだけでなく、脳内に分布したわずか150個の時計ニューロンで体内時計を制御しているため、実験動物として極めて優れています。今後、知識・技術を身につけ、ショウジョウバエだけでなく、様々な動物を使って実験をしてみたいです。
(2021.09.17)
医療面接・現場を英語で再現し、英語能力・医療技術の向上を図る部活動を立ち上げ
医学部医学科4年 瀬谷 海月さん
両親の仕事の関係で、香港で生まれ育ち、高校までインターナショナルスクールに通いました。香港の高校(IB認定校)では、日本人は学年に1人いるかいないかというマイノリティで、様々な国籍の友人と共に学ぶことが出来ました。日本で医療に関して学びたいと考えていたものの、当時IB入試を導入している医学部は多くありませんでした。香港の高校合同の日本語クラスで、サビナ先生(現IB推進室室長)が岡山大学IB入試の紹介を行われたことをきっかけに岡山大学医学部のことを知りました。ただ、香港の高校は5月で卒業のため、4月入学の岡山大学医学部とタイミングが合わず、一旦、9月入学で香港大学の医療系研究学部に入学しました。ただ、岡山大学医学部への思いが断ち切れず、IB入試を利用し、岡山大学医学部へ入学しました。
医学部の同級生でIB入試利用者は、私を含めて3人でした。そのうちの1人は、医学部オリエンテーションの時に初めて話しかけた人でした。出身校の話をしていく中でお互いIB認定校出身とわかり、うれしさと驚きのあまり、思わず英語で会話をしてしまい、周りの同級生をびっくりさせてしまったのは良い思い出ですね(笑)。岡山大学医学部は国内外のIB校出身者が多く、IB生の先輩や教員の皆さんのサポートを得やすい環境だと思います。漢字が苦手であった私に対して、論文を和文でなく英文のまま読むことを認めてくれた時は、弱みではなく強みを認めてくれていると感じ、うれしかったです。
学生生活では、2つの部活動に入っています。1つ目は、弓道部です。日本の武道への憧れと、当時はまだ少なかったIBの先輩がいらしたことから入部を決めました。海外生活が長かったことで不安でしたが、弓道部の仲間たちが温かく見守ってくださったおかげで無事、日本に馴染めたように思います。ARTプログラム とは、『卒後臨床研修と博士号取得を効率よく両立させる』大学院プログラムです。
(2021.08.24)
ネパールに図書館を目標に国際協力学生団体を設立
大学院自然科学研究科 博士前期課程機械システム工学専攻2年 今本 琢さん
広島県のIB課程が選択可能な中高一貫校出身です。IB課程に興味を持ったのは、中学3年生の時にニュージーランドのIB校に留学したことがきっかけです。ものづくりに興味があったため、IB資格を活かし、イギリス、アメリカ、カナダの大学と岡山大学工学部を受験しました。どの大学に進学するか迷いましたが、国内の大学で英語を学び、修士課程、博士課程で海外の大学に行くことも出来ると考え、岡山大学への進学を決めました。
学業の他には、国際協力学生団体Goingを大学2年生のときに3人で設立しました。団体設立後、ネパール地震で日本が支援を行なったニュースからネパールの現状を知り、団体の代表として、ネパールのシュリクリシュナ小学校に図書室を建設するプロジェクトをメインに掲げました。そのための資金集めとして岡山駅前での街頭募金活動、地域のイベントへの出店やクラウドファンディングなど、今まで経験したことがない様々な活動を行いました。3人で始まった小さな活動でしたが、メンバーや賛同者を募って行く中で、1年後には30名を超える団体となっていました。シュリクリシュナ小学校の校長先生と連絡を重ね、3年生の時に小学校に図書室を建てることが出来た時には、大きな達成感がありました。
(2021.08.03)
生物学の研究を通して、国際社会に貢献したい
大学院自然科学研究科博士前期課程 生物科学専攻1年 塩見 裕希乃さん
親の仕事の関係で小さい頃から海外生活が長く、ドイツのインターナショナルスクール(IB認定校)に通っていました。IB認定校であることはあまり意識していませんでしたが、大学進学や就職は日本でしたいと思っていたため、IB資格を生かそうと日本でIB入試を行っている大学を探したところ、岡山大学と出会いました。
入学後は国際シェアハウスに住んだり、留学生が集うL-caféで留学生支援のバイトをしたり・・・。例えば水の扱い方ひとつをとっても、その人の出身の国や地域によって大きく異なり、まだまだ知らないことが多いなと痛感させられます。
(2021.05.07)
IBプログラムの教員として、IB生を導く立場に
教育学部小学校教員養成コース4年 野村 慶太さん
広島県のIB校で学んだ後、進路をじっくりと考えるため、東京で2年間ほど飲食店と小学校の学童指導員として働いて、経営学や教育について学びました。その経験の中で「日本を、多面的な考えをもち、異文化理解のできる国に変えていきたい」という目標を持つようになり、教育に携わりたいと思ったため、教育学部を志望しました。
在学中はさまざまなボランティア活動を行ったのですが、特に力を入れたのは、玉野市の教育委員会から依頼を受けて行った、「たまのスチューデントガイド」という、中高生に英語に親しんでもらう外国語活動で、ほぼ4年間続けました。玉野市教育委員会の方や岡大の学生の計8人ほどで一から活動をスタートし、玉野市の中高生10~20人ほどに対して、直島で外国人観光客の方に観光案内をしてもらうなど、子どもたちが学校で学んできたことを社会で生かせるような活動を企画しました。学校教育ではどうしても子どもたちに評価を付けなければいけませんが、「評価はしないので、相手の反応を楽しんでみよう」という方針で進めると、子どもたちはとても積極的になってくれて、自分から観光客にインタビューをしに行く子もいたりするほどでした。異なる文化圏の人に触れることで、日本の文化や、両者の違いに目を向けるきっかけにもなってくれたと思います。
(2021.03.09)
頑張っている人を裏から支えたい
文学部人文学科4年 岡田 奏さん
国内のIB校出身です。IB校で国際社会を学ぶにつれて、かえって自分が日本のことをまだまだよく知らないということを痛感し、大学では日本のことをもっと学びたいと思うようになりました。国内でIB入試を受験できる大学を調べてみて驚いたのは、一部の学部で行っている大学は多数あっても、全学的に取り入れている大学はとても少なかったということ。岡山大学がIB生を歓迎していて、IB校での経験をしっかり評価してくれる大学なのだと心強く感じ、受験を決めました。
興味をもった授業は受けてみないと気が済まない性格で、教育学部や農学部、経済学部などいろいろな学部の授業を受けました。工学部で放射線の性質について学ぶ授業を受けた際は、物理学の知識が全然なくて苦労しました(笑)。でも、せっかく幅広い分野の勉強ができる環境が文学部にはありましたし、悔いが残らないよう学びたいと思ったので。
(2021.03.04)
世界のユース代表として、One Yong WorldやIFMSAで活躍
医学部医学科2年・喜舎場 朝基さん
高校1年まで沖縄で過ごし、2年生から、ユナイテッド・ワールド・カレッジ(UWC)への派遣プログラムに応募。イギリス校でIBのカリキュラムを受講し、世界90カ国から集まった仲間達たちと2年間の寮生活を送りました。UWCでは、シリア人の子から難民キャンプでの生活の話を聞くなど、自分の日常とは全然違う世界のことを身近に感じるきっかけになりました。「英語力を高めたい」「さまざまな国の人のことを知りたい」といった思いからの参加でしたが、この2年間で「紛争地域や発展途上国の人を医療で助けたい」という具体的な目標が定まりました。
入学後に特に印象に残っているのが、2019年10月に、ロンドンで開催された世界ユースサミット「次世代リーダー・グローバルサミットOne Young World(OYW)」に日本代表団の一員として参加できたこと。岡山大学はOYW日本代表団への派遣枠をもつ数少ない大学であり、岡山大学に惹かれた理由の一つでもあります。OYWでは「宗教間対話」のセッションに世界ユース代表の一人として登壇させていただいたほか、同世代の人たちとディスカッションや交流をもつ機会が多数ありました。各国の大学生たちが人道支援のために企業を立ち上げたり、国際団体に加盟したりして実際に行動を起こしているという話が衝撃的で、今まで医療支援の活動を行いたいと考えながらも「まだ大学生だから・・・」と言い訳していたことを思い知らされましたね。
(2021.03.02)
「人と人とを結びつけたい」という夢に向け、ファジアーノと大学生の交流イベントを企画
マッチングプログラムコース4年 児玉 怜さん
広島で3歳の頃から、高校までの一貫型のインターナショナルスクールに通っており、そこの高校課程でIBプログラムを受けました。岡山大学を受験しようと思ったのは、マッチングプログラムコース(※)の存在です。一つの学問分野にとらわれず幅広い視点をもちたいと思う自分にとって、いろいろな学部の内容を学んだうえで自分の専門分野を決めることができるこのコースはぴったりでした。母校からは岡山大学に進学した人がおらず情報も少なかったのですが、調べていくうちに、グローバル化にも力を入れていると知ってどんどん魅力を感じていきました。家族とあまり遠くに離れたくなかったので、広島に近くて交通の便がいいのも良かったところですね。
授業の他に打ち込んだことといえば、サークル活動ですね。サッカーJ2・ファジアーノ岡山を盛り上げるサークルに入り、代表も務めました。母校でクラスメイトの外国人を近隣の日本人の友達に紹介した際、「外国人の人と知り会えたのは初めて」と喜んでもらえた経験があり、それ以来「人と人とを結びつける役に立つ」のが夢でした。このサークルに入ったのも、単純に楽しそうだったからというのもありますが、ファンと選手や、ファン同士の交流を活発にしようとするサークルの活動が夢につながっていると感じたからでもあります。
(2021.02.24)
英語力を生かして、日本と世界をつなげる人に
医学部医学科6年 住田 まどかさん
岡山大学医学部にIB入試が導入された最初の年に受験しました。IB入試を受けられる日本国内の医学部を探していて、岡山大学に問い合わせた際、とても歓迎してくださったことを覚えています。まだ日本でIB入試を導入している大学が少なかった中、「積極的にIBの良さを広めていきたい」という岡山大学の思いが伝わってきて、受験を決めました。
岡山大学に入学してすぐの頃は、他の新入生たちが入試の話で盛り上がっている輪に入れなくて少し困りました(笑)。ですが、入学後も、医学部の先生方をはじめ多くの先生に「困っていることはない?」と気にかけていただけたのがとてもありがたく、周りともすぐに打ち解けられました。
(2021.02.24)
学長メッセージ
岡山大学×SDGs 大学概要
公表事項
大学情報
法人としての取組
広報活動 点検・評価
キャンパス案内
情報公開・個人情報保護
特色ある教育・研究
病院・図書館・共用施設